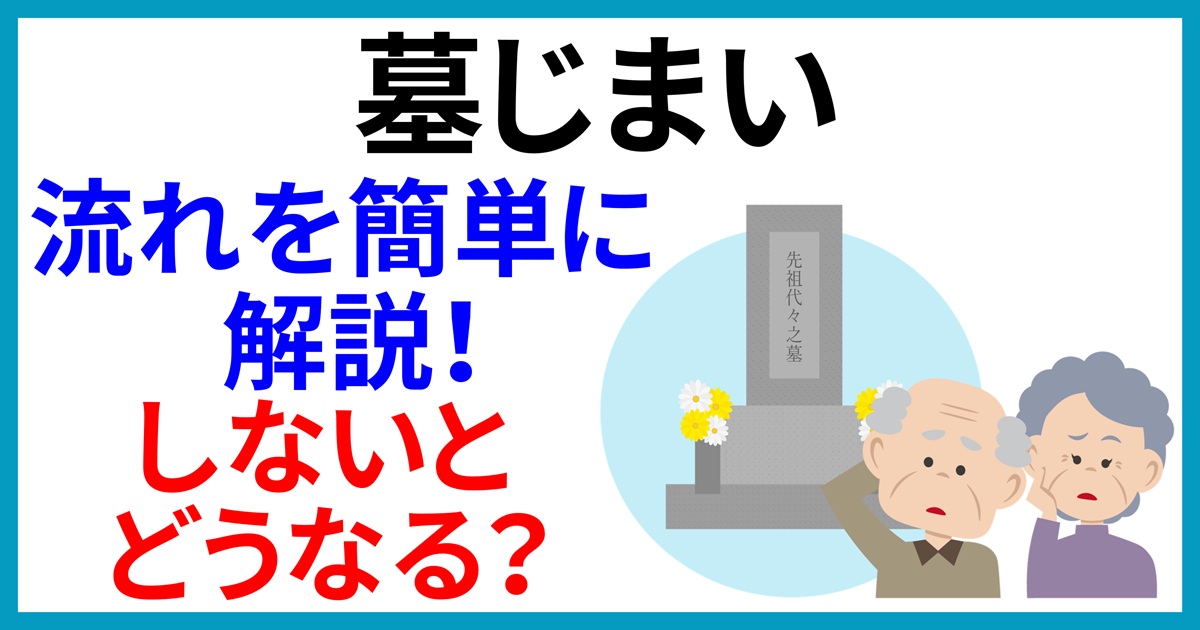
多くのご家庭では、お墓や納骨堂を利用していますが、最近はさまざまな事情で「墓じまい」をするご家庭も増えています。
では、墓じまいは、どのように行うのでしょうか?
墓じまいをしないとどうなるのでしょうか?
墓じまいの流れなどを簡単にわかりやすく解説いたします。
墓じまいとは?
菩提寺(ぼだいじ)にあるお墓を撤去して更地に戻すことです。
納骨堂の場合も「墓じまい」といいます。
「じまい」の部分は漢字で「墓仕舞い」や「墓終い」と書きますが、一般的には「墓じまい」とひらがなで書きます。
菩提寺とは、檀家(だんか)が所属するお寺のことです。
檀家とは、お寺にお布施や会費などを納める代わりに、葬式や法事などを執り行ってもらう家のことです。
関連:檀家とは?簡単にわかりやすく説明します!檀家をやめることはできる?
墓じまいで不幸になる?
墓じまいをすることでご先祖様が祟り、不幸が起きたり体調不良になったりするという人もいますが、科学的根拠のない迷信です。
墓じまいは、そのお墓・納骨堂にいらっしゃるご先祖様を新しい場所で供養することなので、ご先祖様が祟ることはないと考えましょう。
墓じまいで後悔する?
墓じまいで後悔する人もいます。
理由は以下のとおりです。
- 予想以上にお金がかかってしまった
- 親族間でトラブルとなった
- 散骨にしたため、手を合わせる場所がなくなった
など、さまざまな後悔がありますので、墓じまいをする際には親族ときちんと話し合って、納得できる方法を選んでください。
墓じまいの流れを簡単にわかりやすく解説!
墓じまいの流れを簡単にわかりやすくご紹介します。
自治体によっては必要な書類などが異なる場合があります。
墓じまいをする際には、自治体にどの書類が必要なのか確認してください。
納骨堂の場合も基本的に同じ流れです。
①遺骨の行き先を決める
墓じまいしたあと、遺骨をどうするのか決めます。
- 管理しやすい自宅近くのお墓や納骨堂に移す
- 自宅で保管する
- 永代供養(えいたいくよう)
- 樹木葬(じゅもくそう)
- 散骨(さんこつ)
などの方法があります。
永代供養、樹木葬、散骨について解説します。
永代供養とは?
永代供養とは、遺族に代わり、霊園や寺院などが遺骨の管理・供養をすることです。
永代は「長い期間」という意味があり、「霊園や寺院などが長い期間管理・供養する」ということです。
「長い期間」は、年忌法要(ねんきほうよう)を区切りにすることが多く、霊園や寺院によって異なります。
短いところでは三回忌、七回忌を区切りとしたり、長いところだと三十三回忌や五十回忌が区切りとなります。
年忌法要とは、人が亡くなってから一定の期間で行う法要のことです。
年忌法要についての詳細はこちらをご覧ください。
関連:法要とは?法事との違い。初七日、四十九日の意味とは?忌日・年忌法要とは?
寺院で永代供養を行う場合、基本的に檀家になる必要はありません。
永代供養は主に以下の3つの方法があります。
●最初から合祀(ごうし)する
合祀とは、他の人の遺骨と一緒にされることです。
そのため、後から遺骨を取り出すことが不可能となります。
●一定期間経過後に合祀する
期間は霊園や寺院によって異なります。
●合祀しない
霊園や寺院が存続する限り、合祀しません。
樹木葬とは?
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標とすることです。
基本的に骨壺を使わず、遺骨をそのまま土の下に埋葬し、最終的には遺骨が土にかえることになります。
樹木葬は永代供養の一種です。
永代供養は供養の方法、樹木葬はお墓の種類と考えるとわかりやすいです。
樹木葬にはいくつかのタイプがあります。
●合祀型
1本の樹木を墓標に、合祀します。
●個別型
ひとりひとりに区画があり、区画ごとに樹木を植えます。
個人、夫婦、家族などの単位で埋葬することができます。
●集合型
1本の樹木を墓標に、周りに区画を作って複数人の遺骨を埋葬します。
合祀と異なり区画が分かれています。
散骨
散骨とは、火葬後の遺骨を粉末状にしたあと、海や山、空、宇宙などに撒くことです。
●海への散骨
船に乗って沖合まで行き、散骨します。
●山への散骨
業者が管理する山や、所有者が許可した山に行き、散骨します。
●空への散骨
ヘリコプターや小型飛行機で許可されたエリアに行き、散骨します。
●宇宙への散骨
遺骨を載せたロケットを宇宙空間まで飛ばし、散骨します。
散骨は法律で禁止されていませんが、散骨をする場所については自治体などが制限を設けている場合があります。
そのため、個人で自由に散骨を行わず、専門の業者に依頼するのが一般的です。
②手続きに必要な書類を集める
墓じまいには、現在のお墓や納骨堂から遺骨を移動する必要があります。
遺骨を移動するには「改葬許可証」が必要になります。
※自宅で遺骨を保管する場合や散骨をする場合は原則不要ですが、自治体によっては必要な場合がありますのでご確認ください。
※永代供養と樹木葬は「改葬許可証」が必要になります。
改葬許可証を発行してもらうには、
- 「改装許可申請書」
- 「受入証明書」
- 「埋蔵証明書」
を役所に提出しなければなりません。
「改装許可申請書」「受入証明書」「埋蔵証明書」について説明します。
「改葬許可証申請書」とは?
自治体に遺骨の引っ越しを認めてもらうための書類です。
「改葬許可証申請書」は、現在のお墓や納骨堂がある自治体の役所でもらって記入します。
「受入証明書」とは?
「受入証明書」は、新しい墓地や納骨堂の管理者が「遺骨を受け入れます」という証明書です。
新しい墓地や納骨堂の管理者にお願いして作成してもらいます。
「受入証明書」の書式に特に決まりはありません。
「埋蔵証明書」とは?
移動する遺骨がお墓や納骨堂に埋葬されていることを証明するためのものです。
菩提寺にお願いして作成してもらいます。
「埋蔵証明書」の書式に特に決まりはありません。
③「改葬許可証」を発行してもらう
2で集めた「改装許可申請書」「受入証明書」「埋蔵証明書」を現在のお墓や納骨堂がある自治体の役所に提出し「改葬許可証」を発行してもらいます。
「改葬許可証」が発行されれば、遺骨を動かすことが可能になります。
④「改葬許可証」を菩提寺に確認してもらう
菩提寺に「改葬許可証」を確認してもらい、遺骨を移動することを承認してもらいます。
遺骨を取り出す日程を菩提寺と相談しましょう。
⑤閉眼供養(へいがんくよう・へいげんくよう)を行う
閉眼供養とは、お墓や納骨堂に宿っている故人の魂を鎮めて抜き取る供養のことで、魂抜き(たましいぬき・こんぬき・たまぬき)ともいいます。
閉眼供養は、お墓や納骨堂から遺骨を取り出す日、または、お墓を撤去する前に菩提寺によって行われます。
閉眼供養の日程も菩提寺と相談して決めましょう。
⑥遺骨を取り出し、移動する
遺骨を取り出した後は、
- 菩提寺から新しい墓地へ墓石などを移動させ、そこに遺骨を埋葬する
- 菩提寺の墓石は処分して新しく墓石を建てて、遺骨を埋葬する
- 樹木葬にする
- 散骨にする
- 自宅で保管する
など、ご家庭によってさまざまです。
自宅で遺骨を保管する場合と散骨の場合、「改葬許可証」は原則不要ですが、自治体や散骨業者によっては必要となる場合がありますので事前にご確認ください。
「改葬許可証」が不要の場合は、2~4は省略となり、
- ①遺骨の行き先を決める
- ⑤閉眼供養
- ⑥遺骨を取り出し、移動する
の順序で遺骨を移動することになります。
⑦墓地を更地にする
石材店に依頼し、墓石を撤去して墓地を更地にしてもらいます。
お寺によっては石材店を指定するケースもありますので、事前に菩提寺に確認をしておきましょう。
撤去費用は、1㎡あたり10万円~15万円が相場です。
自治体によっては、墓石の撤去に補助金が出ることがあります。
墓じまいの際には、自治体に補助金があるのかどうか確認してください。
墓じまいで遺骨を移す先での費用
永代供養の費用
永代供養の相場は5万円~150万円程度と、費用に幅があります。
これは、管理・供養の仕方が異なるためです。
おおよそ、以下のようになっています。
●最初から合祀(ごうし)する場合の相場は、 5万円~30万円
●一定期間経過後に合祀する場合の相場は、20万円~60万円
●合祀しない場合の相場は、50万円~150万円
樹木葬の費用
樹木葬の費用の相場は5万円~100万円程度と、費用に幅があります。これは、一本の樹木に対する人数や、区画の広さなどによって費用が変わるからです。
●合祀型の相場は、5万円~30万円
●集合型の相場は、20万円~60万円
●個別型の相場は、40万円~100万円
散骨の費用
散骨費用の相場は3万円~200万円程度と、費用に幅があります。
これは、散骨する場所や方法、家族の立ち合いの有無などによって費用が変わるからです。
●海への散骨の相場は、3万円~40万円
●山への散骨の相場は、10万円~30万円
●空への散骨の相場は、20万~60万円
●宇宙への散骨の相場は、30万円~200万円
このように、墓じまいのあと遺骨をどうするのかによって費用が変わってきます。
費用を抑えたい場合は、なるべくお金がかからない方法を選ぶようにして、親族で話し合ってください。
墓じまいしないとどうなる?
墓じまいにはお金も時間もかかります。
お金がない人や、高齢者、体調を崩している人など、墓じまいの手続きを行えない場合もあるでしょう。
諸事情で墓じまいをせずに、お金も払わず、お墓・納骨堂を放置すると、以下のようなことが起こります。
訴訟される可能性がある
管理費が未納の場合、督促状などが届くようになります。
督促状を無視し続けると訴えられる可能性があります。
無縁仏になってしまう
無縁仏とは、供養してくれる人(遺族や子孫)がいない故人や、管理する人がいなくなったお墓のことです。
墓地・納骨堂の管理者が、墓地・納骨堂の所有者と一定期間連絡が取れなくなった場合、無縁仏になることがあります。
無縁仏になると墓石などが撤去され、遺骨は合祀されるのが一般的です。
合祀されたあと、故人の遺骨を取り出すことは不可能となります。

先祖代々のお墓を諸事情で墓じまいする人は増えています。
遺骨を移動するだけでもいろいろな書類が必要となり少々面倒だと思いますが、親族や菩提寺と話し合いながら、手続きを一つずつクリアしていってくださいね。
関連:お墓参りはいつ行けばいいの?時期や服装、マナーについて
関連:【2026年】お彼岸はいつ?お彼岸の意味とお盆との違い

コメント