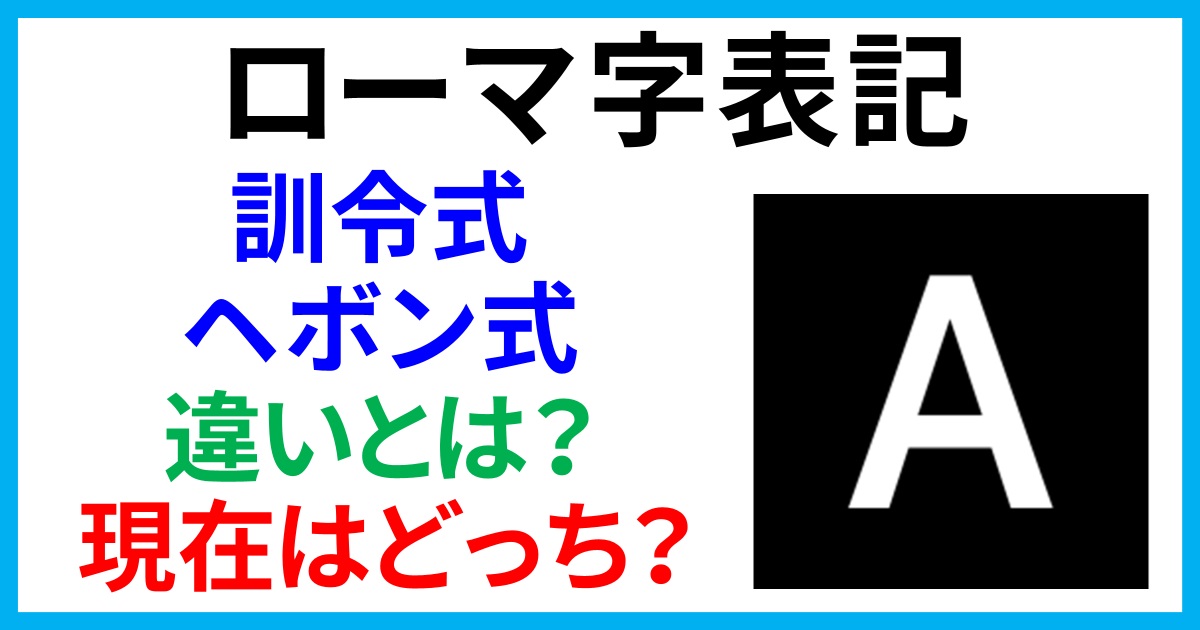
ローマ字の表記には「訓令式」と「ヘボン式」があります。
どのような違いがあるのでしょうか?
また、現在はどちらが使われているのでしょうか?
今回は、ローマ字について解説いたします。
ローマ字とは?
ローマ字は、日本語の発音をラテン文字で表記したものです。
ラテン文字は、古代ローマで使われていた文字であることから、ローマ字と呼ばれています。
英語をはじめ欧米などで使われる言語のアルファベットはラテン文字から派生しています。
そのため、英語のアルファベットとローマ字は同じ文字が使われているのです。
日本でローマ字が使われるようになったのは、室町時代(1336年~1573年)です。
1549年にカトリックの宣教師であるフランシスコ・ザビエル(1506年~1552年)がポルトガルから日本にやってきてからだといわれています。

布教のために来日した宣教師たちは日本語を学び、ポルトガル語に基づいた「ポルトガル式ローマ字」の綴り方を考案し、日本についてローマ字で記録しました。
その後、日本とオランダの交流が盛んになると、オランダ語に基づいた「オランダ式ローマ字」が考案されます。
「ポルトガル式ローマ字」と「オランダ式ローマ字」は、日本人の間に広まることはなく、ごく一部の学者などが使っていただけです。

江戸時代(1603年~1868年)の1853年、浦賀にペリーが来航したことにより英語が日本に広まります。
1867年、来日していたアメリカの医師であり牧師でもあるジェームス・カーティス・ヘボン(1815年~1911年)が英語に基づいたローマ字で和英辞書「和英語林集成(わえいごりんしゅうせい)」を書きました。
ジェームス・カーティス・ヘボン
引用:wikipedia
和英語林集成は、ローマ字の見出しにカタカナ表記と漢字表記を添え、英語で言葉の意味などを記しています。
これが、英語とローマ字と日本語で書かれた最初の日本語辞典です。
ローマ字表記「訓令式」と「ヘボン式」とは?
ローマ字表記には「訓令式」と「ヘボン式」があります。
以前は「日本式」というものもありました。
「ヘボン式」は、先ほども登場したジェームス・カーティス・ヘボンに由来しています。
子音を英語風に、母音をイタリア語風にして発音しているのが特徴です。
ヘボン式は英語の発音に近かったため、日本語の表記としてはふさわしくないという意見がありました。
田中舘愛橘
引用:wikipedia
そこで、明治18年(1885年)に物理学者である田中舘愛橘(たなかだてあいきつ・1856年~1952年)が日本語の発音に基づく「日本式」を考案しました。
しかし、英語の発音に近い「ヘボン式」から「日本式」にすることを英語教育者などから猛反対され、「ヘボン式」と「日本式」どちらにするのか激しい議論が続きました。
その議論を収束させるため、昭和12年(1937年)に「ヘボン式」と「日本式」を統一し、誕生したのが「訓令式(くんれいしき)」です。
しかし、「訓令式」には「日本式」が多く取り入れられたため、「ヘボン式」排除を猛反対していた人たちに受け入れられることはありませんでした。
そして、昭和29年(1954年)に、日本政府は「ローマ字のつづり方」として「訓令式」の表記を告示(こくじ)しました。
告示とは、公式に広く一般に知らせることです。
現在はどっち?
これまで小学校の教科書などでは、告示に基づいて基本的に「訓令式」が使われてきました。
しかし、文化庁は令和7年(2025年)7月、社会で一般的に使われている「ヘボン式」を基本とする表記ルールに改める方針を発表しました。
そして同年12月22日、政府は昭和29年(1954年)以来続いてきた「ローマ字のつづり方は訓令式」という告示を廃止し、英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とする新しいルールに変更する方針を決定しました。
この変更により、2026年度以降に発行される教科書などでも、順次ヘボン式が採用される見込みです。
ただし、すでに定着している用語についてはすぐに変更するよう求めてはおらず、個人名や団体名については当事者の意思を尊重するとしています。
ローマ字表記の改定案は以下のとおりです。
| あ a |
い i |
う u |
え e |
お o |
|||
| か ka |
き ki |
く ku |
け ke |
こ ko |
きゃ kya |
きゅ kyu |
きょ kyo |
| さ sa |
し shi |
す su |
せ se |
そ so |
しゃ sha |
しゅ shu |
しょ sho |
| た ta |
ち chi |
つ tsu |
て te |
と to |
ちゃ cha |
ちゅ chu |
ちょ cho |
| な na |
に ni |
ぬ nu |
ね ne |
の no |
にゃ nya |
にょ nyu |
にょ nyo |
| は ha |
ひ hi |
ふ fu |
へ he |
ほ ho |
ひゃ hya |
ひゅ hyu |
ひょ hyo |
| ま ma |
み mi |
む mu |
め me |
も mo |
みゃ mya |
みゅ myu |
みょ myo |
| や ya |
ゆ yu |
よ yo |
|||||
| ら ra |
り ri |
る ru |
れ re |
ろ ro |
りゃ rya |
りゅ ryu |
りょ ryo |
| わ wa |
(を) (o) |
||||||
| が ga |
ぎ gi |
ぐ gu |
げ ge |
ご go |
ぎゃ gya |
ぎゅ gyu |
ぎょ gyo |
| ざ za |
じ ji |
ず zu |
ぜ ze |
ぞ zo |
じゃ ja |
じゅ ju |
じょ jo |
| だ da |
(ぢ) (ji) |
(ず) (zu) |
で de |
ど do |
ぢゃ (ja) |
ぢゅ (ju) |
ぢょ (jo) |
| ば ba |
び bi |
ぶ bu |
べ be |
ぼ bo |
びゃ bya |
びゅ byu |
びょ byo |
| ぱ pa |
ぴ pi |
ぷ pu |
ぺ pe |
ぽ po |
ぴゃ pya |
ぴゅ pyu |
ぴょ pyo |
| ん n |
|||||||
※括弧をつけたつづりは、現代において、別のかなに対応する音と同じ発音をするものとして扱われるため、このつづり方においては使い分けをしない。
これまで日本政府は、公式には「訓令式」を正式なローマ字としながらも、「ヘボン式」や「日本式」でも差し支えないとしていました。
「訓令式」と「日本式」は非常に似ており、一般には区別されることはほとんどありません。
現在の日本では、「訓令式」と「ヘボン式」が入り交じって使われているのが実情です。
しかし、すでに説明したとおり、2026年度以降の教科書などで順次ヘボン式が採用される見込みです。
ただし、すでに定着している用語や個人名、団体名については当事者の意思を尊重するとしていますから、今後も「訓令式」と「ヘボン式」の両方の表記が存在することになります。
ローマ字表記「訓令式」と「ヘボン式」の違いとは?
「ヘボン式」「訓令式」「日本式」のローマ字表記の主な違いは以下の通りです。
| 日本語 | 訓令式 | ヘボン式 | 日本式 |
| し | si | shi | si |
| しゃ しゅ しょ |
sya syu syo |
sha shu sho |
sya syu syo |
| じ | zi | ji | zi |
| じゃ じゅ じょ |
zya zyu zyo |
ja ju jo |
zya zyu zyo |
| ち | ti | chi | ti |
| ちゃ ちゅ ちょ |
tya tyu tyo |
cya chu cho |
tya tyu tyo |
| ぢ | zi | ji | di |
| ぢゃ ぢゅ ぢょ |
zya zyu zyo |
ja ju jo |
dya dyu dyo |
| つ | tu | tsu | tu |
| づ | zu | zu | du |
| ふ | hu | fu | hu |
| を | o | o | wo |
| ん | n | n または m (d,m,pの前 はm) |
n |
表記の違いは、たとえば以下のようになります。
「社会」は
訓令式では「syakai」
ヘボン式では「shakai」
「砂利」は
訓令式では「zyari」
ヘボン式では「jari」
「愛知」は
訓令式では「aiti」
ヘボン式では「aichi」
「福岡」は
訓令式では「hukuoka」
ヘボン式では「fukuoka」
小学校では「訓令式」を学びますが、大人になってからは「ヘボン式」を使う人が多いといわれており、日常生活では「ヘボン式」が使われている場面の方が多いです。
たとえば、パスポートの名前は「ヘボン式」での記入が基本ですし、駅名や地名なども「ヘボン式」が多いです。
令和7年(2025年)現在、文部科学省は「ヘボン式のほうが広く浸透している」ということを踏まえ、昭和29年(1954年)の告示を廃止し、基本的に「ヘボン式」となりました。
※ローマ字表記の改定案が正式にいつから採用されるのか、パスポートや駅名などが今後どのように変更されるのか、2025年12月時点では不明です。

ローマ字表記にはいろいろな種類があることがわかりましたね。
小学校で習ったものと普段目にするものに違いがあったら、子どもたちは混乱してしまいますよね!
大人でも、「新宿」の表記が「Sinzyuku(訓令式)」と「Shinjuku(ヘボン式)」どちらもあるので「どっちが正解なの?!」と混乱してしまいます。
2025年7月にローマ字の改定案が出されましたが、絶対にその改定案で表記せねばならない!というものではありません。
いずれの表記も間違いではないということを覚えておきましょう。
関連:常用漢字とは?小学校・中学校で習う漢字の数はいくつ?常用漢字一覧


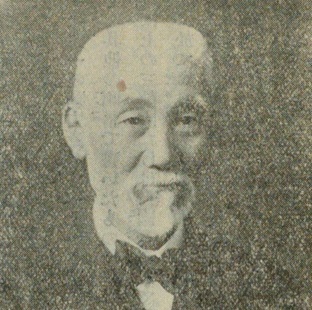
コメント