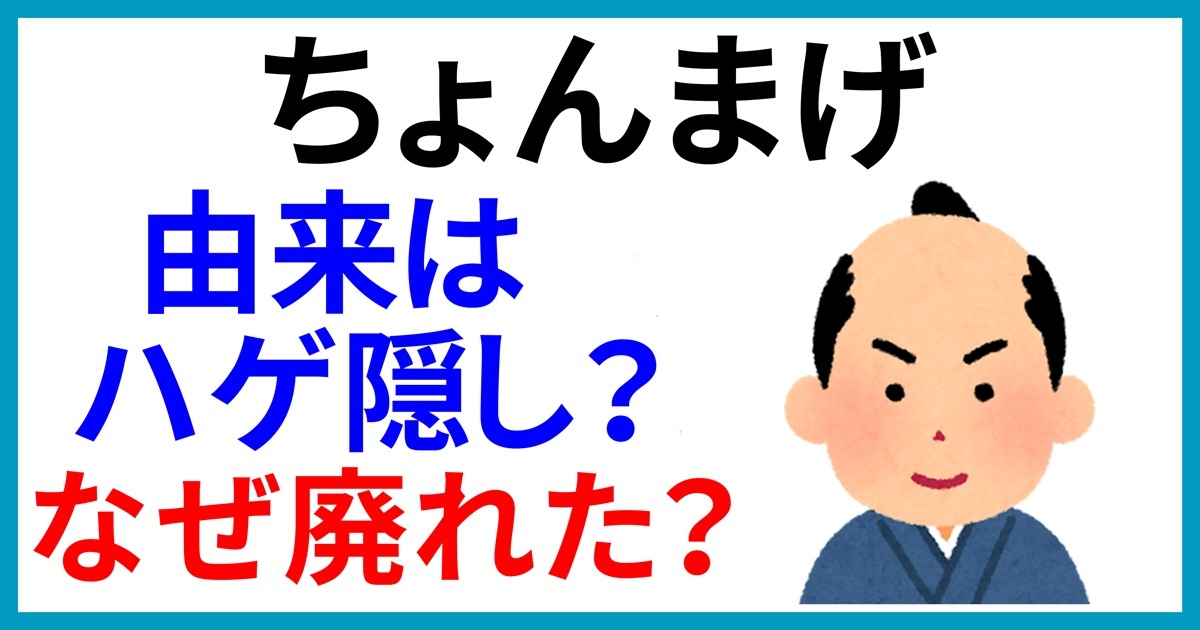
昔の日本の男性の髪型といえば「ちょんまげ」ですよね。
ちょんまげの由来はハゲ隠しといわれているのですが、本当でしょうか?
ちょんまげはなぜ流行り、なぜ廃れたのでしょう?なぜ剃るのかも気になりますよね。
ちょんまげの由来や歴史、種類などを解説いたします。
ちょんまげとは?
漢字で「丁髷」と書きます。
歴史的には、江戸時代(1603年~1868年)の男性に見られた髪型であり、特に月代(さかやき)といって前頭部から頭頂部にかけて髪の毛を剃り上げ、残った髪で髷(まげ)を結ったものを指します。

月代(青い部分)
「月代」は半月形に剃ることが語源といわれており、もともと毛抜きで髪の毛を1本1本抜いていましたが、安土桃山時代ごろに剃刀で剃るようになりました。
また、髷(まげ)とは、頭の高い位置で髪を束ねて結んで折り曲げたものです。
ちょんまげという言葉自体は、明治時代以降に広まったものです。
ちょんまげは、もともとは「ゝ髷」と書き、「ゝ(ちょん)」は少ない、小さいという意味があります。
老人など髪の毛が少なくなった人の髷が「ゝ」という字に似ていることから、それを揶揄した言葉として「ゝ髷」と呼ばれるようになったといわれています。
のちに「ゝ」は「丁」という字が当てられ「丁髷」という表記になりました。
現在は、月代があってもなくても江戸時代の男性が髷を結ったものはすべて「ちょんまげ」と呼ぶのが一般的です。
髷にはいろいろな種類があり、大相撲の力士の髪形も髷を結うので「ちょんまげ」と呼ばれています。
ここからは髷を結った髪形を「ちょんまげ」として解説していきます。
ちょんまげの由来とは?
ちょんまげの由来は飛鳥時代(592年~710年)~奈良時代(710年~794年)ごろだといわれています。
このころ、中国から烏帽子(えぼし)が日本に伝わりました。

烏帽子とは黒い帽子のことで、烏(からす)のように黒いことが名前の由来です。
絹に漆を塗って作られています。
現在でも大相撲の行司や神社の神職などが烏帽子を着用しています。
烏帽子はそのままでは頭に固定できないため、頭頂部で髻を作って烏帽子の中に入れ、紐などで烏帽子と髻を結んで固定していました。
これがちょんまげの由来といわれています。
鎌倉時代(1185年~1333年)になると武士の時代が始まりました。
武士は戦の時には兜をかぶりますが、その際、兜の中で頭が蒸れないように月代を作り、残った髪の毛を高い位置で結うようになりました。
室町時代(1336年~1573年)~安土桃山時代(1573年~1603年)になると月代を作るちょんまげは武士の髪形として定着しました。
江戸時代(1603年~1868年)になると、ちょんまげは町人にも広まりました。
江戸時代のちょんまげは年齢や身分、職業などでいろいろなバリエーションが生まれました。
ちょんまげの種類は後ほどご紹介します。
ちょんまげはハゲ隠し?

ちょんまげは見た目から「ハゲ隠しが由来ではないか」と思う人もいるようですが、烏帽子を固定するために髪の毛を束ねて入れるようになり、戦で兜の蒸れを無くすために月代を作るようになりました。
ハゲを隠すためにちょんまげが誕生したわけではありません。
ちょんまげはなぜ流行り、なぜ廃れた?
先ほど説明したとおり、ちょんまげは、武士の髪形として定着し、江戸時代になると町人にも広まりました。
その頃の人々は職業や身分を表したり、オシャレのためにちょんまげをするようになり、江戸時代の男性の一般的な髪形として流行りました。
しかし、明治4年(1871年)に明治政府が散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい、通称:断髪令)を出したことをきっかけに廃れていきます。
散髪脱刀令は、
●ちょんまげ以外の髪型にしても良い(髪型は自由にして良いということ)
●帯刀(たいとう・刀を装備すること)しなくても構わない
という法令で、ちょんまげを禁止したものではありません。
散髪脱刀令が出る前は、ちょんまげは強制されていたわけではありませんが、ごくごく当たり前の髪形として定着しており社会的に「しなければならない」髪型になっていました。
散髪脱刀令によって「しなければならない」から「ちょんまげにしなくてもよい」となったわけです。

明治天皇
しかし、明治6年(1873年)に明治天皇が短く散髪したことで官吏(かんり・国家公務員のこと)を中心に短髪にする人が増えていきました。
また、このころは洋装の人も増えましたが、ちょんまげは洋装には合わないため、ちょんまげをする人は減っていきました。
ちょんまげの人がいなくなったのが明確にいつなのかは不明ですが、明治時代の終わりごろではないかと言われています。
つまり、男性の髪形がいつからいつまでちょんまげだったのかというと、室町時代~明治時代初期までということになります。
ただ、現在でも大相撲の力士はちょんまげをしていますし、ファッションとしてちょんまげをする人もいますので完全になくなったわけではありません。
ちょんまげの種類
江戸時代にちょんまげはいろいろな種類が登場しましたのでご紹介します。
ちょんまげ
最初に説明したとおり、ちょんまげは江戸時代(1603年~1868年)に男性の間で流行った髪型で、厳密には「月代」を半月形に剃り上げ、残った髪で髷(まげ)を結ったものを指します。
一般的には男性が髷を結った髪型をすべて「ちょんまげ」と呼びます。
銀杏髷(いちょうまげ)
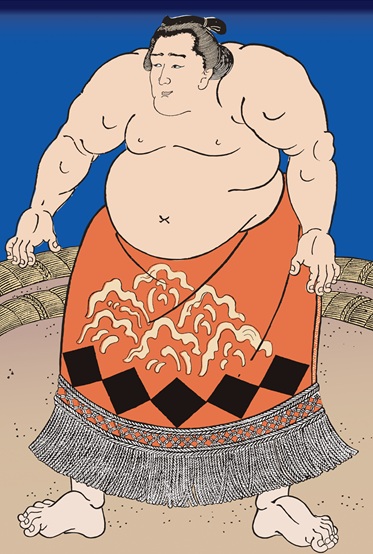
結った髪の毛の先がイチョウの葉のように広がったもので、江戸時代に最も多かった髪型です。
銀杏髷は大銀杏(おおいちょう)と小銀杏(こいちょう)があります。
大銀杏は髪の毛の先が大きく広がったもので、武士や力士に多い髪型です。
小銀杏は髪の毛の先がやや小ぶりで、商人や町人に多い髪型です。
また、浪人(ろうにん・主君を持たない武士)は節約のために月代を作らず銀杏髷を結っていたので、その髪型を「浪人銀杏(ろうにんいちょう)」と呼びました。

浪人銀杏
また、力士については、江戸時代の初期から中期にかけては、月代を作る髪型が一般的だった時期もありますが、時代が下るにつれ、月代を作らず髪を伸ばして大銀杏を結う現在のスタイルが定着していきました。
これは、力士は見栄えや強さの象徴として豊かな髪を重視したためといわれています。
十両以上の力士になると「大銀杏」を結うことができます。
本田髷(ほんだまげ)

月代部分を大きくすることで髪の毛の広がりが少なくなる髪型で、男らしさを演出する目的があったそうです。
遊び人や商人の息子など富裕層に人気でした。
若衆髷(わかしゅまげ)

月代を狭く作り、髷そのものも小さく作るもので、若者や少年向けの髪形です。
茶筅髷(ちゃせんまげ)
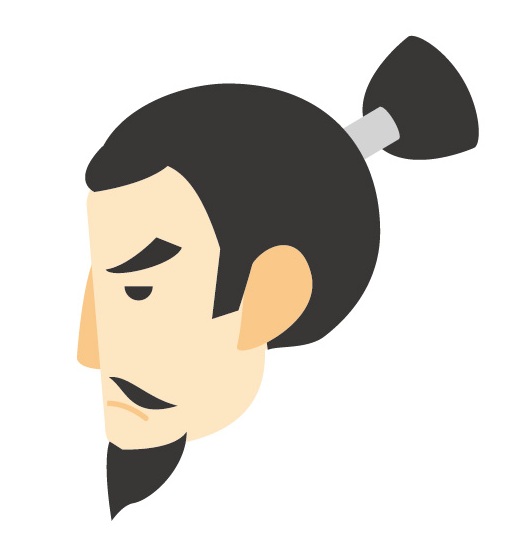
江戸時代には廃れていましたが、安土桃山時代に生まれ戦国時代に奇抜なものを好む「傾奇者(かぶきもの)」たちの間で流行しました。
毛先を茶筅のようにした髪型です。
茶筅とは、抹茶を点てるときにかき混ぜるための道具です。
総髪(そうはつ)

月代を作らずに、前髪は後ろになでつけて髪の毛をひとつに結うだけの髪形です。
江戸時代初期は医者や学者など、江戸時代後期から明治時代にかけては武士や浪人などにも多くみられました。

ちょんまげはハゲ隠しではなかったのですね。
わざわざ髪の毛を剃って月代を作るのは大変なことだったと思いますが、戦国時代よりも前は髪の毛1本1本を抜いていたのですから驚きですよね。
戦のない江戸時代には武士以外の男性もちょんまげを作るようになり、いろいろなバリエーションのちょんまげが誕生しました。
時代劇を見るときにはちょんまげに注目してみるのも面白いかもしれませんよ。
関連:きんぴらごぼうの「きんぴら」の語源と意味とは?なぜきんぴらなの?

コメント