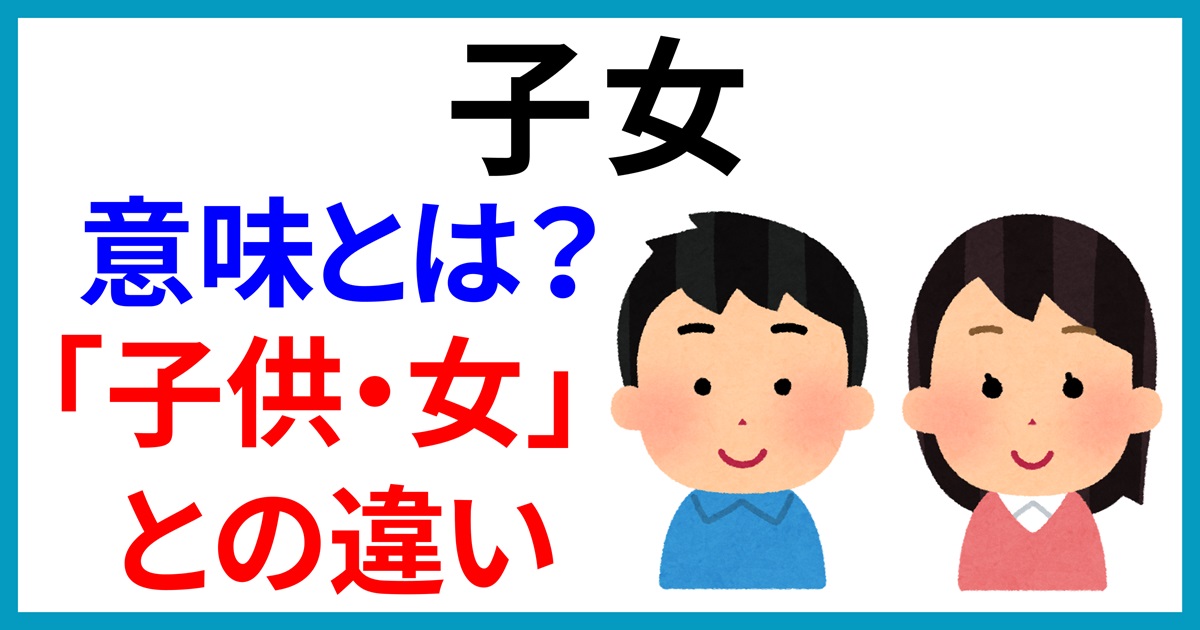
「子女」という言葉はあまり馴染みがありませんが、どのような意味があるのでしょう?
字をみると「女と子供」を表しているように思いますが、違いはあるのでしょうか?
「子女」の意味と「女・子供」との違い、子女の使い方と言い換え表現について解説いたします。
「子女」の意味とは?
読み方は「しじょ」です。
子女には、「息子と娘」という意味と、「子供」という意味があります。
また、「子女」は大人に対しても使われることがあります。
「子女」と「子供・女」との違いとは?
「子女」のことを「女や子供」と思って差別的な表現だという人もいますが、「子女」の漢字の意味を知るとそれが間違いだと気づきます。
それぞれの漢字の意味は「子」は息子・男の子供、「女」は娘・女の子供のことです。
息子は「子」なのに、娘はなぜ「女」なのか不思議ですよね。
なぜ「子=息子・男の子供」「女=娘・女の子供」なの?
まず「子=息子・男の子供」について説明します。
もともと「子」という漢字は男女ともに使われていましたが、男系継承が重視されていた古代中国では「子」が男子を指す風潮が強まり、跡取りや家を継ぐ存在(息子)としての意味をもつようになったのです。
このような経緯がある「子」は男の子供や息子を指すのです。
「子」は男子の通称や尊称(そんしょう・尊敬の気持ちを込めた呼び方)としても用いられています。
たとえば思想家である孔子(こうし)や孟子(もうし)などがその例です。
飛鳥時代(592年~710年)の日本でも中国に倣い、身分の高い男性の名前に「子」が用いられており、小野妹子(おののいもこ)や蘇我馬子(そがのうまこ)などが有名です。
また、日本では「子」は女性の名前によく用いられていますよね。
その経緯については以下のリンク先をご覧ください。
関連:明治・大正・昭和の女性の名前に「カタカナ二文字」や「〇子」が多かった理由
次に「女=娘」について説明します。
「子女」の「女」は、そのまま「女の子供」を指します。
現在、女の子供のことを「娘(むすめ)」といいますが、もともとは「女」と書いて「むすめ」と読んでいました。
平安時代ごろの女性の名前は記録に残ることがほとんどなく、「〇〇の女(むすめ)」と書かれていました。(母の場合は「〇〇の母」)
たとえば、源氏物語の作者である紫式部は「藤原為時女(ふじわらのためときのむすめ)」、更級日記の作者は「菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)という名前で表記されています。
ほかの「子女」と同じ例としては、「王子」は王の息子を表し、「王女」は王の娘を表しているように、「子」は息子・男の子供、「女」は娘・女の子供を表しています。
「息子」と「娘」の成り立ち
息子と娘という成り立ちについても触れておきましょう。
息子(むすこ)と娘(むすめ)は「むす」が共通しています。
この「むす」は、苔や草が生い茂って繁殖するという意味があります。
君が代の「苔のむすまで」の「むす」も漢字で「産す」または「生す」と書きます。
そして「産す・生す」に男性を表す「子」をつけて「むすこ=産す子・生す子」、女性を表す「女」をつけて「むすめ=産す女・生す女」になったといわれています。
また、「息子」の「息」は、生命や息吹を表し「生息する」「生きている」という意味があり、「産す・生す」と同じ意味があることから「息子」と書くようになったといわれています。
男の子を「息子(むすこ)」と書くのなら、女の子は「息女(むすめ)」と書けばいいのでは?と思いますが、「息女」は「そくじょ」と読むのが一般的です。
「息女(そくじょ)」は特に身分の高い人の娘や、敬語として他人の娘のことを言う言葉です。
たとえば「田中さんの娘」を敬語にすると「田中さんのご息女」です。
ちなみに、「息子」の敬語は「ご子息(しそく)」です。
詳細は不明ですが、「むすこ」には「息子」という漢字を当て、「むすめ」は「息女」ではなく「体がしなやかな少女」という意味の「娘」という漢字を当てられました。
「子女」の使い方

「子女」の使い方としては、「帰国子女(きこくしじょ)」がという言葉をよく見聞きするのではないでしょうか?
帰国子女とは、親の仕事の都合などで、子供時代に海外で1年以上過ごして帰国した人のことです。
帰国子女の場合の子供時代とは、小学校~中学校(6歳~15歳)の期間内です。
そして、その期間に海外で過ごした人であれば大人でも「帰国子女」というのが一般的です。
また、子供だけで海外に行って教育を受ける留学の場合は帰国子女という言葉は使いません。
ただし、「海外経験のある日本人」というイメージで認知されていることもあり、その場合も「帰国子女」が使用されるケースがあります。
「子女」は古い言い回しなので日常的に使われることは少ないですが、法律ではよく使われています。
たとえば、義務教育について定めた憲法第26条第2項では
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」
のように記されています。
「子女」と「子供」の違いとは?
子女には、「息子と娘」という意味と、「子供」という意味があります。
「子供」とは、年齢の若い人、幼い人、児童、などの意味があります。
しかし、「子供」の定義は曖昧です。
たとえば、国際連合の児童の権利に関する条約では「子供」は「18歳未満のすべての者」を指します。
地域のイベントなどで「子供参加無料」と会った場合、12歳未満だったり、15歳未満だったりとさまざまです。
「子女」と「子供」の違いをまとめると以下ようになります。
年齢で区切られるかどうか
「子女」は明確な年齢の区切りがありません。「帰国子女」の場合は大人になってからも使われます。
「子供」は主に未成年者を指します。
使われる場面が違う
「子女」は古い言い回しなので、日常会話で使うことはほとんどありません。
「子供」は日常会話でも使われる言葉です。
「子女」の言い換え表現
「子女」の言い換えは、「子供」「子」「お子さん」「お子様」などいろいろあります。
言い換えるとすると、
良家の子女→良家のお子様
子女の教育→子の教育
子女の成長を嬉しく思う→子供の成長を嬉しく思う
などになりますね。
「子女」を英語で何と言う?
「子女」は英語で「children」です。
「children」は「子供」と訳すことが一般的ですが、英語では「子女」と「子供」は区別がありません。

「子女」がどういうものかわかりましたね。
字をみただけで「子女」を差別的表現と考える人もいるようですが、「子女」は男の子も女の子も含まれているので、現在も問題なく使われている言葉です。
ただ、古い言い回しなので日常会話で使うことが少ないので、意味を勘違いする人がいても仕方ないかなと思いますよね。
関連:「子ども」「子供」という表記はどちらが正しい?子供という漢字の由来と使ってはだめな理由
関連:【言葉の違い辞典】似ている日本語の意味の違いをまとめて解説!

コメント