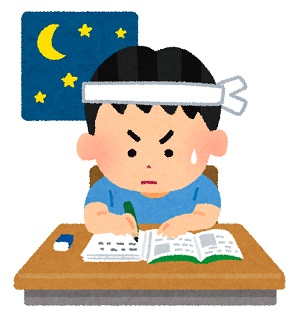
日常的に「鉢巻(はちまき)」をすることはありませんが、運動会や体育祭でのチーム分けや、受験勉強をする時に鉢巻をするイメージがありますよね。
鉢巻(はちまき)にはどのような意味があるのでしょうか?
また鉢巻にはどのような効果があるのでしょうか?
語源や由来、いろいろな巻き方を紹介します。
鉢巻をする意味や効果とは?
「鉢巻」は額の位置で頭を布や紐(ひも)で結ぶことです。
または、その布や紐そのもののことを指します。
鉢巻をする意味は精神統一や気合いを入れるためです。
また、 運動会などのチーム分けで用いられることもあります。

土木作業員や料理人も鉢巻をすることがありますが、 額から流れ落ちる汗を鉢巻で受け止め、顔に垂れてこないようにする目的があり、バンダナやヘアバンド、タオルなどを鉢巻のように頭に巻くこともあります。
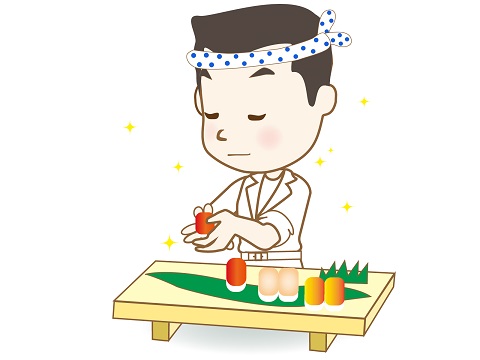
鉢巻をすることで精神統一したり、気合を入れるという、その効果は、科学的に証明されているわけではありませんが、 勉強を始めるときに鉢巻をすることによって脳が「勉強するぞ!」というモードに切り替わり、集中力がアップし、鉢巻をしない時よりも効率的に勉強ができるそうです。
また、 運動会などでチームごとに色分けした鉢巻をすると、チームの士気が高まり、絆が深まる効果があると言われています。
鉢巻の起源や由来とは?
鉢巻の起源は神話の時代に遡るといわれています。

天宇受売
天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸(あまのいわと)に隠れてしまい、世界が暗闇に包まれた時、天照大御神にお出ましいただくため、天宇受売(あめのうずめ)が額に蔦(つた)を巻いた衣装で舞ったことだといわれています。
鎌倉時代(1185年~1333年)中期ごろには、武士は烏帽子(えぼし・成人男性の帽子)の上から鉢巻を締め、その上に兜をかぶり、精神統一の目的のほか、烏帽子が落ちないようにしていたようです。

鉢巻の語源

鉢巻の「鉢」は、僧侶が托鉢(たくはつ・お経を唱えながら鉢を持ち食べ物などを乞うこと)に用いる円形の深い容器のことを指します。
その容器の形が頭蓋骨の形に似ていることから、頭蓋骨のことを「鉢」と言うよになりました。
「鉢=頭蓋骨(頭)」から「鉢巻=頭に巻く」となったようです。
頭蓋骨のことを「鉢」と言うようになったのは室町時代(1336年~1573年)で、1477年の「史記抄(しきしょう・中国の史記を口語でまとめたもの)」に「頭のはちを漆で塗りて酒杯にしたぞ」という記述があるそうです。
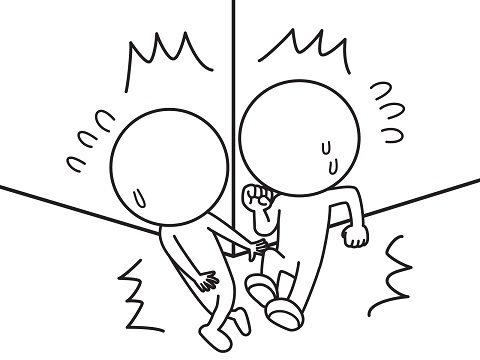
また、二人の人が出会い頭に頭をぶつけることを「鉢合わせ」と言いますが、これも「鉢=頭蓋骨(頭)」が由来で、江戸時代から使われているそうです。
鉢巻の巻き方
鉢巻の結び方をいくつかご紹介します。
後ろ鉢巻

細長い布・細長く折った手ぬぐいなどを、額の位置で頭に巻き、結び目が後頭部に来るようにします。
最も一般的な巻き方です。
向こう鉢巻(向こうしばり)
細長い布・細長く折った手ぬぐいなどを、額の位置で頭に巻き、結び目が額に来るように結びます。
ねじり鉢巻
細長い布では綺麗にねじることができないので、細長く折った手ぬぐいをねじり、堅くロープ状にして額の位置で頭に巻きます。
後頭部で手ぬぐいの両端を交差させ、両端を上にひっぱり、頭に巻いた部分に両端を入れ込みます。
交差させた部分が後頭部の真ん中にくるよう調整し、手ぬぐいの両端を上向きに整えます。
喧嘩結び
細長い布では綺麗に結ぶことが難しいので、細長く折った手ぬぐいなどを、額の位置で頭に巻き、額の真ん中で結びます。
ここで一旦、頭からはずし、自分の膝に鉢巻を置くと結びやすいです。
両端の片方が角のようにピンと張るよう形を整え、額の真ん中に結び目が来るように鉢巻を頭に乗せます。
くわがた結び(くわがたかぶり)
女性がお祭などで粋に鉢巻をする代表的な結び方で、髪型はお団子にしておきます。
細長い布では綺麗に結ぶことが難しいので、細長く折った手ぬぐいなどを、お団子の上で交差させ、一旦頭からはずします。
交差させた両端をそれぞれ内側に折り返し、形を整え、額より少し上に乗るように置き、ヘアピンで固定します。
元気結び
細長い布では綺麗に結ぶことが難しいので、細長く折った手ぬぐいなどを、額の位置で両端が前に来るよう頭に巻き、両端が同じ長さになるよう持ちます。
頭の大きさのところを指でしっかり押さえ、一旦、頭からはずします。
頭の大きさのところが根元になるように、両端を一緒に上向きに折り、鉢巻の裏側を通るように下向きに折ります。
このとき、輪ができているので、両端を輪に通し、おにぎりの形になるように形を整えきつく結びます。
額の真ん中におにぎりの形が来るように頭にかぶります。
いかがでしたでしょうか?
受験生が鉢巻をするイメージが強かったですが、気合いを入れるためだけではなく、勉強するために脳を切り替える効果もあるんですね。
運動会などで鉢巻をするときは、額に巻いて後頭部で結ぶだけでしたが、お祭の参加者をよくみてみると、いろいろな結び方があることに気づきます。
お祭に参加する際には粋な結び方に挑戦してみたいですね!
関連:「貧乏ゆすり」はなぜ貧乏?由来とは?貧乏ゆすりの原因と健康効果
関連:【日本の神様10選!】日本の有名な神様 人気ランキング!

コメント