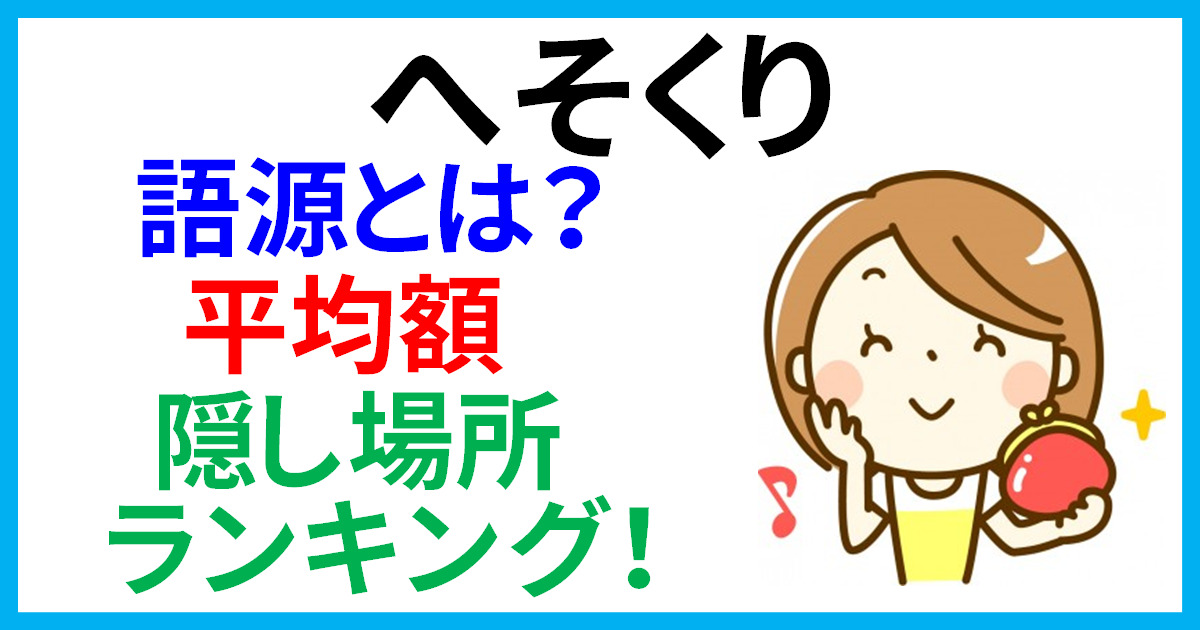
みなさんは、へそくりしていますか?
へそくりというと、家計をやりくりして家族には内緒でこっそり貯めているお金のことですが、その語源はどこから来ているのでしょうか?
平均額や隠し場所などは一体どうなっているのでしょうか?
隠し場所をランキング形式でご紹介します。
へそくりの語源とは?
へそくりの語源は以下のとおり諸説あります。
「綜麻繰り」が語源
江戸時代(1603年~1868年)にはへそくりという言葉が使われていたといわれています。
語源については諸説あり、有力なのは「綜麻繰り」が語源というものです。
「綜麻繰り」は「へそくり」と読みます。

綜麻(へそ)は紡いだ麻糸を巻き付けた糸巻きのことで、麻糸を巻いていく作業のこと「綜麻を繰る(へそをくる)」をいいます。
家計を助けるために女性が綜麻繰りの内職をして得たお金を「へそくり金」といい、これが転じて、いつの間にか内緒でお金を貯めることを「へそくり」と呼ぶようになったといわれています。
「臍繰り」が語源
また、「臍繰り」が語源という説もあります。
こちらも「へそくり」と読みます。
臍(へそ)は、おへそのことです。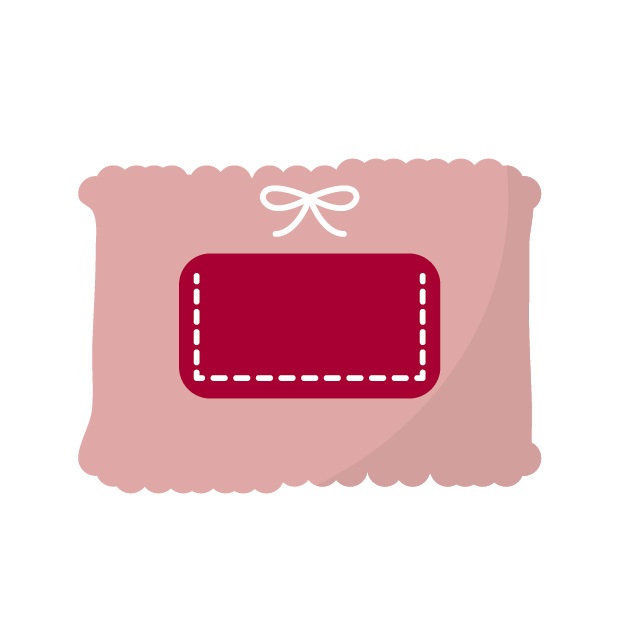
昔お金や貴重品を腹巻などで巻きつけていたことから「臍の奥(腹巻など)から繰り出すお金」を意味し、ほかの人に知られないように内緒で貯めておくこと、隠し蓄えていたお金のことを「臍繰り(へそくり)」と呼ぶようになったという説があります。
へそくりの平均額は?

へそくりの平均額に関しては、調査方法や調査会社などで多少異なりますが、夫は100万円ほど、妻は400万円ほどあるそうです。
へそくりをしている主婦は4割程度といわれており、なかには1000万円を超えるへそくりをしている主婦もいるそうです。
へそくりの隠し場所ランキング

1位 箪笥(たんす)やクローゼットなどで衣類にまぎれさせる
昔から「タンス預金」という言葉もありますよね。
家族がタンスやクローゼットを開けても見つからないように、衣類にまぎれさせるといいようですよ。
2位 キッチン
料理をするのが妻だけの場合、キッチンのあらゆる場所が隠し場所になりますね。
床下収納や食器棚はもちろん、冷蔵庫の奥に隠したり、ビニール袋で何重にも包んでぬか床に隠す!という人もいます。
3位 机の引き出し、会社のデスク
家の中だと家族に見つかる!特に、妻に発見される!という心配がある夫たちは、鍵付きの引き出しや会社のデスクに隠しているようです。
4位 本棚(本)
家族は絶対見ないような本に挟んだり、本の形をしたへそくりケースを使う人も。
5位 寝室
マットの下や、ベッドの下、枕に隠すという人もいます。
その他
ほかにも、
・靴箱
・車の中
・神棚
・仏壇
・天井裏
・子どものおもちゃ箱
などなど、いろいろな隠し場所があるようです。

へそくりの隠し場所1位の箪笥は、今も昔も定番中の定番ですね。
自分の衣類に挟んでおけば、家族に見つかる心配もありませんし、隠し場所を忘れてしまうこともないのでしょう。
一ヶ所に隠すと発見されたときのリスクが大きいから・・・と、小分けにしてさまざまな場所に隠す人もいるそうですよ。
関連:お年玉はいつから始まったの?起源と由来、お年玉をあげる意味とは?
関連:どろぼうはなぜ唐草模様の風呂敷を使うの?意味や由来とは?

コメント