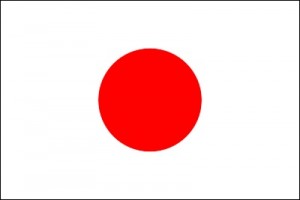
「君が代」を入学式や卒業式で歌ったり、ワールドカップやオリンピックなどで聞いたという方は多いのではないでしょうか?
ですが歌詞の意味を知らないまま歌っていたという人はいらっしゃいませんか?
今回は、君が代の歌詞の本当の意味や、いつから歌われているのかについて解説します。
実は恋の歌だったという話もあるようですよ。
歌詞の意味とは?
君が代は、平安時代(794年~1192年ごろ)の歌集「古今和歌集」(905年)の詠み人知らずの賀歌(がか)が由来です。
賀歌とは、長寿や繁栄を祈る歌のことです。

さざれ石
「君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌(いわお)となりて 苔(こけ)のむすまで」
現代語に訳すと
「あなたの命が、千年も八千年も永遠ともいえる時間、小さな石が大きな岩になって、その岩に苔が生えるまで、長く長く続きますように」
となります。
ここでの「君(あなた)」は特定の人物を指しているわけではなく、身近な人を指すと考えられています。
君が代は身近な人の長寿を祈る歌として歌われてきたのです。

イザナキとイザナミ
また、男女の永遠の絆を歌った恋の歌という解釈もあります。
古代日本語では、
「き」は男性
「み」は女性
を表したそうです。
日本神話に登場する最初の男女神は「イザナキ(イザナギ)」と「イザナミ」です。
「イザナキ」の「キ」は男性
「イザナミ」の「ミ」は女性
を指すそうです。
そして、神は完全な存在であることから、君が代の「君(キミ)」は心身ともに完全に成長した男女を指すと考えるようです。
また、
「さざれ石の 巌(いわお)となりて」
は、小さな小石が結束して大きな岩石となることから、協力しあい、団結しあうことを表しています。
まとめると
「君」は「心身ともに成長した男女が」
「代」は「時代を超えて」
「千代に八千代に」は「永遠に千年も八千年も、生まれ変わってもなお」
「さざれ石の巌となりて」は「協力し合い、団結をして」
「苔のむすまで」は「固い絆と信頼で結びついていこう」
と解釈するようです。
「君が代」には続きがある?
国歌としての「君が代」には続きはありません。
しかし、明治時代には小学校の教科書に続きが載っていたそうです。
明治14年(1881年)に、文部省によって「小学唱歌集 初篇」が編集され、このとき掲載された「君が代」は2番までありました。
| 番 | 歌 |
| 1番 | 君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて こけのむすまで うごきなく 常磐(ときは)かきはに かぎりもあらじ |
| 2番 | 君が代は 千尋(ちひろ)の底の さざれいしの 鵜のゐる磯と(うのいるいそと) あらはるるまで かぎりなき みよの栄を ほぎたてまつる |
このように、現在の歌詞とは若干異なるのですが、その理由は定かではありません。
また、明治23年(1890年)の「生徒用唱歌」という教科書に掲載された「君が代」は、1番は現在と同じで、3番まであったようです。
| 番 | 作者 | 歌 |
| 1番 | 詠み人知らず | 君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで |
| 2番 | 源頼政 | 君が代は 千尋(ちひろ)の底の さざれ石の 鵜(う)のゐる磯と あらはるるまで |
| 3番 | 藤原俊成 | 君が代は 千代ともささじ 天の戸や いづる月日の 限りなければ |
2番は平安時代末期の武将の源頼政(みなもとのよりまさ・1104年~1180年、)が詠んだものです。
3番は藤原俊成(ふじわらのとしなり・1114年~1204年、平安~鎌倉時代の公家、歌人)の歌で、六条天皇(ろくじょうてんのう・第79代天皇)の大嘗祭のときに贈られた歌です。
また、上記の「生徒用唱歌」の3番の歌が異なっていたという説もあります。
| 番 | 作者 | 歌 |
| 3番 | 詠み人知らず | 君が代は 限りもあらじ 長浜の 真砂の数は よみつくすとも |
詠み人はわかりませんが、光孝天皇(こうこうてんのう・第58代天皇)の大嘗祭(だいじょうさい)ときに贈られた歌といわれています。
またさらに、明治時代の別の教科書には4番まであったという説があります。
1番、2番、3番は「生徒用唱歌」と同じで、4番が加わります。
| 番 | 作者 | 歌 |
| 4番 | 大江匡房 | 君が代は 久しかるべし わたらひや いすずの川の 流たえせで |
この歌は、大江匡房(おおえのまさふさ・1041年~1111年、平安時代の公卿、歌人)が詠んだものです。
「君が代」はいつから歌われているの?
平安時代の古今和歌集に詠まれた君が代は、鎌倉時代(1185年~1333年)以降、庶民に広まり、長寿を祈る歌、お祝いの歌、さらには恋の歌として、さまざまなお祝いの場面で歌われるようになりました。
江戸時代(1603年~1868年)には三味線で曲をつけたものが酒場で流行ったこともあるようです。
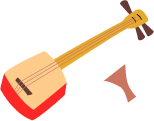
国歌として歌われるようになったのは明治13年(1880年)で、雅楽奏者の林廣守(はやし ひろもり)が曲に起こし、ドイツ人音楽家フランツ・エッケルトが西洋風和声をつけることで国歌として用いられるようになりました。
明治36年(1903年)には、ドイツで開催された「世界国歌コンクール」で、君が代は一等賞を受賞しているそうですよ。
第二次世界大戦前までは、国家平安の歌として親しまれていましたが、戦中に天皇を称える歌として君が代が使われたこと、軍国主義の象徴となったことなどから、戦後、GHQ(連合国軍総司令部)が日の丸掲揚と君が代の斉唱を禁止し、その後も厳しく制限をしましたが、特定の場合に日の丸の掲揚と君が代の斉唱を認めました。
その後、日本には正式な国歌がなかったので慣習として君が代が国歌として使われ、学習指導要領では1978年に「国歌を斉唱することが望ましい」、平成元年(1989年)には「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と改訂され、入学式、卒業式で君が代が歌われるようになりました。
そして、正式に国歌として制定されたのは平成11年(1999年)になってからなのです。

平成になって正式に国歌として制定されたことに驚いた人もいるのではないでしょうか?
ちなみに、君が代は、歌詞の付いた国歌の中で世界最短の国歌なのだそうですよ。
また、古今和歌集(905年)に詠まれた歌を由来とする君が代は、世界で最も古い歌詞の国歌でもあるのです。
千年以上前の平安の時代から歌い継がれてきた「君が代」ですが、もともとは、長寿を祈る歌であり、男女の永遠の絆を歌った恋の歌でもあったのですね。
いろいろな解釈はございますが、君が代が、長い間日本人に愛され、歌われてきたということに変わりはないようです。
関連:日の丸の由来とは?赤と白の意味とは?日本の国旗になったのはいつ?
関連:【日本の神様10選!】日本の有名な神様 人気ランキング!
関連:大嘗祭の意味とは?新嘗祭との違いとは?日程は?祝日になるの?

コメント
コメント一覧 (6件)
勉強に成ります
コメントありがとうございます!
少し前にYouTubeで歌と一緒に同じ解説が載っているのを拝見しました。今、45歳なのですが、
小さい頃から学校での行事ごとに普通に歌って来ました。その頃は別段、誰も気にすることな
く歌っていたのにいつの間にかこんな事態になって驚いています。一番しかないと思っていた
ら5番まであるとか、戦争などまるで無関係な祝い唄として千年も前から受け継がれてきた事な
と新しく知ることが出来て本当に嬉しかったです。これからも歌い続けたいと思います。
コメントありがとうございます。
これからも歌い続けていきたいですね!
たまたまGoogle検索で一番上に出てきたので拝読いたしましたが、とてもわかりやすく楽しい説明で他の記事も読んでしまいました。
ずっとGoogle検索の一番上出てくるように更新していっていただけると、何年先もふと日本のことについて疑問を抱いた方たちが読めるのでそういう未来も素敵だなと思いました。
心温まるコメントありがとうございます。
「とてもわかりやすく楽しい説明」と仰っていただきとても嬉しいです!
今後も皆さまのお役に立てるような記事を投稿していきたいと思います。
ありがとうございました!