
一年の始まりは1月1日、お正月ですが、お正月を境に色々なことが新しく始まるわけではありません。
学校や会社など、私たちの生活に関わる多くの場面で、新しく年が始まるのは4月1日です。
これを「新年度」または「年度初め」といいますがなぜ4月なのでしょうか?
また、「入学式」や「入社式」も4月の場合が多いですがこれはなぜなのでしょうか?
※年度はじめは「年度初め」と「年度始め」の二種類の表記がございますが、どちらが正しいということはなく、いずれを使用してもいいそうです。
本記事ではGoogleでの検索件数の多い「年度初め」に統一しています。
年度とは?
読み方は「ねんど」です。
年度とは、特定の目的のために規定された1年間の区切り方です。
多くの場合用いられているのは、官公庁などが予算を執行するための期間である「会計年度」、学校など学年の切り替わりを目的とした「学校年度」です。
会計年度と学校年度はどちらも4月から3月までを区切りとしています。
一般的に「年度」といえば、4月から3月までの区切りを指しますが、ほかにもさまざまな「年度」があります。
たとえば、
6月から5月まで・・・「生糸年度」
7月から6月まで・・・「麦年度」「酒造年度」「羊毛年度」
8月から7月まで・・・「綿花年度」
9月から8月まで・・・「いも年度」「砂糖年度」「でん粉年度」
10月から9月まで・・・「大豆年度」「農薬年度」
11月から10月まで・・・「米穀年度」
などがあります。
これらは収穫時期などが基準となって区切られています。
たとえば、
生糸年度は、生糸のもととなる蚕(かいこ)が繭(まゆ)になり糸を採取できる時期が6月です。
麦年度は、6月~8月に収穫時期を迎えるので7月が基準になっています。
酒造年度は、日本酒の原料となる米の収穫が始まるのが7月からです。
会計年度とは?
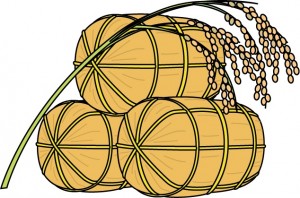
会計年度は明治19年(1886年)に始まりました。
当時、日本の主産業は稲作でした。
政府の主な税金収入源が農家のお米だったのです。
納税はお米ではなく現金だったので、農家が秋にお米を収穫し、それを現金に換えて納税し予算を編成すると、1月では間に合わず、4月からとするのが都合が良かったため会計年度を4月にしたといわれています。

また、当時世界一の経済力を誇ったイギリスの会計年度が4月からでした。
当時の日本にとってイギリスは重要な国であったこともあり、イギリスに倣(なら)って会計年度を4月からにしたともいわれています。
学校年度とは?

江戸時代(1603年~1868年)の寺子屋や、明治時代(1868年~1912年)初期の学校では、入学時期や進学時期は決まっていなかったそうです。
いつでも入学できますし、個人の能力によって勉強の進み方も違ったので一斉に学年が進級することもありませんでした。
しかし、大学ができると外国に倣って「一斉入学・一斉進級」にしたほうがいいということで、9月から8月という区切りを作りました。
ところが、明治19年(1886年)に会計年度が始まったことで、それに合わせるために学校年度は4月から3月という区切りに変わっていきました。
会計年度に合わせることで、政府から学校の運営資金を調達するのに都合が良かったといわれています。
明治の終わりごろになると国が積極的に会計年度と学校年度の統一を指導するようになり、国や県から学校運営のための補助金をもらっている学校は会計年度に合わせて4月入学に変えていきました。
また、9月入学・進学の場合、入学試験の時期が6月ごろになります。
6月ごろの日本は梅雨時で蒸し暑い時期のため学生の健康を考慮し、4月入学にしたともいわれています。

ほかにも、明治時代の日本は「徴兵令(ちょうへいれい)」によって、国民に兵役の義務を課していました。
徴兵令では20歳以上の男性が対象となっており、対象者は徴兵検査を受けるために役所や軍に届出が必要でした。
その届出の期日はもともと9月1日だったのですが、明治19年(1886年)に会計年度が始まったことによって4月1日に変更されました。
それに伴い、軍隊に関する士官学校などの新学期も4月1日からとなったのです。
徴兵の届出期日や士官学校などの新学期が前倒しになったことから「優秀な人材が徴兵されてしまう」と考えた一般の学校関係者は、9月入学から4月入学へ早めたともいわれています。
新年度・年度初め・入学式・入社式はなぜ4月なの?
ここまで書いてきたように、 明治時代に会計年度が始まったことで日本では4月が新年度、年度初めとなり、学校年度もそれに合わせる形で4月になったのです。
昭和(1926年~1989年)に入るとほぼすべての学校で4月始まりの年度に統一され、入学式は4月になったのです。
また、戦後、一般企業の多くも国の会計年度に合わせるようになったことで、民間企業もほぼすべてが4月からが新年度となり、新卒の一括採用が一般化し、入社式は4月になったのです。

いかがでしたでしょうか?
日本人にとって、学校の新年度は4月というのが当たり前ですが、多くの先進国では9月が新年度になっています。
日本でも、学校年度は9月からにしたほうがいいのではないか?という話もあるようですが、どうなっていくのでしょうね?
卒業式や入学式は桜の季節というイメージが大きい人も多いと思います。
真夏の8月に卒業して、9月に入学するようになるのは・・・ちょっと想像しづらいかもしれませんね。
関連:日本の入学式はなぜ9月ではない?導入のメリット・デメリット
関連:【2026年】入学式は何時から何時まで?時間と流れ、やることは?
関連:【2026年】入社式はいつ?入社式では何をするの?その目的や内容とは?
関連:「早生まれ」と「遅生まれ」の意味と違いとは?メリットとデメリット

コメント
コメント一覧 (1件)
3月31日が実質の大みそかになった理由は、そんな所にあったのですね。
明日で施行されて132年も経つのですか。
こういう重要な事は、学校教育で教えた方が良いとも思います。