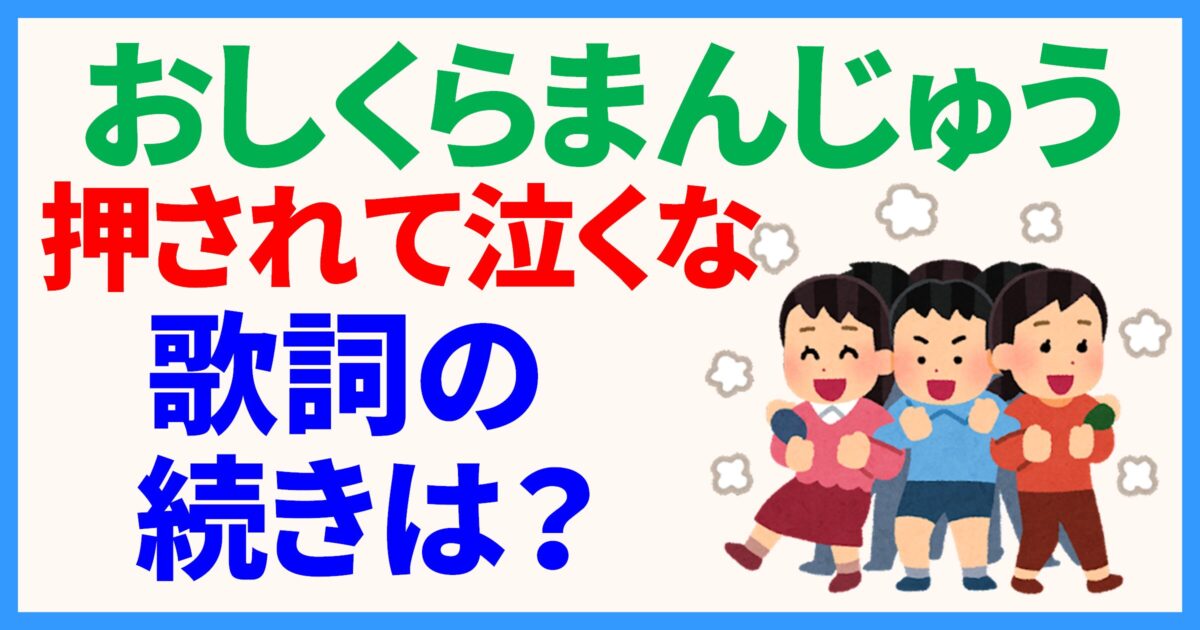
「♪おしくらまんじゅう~おされてなくな~」というわらべうたを歌いながら遊んでいるうち体中ぽっかぽかになりましたよね。
子どもの頃は意味もわからずに歌っていましたが、おしくらまんじゅうとはどのような意味があるのでしょうか?
また、あの歌には続きがあるのでしょうか?由来や遊び方をご紹介します。
おしくらまんじゅうの意味や由来とは?
「おしくらまんじゅう」は、基本的に大勢の人が寄り集まって、お互いに押し合い、体を温めることが目的の遊びです。
また、お互いに押し合ったときに、その場から押し出されたり、倒れたりした人を負けとする勝敗を決める遊び方もあります。
漢字で「押し競饅頭」と書き、押し比べる、押し合う、押し競うなどの意味があます。
由来については、はっきりしたことはわかっていません。
語源は「押し比べる(おしくらべる)」→「押し比べ」→「おしくら」に変化したという説があります。
「まんじゅう」は、大勢の人が一カ所に集まった状態を表していると考えられています。
おしくらまんじゅうの遊び方は?
基本的な遊び方
お互い押し合うだけの遊び方
① 参加者は背中合わせで円陣を組み、隣の人同士で腕を絡めます。
② 「おしくらまんじゅう おされてなくな」と歌いながら、自分の体を円陣の中に押し込んだり、外へ引っ張ったり、肩だけで押したりお尻で押したりするうちに体が温まります。
参加者がそれぞれ不規則な動きをすることで、自分が思ってもいない方向に体が動いていくのもおしくらまんじゅうの楽しさのひとつです。
腕を絡めるのは、手を使って他の人を押し出したり、ひっぱったりしないためです。
しかし、転んだ時に危険だからという理由から、腕を絡めない場合や、腕を胸の前に組む場合もあります。
4人以下だと動きが小さく、体を温める効果が少ないため、4人以上で遊ぶといいようですよ。
勝敗を決める遊び方
お互いを押し合うだけの遊び方と同じですが、押し合ううちに倒れたり、押し出された人が負けです。
アレンジした遊び方
円を描く遊び方
円の中で押し合い、円から出たら負けというルールです。
この時、円ではなく楕円形にしたり、三角形にしたりと、「出たら負け」の範囲をいろいろな形にすることで、遊び方をアレンジすることもできます。

鬼ごっこをプラスした遊び方
参加者全員が押し合いながら動き回れる程度の円を描きます。
鬼はその円の中に入ることはできず、円の外で待機します。
円の中の人たちでおしくらまんじゅうをし、円の外に押し出された人に鬼がタッチをしたら、タッチをされた人と鬼が入れ替わり、おしくらまんじゅうを続けます。
円を大きくすればするほど、鬼は円のどこから中の人が押し出されるか予測して動き回ることになります。
鬼にタッチされたらその人も鬼になり、最後まで円の中に残った人の勝ちというルールにアレンジすることもできます。
時間を決める遊び方
数人ずつの複数のグループを作ります。
それぞれのグループがそれぞれの円の中でおしくらまんじゅうをします。
1分間とか3分間とか時間を決めておしくらまんじゅうをし、円から出てしまった人はそのまま外で待ちます。
時間が来たら円の中に何人残っているで勝敗を決めます。
この時の勝敗の決め方ですが、
・残っている人数が少ないグループが勝ち
・残っている人数が多いグループが勝ち
・3人残っているグループが勝ち
・1人だけ残っているグループが勝ち
などと書いた紙を見えないよう折った状態で箱に入れ、時間が来たら箱から紙を一枚取り出します。
この時初めて参加者は勝敗を知ることになります。
歌詞の続きがあるの?

「おしくらまんじゅう おされてなくな」という歌詞がとても有名で、その部分しか知らない、覚えていないよ!という人も多いかもしれませんが、実は、続きがあるのです。
おしくらまんじゅう おされてなくな
あんまりおすと あんこがでるぞ
あんこがでたら つまんでなめろ
作詞作曲が誰なのか、いつの時代から歌われているのかなどは不明です。
いつの季語?
おしくらまんじゅうは冬の季語です。
有名な俳句には次のものがあります。
●大野林火
『おしくらまんじゅう 路地を塞ぎて 貧などなし』
「子どもたちが路地を塞いでおしくらまんじゅうをしている。寒さも貧しさも吹き飛ばしている。」という意味です。

歌詞には続きがあることがわかりましたね。
ですが、多くの場合「おしくらまんじゅう おされてなくな」の部分を繰り返しているようです。
歌いながらみんなで押し合うというとてもシンプルな遊びですが、体がぽかぽか温まるので寒い季節にはお友達を誘って大勢で遊ぶと楽しいですよ。
遊び方をアレンジして、自分たちなりのおしくらまんじゅうをするのもいいですね!
関連:「指きりげんまん 嘘ついたら針千本飲ます」の歌の意味と由来とは?
関連:「あんたがたどこさ」の歌詞全文とその意味とは?実は怖い歌だった?

コメント