
皆さんは「質屋」を利用したことがありますか?
「質屋」というと「自分のものを預けてお金を貸してくれるところ」という漠然としたイメージしかないかもしれません。
今回は質屋の仕組みや、買取と質入れどっちがいいのかなど、質屋についてわかりやすく解説します。
質屋の意味とは?
読み方は「しちや」です。
質屋の「質」は、「約束を守る証として相手に預けておくもの」という意味があります。
簡単に説明すると、物品を預ける代わりにお金を貸してもらうのが質屋です。
仕組みなどについては後ほど詳しく説明します。
質屋の由来とは?

質屋の歴史は古く、遣唐使(けんとうし・7世紀~9世紀)の時代のころにはすでにあったと考えられていますが、生業として質屋の店舗が構えられたのは鎌倉時代(1185年~1333年)といわれています。
このころは質屋という名前ではなく、担保(預かる物品)を保管するため土蔵を建てたことから「土倉(どそう・とくら・つちくら)」と呼ばれていました。
土倉の主な取引相手は武士で、刀や領地を担保としてお金を貸していました。
室町時代(1336年~1573年)になると貨幣経済が発達したため、一般庶民の間にも広まりました。
江戸時代(1603年~1868年)には「質屋」と呼ばれるようになり、庶民の間で盛んに利用されるようになりました。
生活に困った時は着物や帯などを担保にお金を借りていたそうです。
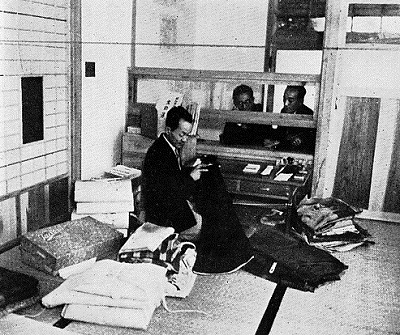
明治28年(1895年)には「質屋取締法」という質屋に関する法律が制定されました。
そして、昭和25年(1950年)に「質屋営業法」が制定され、各都道府県の公安委員会への届け出や、利子や期限などについて法的整備が加えられ、現在に至ります。

質屋では、物品を担保にしてお金を借りますが、現在は無担保でお金を貸してくれる消費者金融が発達したため、質屋の経営状態が悪化し、廃業したところも多いそうです。
質屋の仕組みを簡単に解説
質屋の仕組みを簡単に説明すると以下のようになります。
① 担保を預け、お金を借りる
② 期限までに金利と元金を返せば、担保は戻ってくる
③ 期限までに返済できない場合、担保は戻ってこない
担保とは、契約や取引を実行できず不利益が生じた場合に備えるもので、質屋の場合は、腕時計、ブランドバッグ、ブランド財布、アクセサリー、宝石などの物品が担保となることが多いです。
担保となる物品を持って質屋へ行くと、査定してくれます。

その金額に納得できれば取引が成立し、その場で現金をもらいます。
査定は無料です。
査定に納得できない場合は交渉したり、別のお店へ行くなどします。
物品(担保)を預けてお金を借りることを「質入れ(しちいれ)」といいます。
質入れした担保は、期限までに金利と元金を返せば戻ってきます。
期限までに返済できない場合、担保は戻って来ません。
このことを「質流れ(しちながれ)」といい、所有権はお店側に移ります。
担保で、借りたお金を弁償する・・・ということですね。
質流れしたものは基本的に取り戻すことができず、お店側でメンテナンスやクリーニングをした後に販売に出したりします。
買取と質入れどっちがいい?
質屋には「買取(かいとり)」と「質入れ」があります。
「買取」とは、お店に物品を買い取ってもらうことです。
但し、取引が成立すると物品の所有権はお店に移るので後で取り戻すことは難くなります。
「質入れ」は、先ほど説明した通り、担保を預けてお金を借りることで、期限までに元金と金利を返済すれば担保は戻ってきます。
一般的に「質入れ」は「買取」よりも2~3割ほど受け取る金額が少なくなります。
質入れの場合、返済すれば手元に戻ってくるので、その間の保管料と考えるといいかもしれません。

しかし、返済金利は他の金融業(カードローンやキャッシング)よりも高く設定されています。
年利(一年間の金利)は一般的な金融機関で高くても9~18%、消費者金融の上限金利で29.2%です。
質屋は年利109.5%、月利(ひと月の金利)が約9%が上限で高く設定されています。
実際に上限で設定している質屋は少ないですが、一般的には月利3~8%、年利36~96%で設定しているようです。
質屋の金利が高く設定されているのは、以下の理由があるそうです。
「少額融資である」
「担保の状態を損なわないよう保管しなければならない」
「担保の鑑定が必要」
「盗品の場合警察と協力しなければならない」
「一般的に最大3か月で設定されているので1年間も借り入れを続けことは少ない」など
買取と質入れどっちがいいのか?ということについては、利用する人の状況や考え方によってそれぞれです。
買取がいい人
●物品に特別な思い入れがないので戻ってこなくても構わない
●少しでも多く現金が欲しい
●引っ越しなどで荷物を減らしたい
●使わないものを整理したい
質入れがいい人
●物品を必ず取り戻したい
●一時的に現金が必要になった
預かり期限はいつまで?

質入れした際の預かり期限は3ヶ月間のところが多いです。
また、期限がきたからといってお店から連絡がくることはありません。
これは質屋からお客へ連絡をすることは質屋営業法で禁止されている「催促、取り立て」とみなされる可能性があるからです。
何らかの事情で期限を過ぎるようであれば、自分から事前に連絡をしておけば対応してくれるようですよ。
逆に言うと自分から連絡しないかぎり質屋から連絡がくることはないということになります。

質屋がどういうものかわかりましたか?
毎年7月8日は「質屋の日」という記念日なのだそうです。
「7・8(しちや)」の語呂合わせで、全国質屋組合連合会が「低利で安心して利用できる融資事業者としての質屋をPRする」ことを目的に制定したそうですよ。
最近ではネットで査定もしてくれるそうなので、利用してみてはいかがでしょうか。

コメント