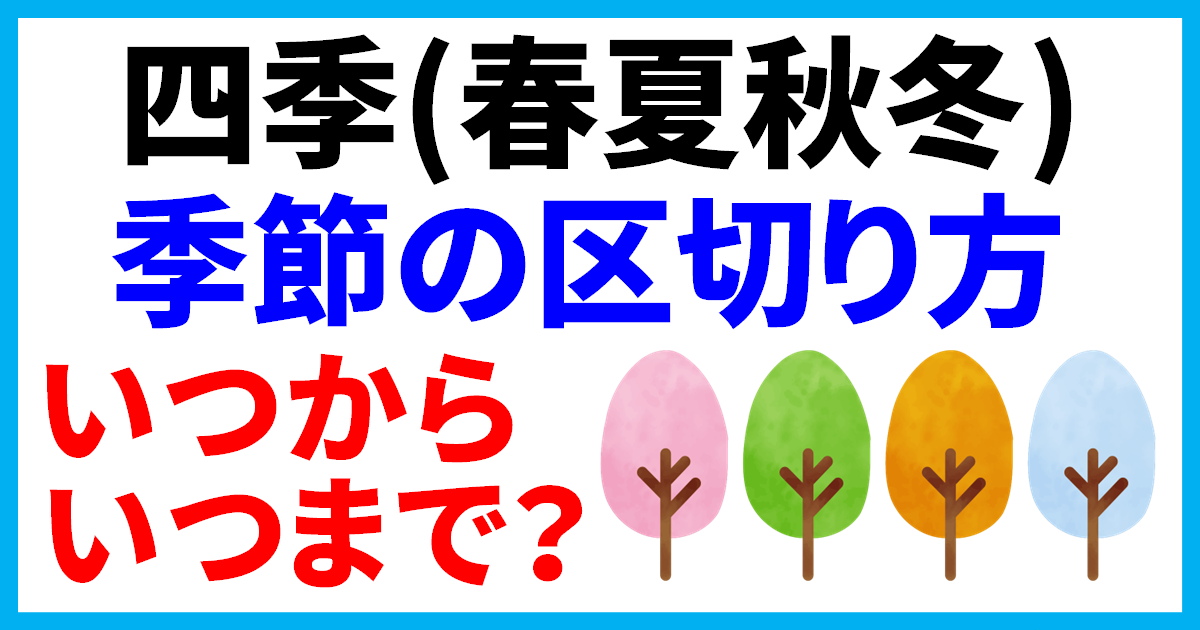
日本には春夏秋冬、四季がありますね。
では、四季の期間は具体的にいつからいつまでなのでしょう?
明確な区切りはあるのでしょうか?
今回はそんな疑問についてわかりやすく解説します。
四季の期間はいつからいつまで?季節の区切り方とは?

四季の期間や季節の区切りには絶対的な定義は存在しないそうです。
四季の期間、季節の区切り方は以下のとおり、いくつかの方法があります。
● 気象学的な区別(気象庁が用いており、一般的にも使われます)
● 年度による区別(学校行事やテレビの編成などに使われます)
では、一つずつみていきましょう。

気象学的な区別
一般的には季節の区切り方とされているのが気象庁が用いている(気象学的な区別)です。
気象庁では「時に関する用語」として四季を以下のように区別しています。
「春」・・・ 3月、4月、5月
「夏」・・・ 6月、7月、8月
「秋」・・・ 9月、10月、11月
「冬」・・・ 12月、1月、2月

天文学的な区別
天文学では二至二分(にしにぶん)を基準にして季節を区別しています。
二至とは、夏至(げし)と冬至(とうじ)のことです。
二分とは、春分(しゅんぶん)と秋分(しゅうぶん)のことです。
二至二分は、太陽の動きによって決まり、毎年同じ日になるわけではないため、「~ごろ」という表記にしています。
夏至、冬至、春分、秋分で四等分し、季節を区別しているため、以下のようになります。
「春」・・・ 3月21日ごろ(春分)~6月20日ごろまで
「夏」・・・ 6月21日ごろ(夏至)~9月22日ごろまで
「秋」・・・ 9月23日ごろ(秋分)~12月21日ごろまで
「冬」・・・ 12月22日ごろ(冬至)~3月20日ごろまで
暦による区別
一年間を24等分した二十四節気(にじゅうしせっき)が基準となっています。
二十四節気には、
立春(りっしゅん)
立夏(りっか)
立秋(りっしゅう)
立冬(りっとう)
という、季節の始まりの日があり、これが春夏秋冬の基準となっています。
二十四節気は太陽の動きを基準に決められるため、毎年同じ日になるわけではありませんので、「~ごろ」という表記にしています。
暦による区別は以下のようになります。
「春」・・・ 2月4日ごろ(立春)~5月5日ごろまで
「夏」・・・ 5月6日ごろ(立夏)~8月7日ごろまで
「秋」・・・ 8月8日ごろ(立秋)~11月7日ごろまで
「冬」・・・ 11月8日ごろ(立冬)~2月3日ごろまで

年度による区別
一般的に新年度(年度初め)が4月から始まるため、それに合わせて季節を区別しています。
テレビやラジオの新番組が始まる月を思い浮かべてもらうとわかりやすいですね。
「春」・・・ 4月、5月、6月
「夏」・・・ 7月、8月、9月
「秋」・・・ 10月、11月、12月
「冬」・・・ 1月、2月、3月
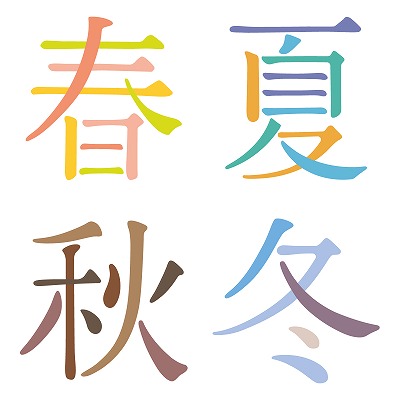
季節の区切り方にはいろいろな方法があることがわかりましたね。
季節はある日を境に「春」から「夏」へと切り替わるわけではありません。
少しずつ少しずつ、季節は移り変わっていきますね。
だからこそ、季節の区別に明確な定義が存在しないのかもしれませんね。
四季がある美しい日本。
それぞれの季節の区切りを知ったうえで、肌で感じる四季を楽しめるといいですね。

コメント
コメント一覧 (3件)
サザエさんのオープニングとサザエさんのエンディングの場合
春は4月5月6月、夏は7月8月9月、秋は10月11月12月、冬は1月2月3月ですからな。
テレビアニメのほとんどは6月から9月は半袖ですな。
もしも涼しい9月が訪れてるんだったら長袖でも過ごしやすいのにね。