
12月に入り年末がせまってくるとなんとなく気持ちがそわそわしませんか?
この時期を表現する言葉に「年の瀬」があります。
では、この年の瀬とはいつからいつまでのことを言うのでしょうか?
年の瀬の意味と使い方をわかりやすく解説します。
年の瀬とは?いつからいつまで?
年の瀬の読み方は「としのせ」です。
その年の終わりが近づき、慌ただしい時期を指す言葉です。
「年の瀬」という言葉を使う期間いつからいつまでと明確には決まっていませんが、12月に入った頃から徐々に使い始め、特に中旬以降になって使うことが多いです。

年の瀬の意味は?
年の瀬とは、「年の暮れ」「年末」「歳末」という意味です。
年の瀬の「瀬」は、川の瀬のことです。
川の瀬とは、川の浅いところ、流れが速く急なところ、急流で船で渡ることが難しいところをいいます。

江戸時代(1603年~1868年)の生活ではツケがほとんどだったようです。
ツケとは、なにか商品を購入したり、飲食をしたとき、その場で支払いうことはせずお店の帳簿に記録をしておいてもらい、お金が入った時にまとめて支払うことをいいます。

そして、江戸の庶民は、
「ツケは年内に支払ってしまい、まっさらな状態で新年を迎えたい」
「年内には未払いのものを清算しないといけない」
という考え方があったので、支払わないと年を越すことができませんが、支払ってしまうと食べ物が買えません。
食べ物が買えないどころか、寒い季節に暖をとることができずに命まで危なくなります。
ツケを支払いたいけれど、支払ってしまうと命の危険にさらされてしまう・・・そういう鬼気迫る状況、ツケの支払いを行う困難さを、川の瀬にたとえて表現したのだそうです。
「年の瀬」の使い方
「年の瀬」は、「年の暮れ」や「年末」という意味ですが、鬼気迫る様子を表現した言葉であることから、慌ただしく押し詰まっているということを念頭においておくといいようですね。
12月に入ったころから
「年の瀬に入り・・・」
「年の瀬の時期に・・・」
などと使い始め、
12月15日ごろからは
「年の瀬も押し迫って・・・」
「年の瀬も押し詰まって・・・」
という風に使うといいですね。
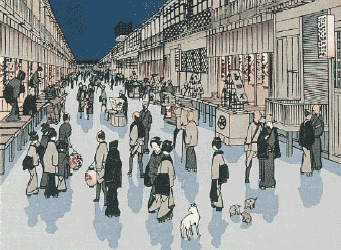
なんとなく使っていた「年の瀬」という言葉ですが、江戸時代の庶民の生活からできた言葉だったのですね。
現在でも、12月はクリスマスやお正月、忘年会などでなにかと出費の多い時期ですね。
江戸時代のように命が危険にさらされるほどのことではないとしても、お金のやりくりに頭を悩ませることは一緒なのかもしれません。
慌ただしく押し詰まるこの時期、体調を崩さないよう元気に新しい年を迎えましょう!
関連:日本のクリスマスの始まりはいつ?起源と歴史。外国との違いとは?
関連:【2025年】忘年会はいつ? 忘年会の意味とは?いつから始まったの?
関連:【2025年】仕事納めは何日?仕事納めの意味、御用納めとの違いとは?
関連:「良いお年を」の続きとは?使う時期はいつからいつまで?

コメント