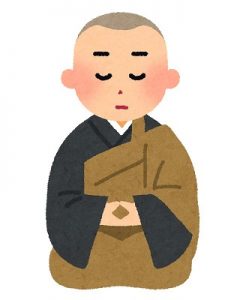
禅や禅問答と聞くとどのようなことを思い浮かべるでしょうか?
普段はあまり接することのない禅や禅問答の世界とはどのようなものなのでしょうか?
今回は禅や禅問答の意味や由来、その歴史についてご紹介します。
禅の意味や由来とは?
禅の読み方は「ぜん」です。
語源はサンスクリット語の「静かに考える」という意味の「dhyana(ディヤーナ)」 に由来します。
dhyanaという発音を漢字で表記した「禅那(ぜんな)」であり、その略が「禅」であるといわれています。
禅とは、インドの釈迦(ゴーダマ・シッダールダ)を開祖とする仏教の二大流派のひとつである大乗仏教(だいじょうぶっきょう)の一派の禅宗(ぜんしゅう)のことです。
大乗仏教とは、自分ひとりの悟りのためではなく、すべての生き物たちを救いたいという考え方です。
因みにもう一方の小乗仏教は、自己一身の救いのみを目ざすものとする大乗仏教側から見た批判的な意味をもつ呼称です。
禅宗は、経典を読んで知識を得ることよりも、自らの体験によって真理に至ることを重んじます。
主な修行は「坐禅(ざぜん)」で、姿勢を正し呼吸を整え、心に浮かぶ雑念を手放すことによって心身を統一し、やがて「悟り=本来の自己」に気づくことを目指します。
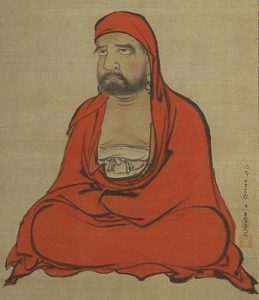
禅宗はインドの僧である達磨(だるま)によって中国に伝わり、中国で独自に発展しました。
そして鎌倉時代に道元が開いた「曹洞宗(そうとうしゅう)」、栄西が伝えた「臨済宗(りんざいしゅう)」、江戸時代の明の隠元禅師が広めた「黄檗宗(おうばくしゅう)」などが主要な宗派として知られています。
これらの禅の教えは、単なる仏教の一派でとしてだけではなく、日本文化全体に大きな影響を与えました。

たとえば、茶道、書道、弓道、剣道など「道(どう)」とつく日本の芸術や武道は、謙虚に自分を抑え、ひとつのことに専念して一事を極め、高い境地に達することを良しとしており、禅の影響を強く受けているといわれています。
禅の本質は、「言葉や論理的な思考を超えたところに存在する真理を、直接体験によって理解すること」にあります。
これは頭でただ知識として理解するのではなく、心を静めた状態で直感的に得られる気づきとも言えます。
こうした「体験に基づく悟り」が他の仏教思想と大きく異なる特徴です。
禅では悟りを「自分の中の仏性(ぶっしょう)」に気づくこととし、すべての人にその可能性があると説きます。
つまり、誰もがもともと「仏(ほとけ)」であり、それに気づくかどうかが修行の核心となっています。
禅問答ってなに?
禅問答は、普段の生活で使う場合は「わけのわからない問答」や「答えのない問答」などを指しますが、もともとは禅僧が悟りに至るために師と行う修行法の一つです。
その際に師が弟子に与える“なぞなぞ”のような問いを「公案(こうあん)」といいます。
公案は常識的な答えのない問いであり、論理では解けないものです。
公案とは以下のようなものです。
馬祖が弟子の百丈と歩いていると、野原から野鴨の一群が飛び去っていった。
それを見た馬祖が、百丈に尋ねた。
「あれは何だ」
「野鴨です」
「どこへ飛んでいったのか」
「わかりません。ただ飛んでいったのみです」
答えを聞いた馬祖は、いきなり百丈の鼻を強くつまみあげた。
「痛い!」
「なんだ、飛び去ったというが、野鴨はここにいるではないか」
百丈は悟りを開いた。-碧巌録-
出典:斉藤啓一のホームページ
その答えは論理的思考では決して解けないような矛盾や不合理なもので、「正解」はないといわれています。
このように、公案の世界では理屈を超えた気づきが求められます。
固定観念や、自分という枠組みを捨て、論理の壁を破った時に悟りが開かれ、その答えがわかると言われています。
公案の答えに客観的な「正解」は存在せず、その人がどのような心境から答えを導き出したかが重要とされます。
つまり、「知識よりも精神の成熟」が問われるのです。
現代社会に活かされる禅の精神
禅の考え方は、今日のマインドフルネス瞑想や心理療法とも共通点が多く、心を整えストレスを減らす方法として注目されています。
日常生活の中で「今ここ」に集中し、余計な思考を手放すことは、心の平穏を保つ手法として多くの人に支持されています。
また、ビジネスの現場でも禅の「無駄を省き、本質に集中する」という考え方が活用されています。
たとえば、アップルの創業者スティーブ・ジョブズも禅の影響を強く受けており、彼の製品や経営には禅の「シンプルさ」や「本質を大事にする」という考え方が色濃く反映されています。

禅は、単なる宗教儀礼ではなく「自分自身と向き合う生き方」を教える実践哲学です。
禅問答のように、矛盾や不合理と向き合いながら自分の執着を手放していく過程こそが悟りへの道だといえるでしょう。
現代の私たちにとっても、心を静め、物事の本質を見極める禅の教えは、日々の暮らしをより豊かにするヒントになるかもしれません。
関連:「だるま」の意味や由来とは?なぜ赤い色なの?選挙などで目を入れるのはなぜ?右と左どちらから?
関連:「僧侶」「住職」「和尚」「お坊さん」の意味と違いとは?


コメント