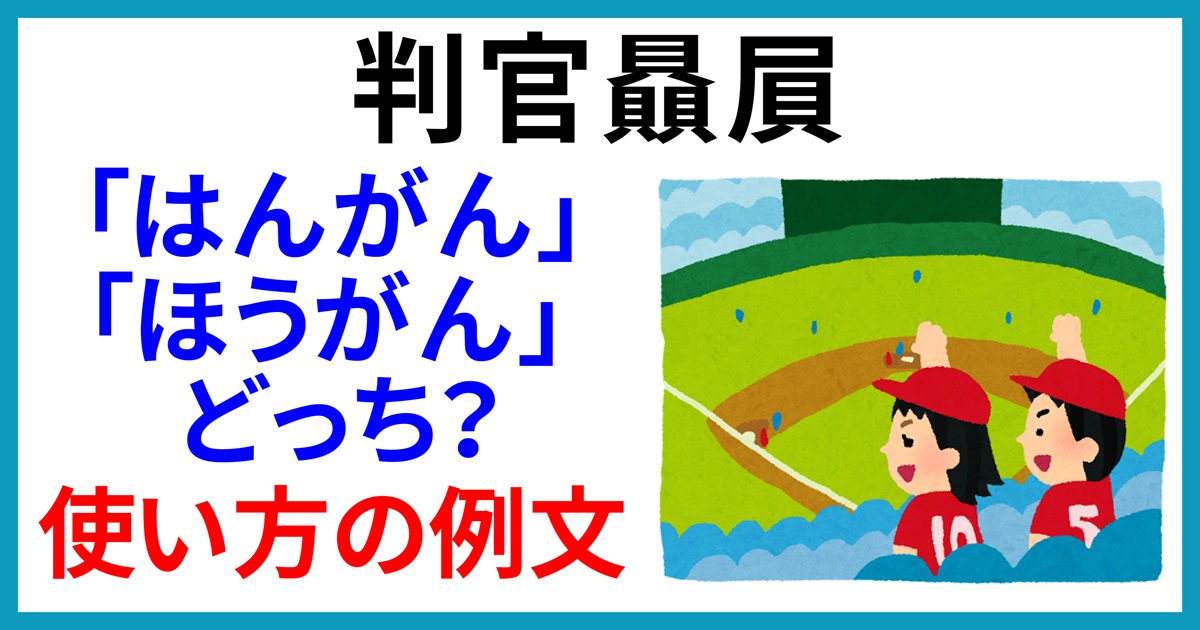
スポーツ観戦しているときによく使う言葉「判官贔屓」
この言葉の意味と由来とはどういうものなのでしょうか?
読み方は「はんがん」「ほうがん」どっちなのでしょうか?
使い方の例文なども合わせて紹介いたします。
判官贔屓の読み方は「はんがん」「ほうがん」どっち?
「判官贔屓」の読み方は一般的に「ほうがんびいき」です。
しかし、「はんがんびいき」と読んでも間違いではありません。
判官贔屓の意味とは?
「判官贔屓」の意味は、弱い立場の人、敗者、不幸な人、不運な人に同情したり、肩を持ったり、応援したりすることです。
判官贔屓の由来とは?

源義経
判官贔屓は、平安時代(794年~1185年)末から鎌倉時代(1185年~1333年)始めにかけて活躍した源義経(みなもとのよしつね・1159年~1189年)に対する人々の同情の気持ちが由来となっています。
義経の幼名(ようみょう・幼いころの名前)を「牛若丸(うしわかまる)」といいます。
「牛若丸」は、
- 丑(うし)年に生まれたから「牛」
- 幼い(若い)から「若」
- 男の子は一般的に「丸」が付けられていた
というのが由来です。
牛若丸といえば、弁慶(べんけい・生年不明~1189年)との以下のエピソードが有名ですよね。
平安時代の末、都に弁慶という僧がいました。
弁慶は比叡山で修行を積んだ腕の立つ武者でしたが、力の強さゆえに粗暴で、人並み外れた体格と腕力を誇っていました。
あるとき弁慶は、自らの力を試すため、「千本の刀を集める」という誓いを立て、通りに立ち、行き交う武士に勝負を挑んでは、その刀を奪い取っていきました。
やがて九百九十九本まで集め終え、最後の一本を求めて五条大橋に立ったのです。
その夜、橋の向こうから一人の若者が歩いてきました。
細身ながら凛とした姿、その腰には立派な刀が光っていました。
その若者が牛若丸(のちの源義経)です。

弁慶はいつものように挑みかかりますが、牛若丸は軽やかに身をひるがえし、欄干を飛び移りながら弁慶の大薙刀をかわしました。
弁慶の攻撃は次々と空を切り、ついには牛若丸の見事な太刀さばきに打たれ、倒れてしまいます。
弁慶は牛若丸の強さと見事な立ち居振る舞いに感服して家来になり、生涯にわたり牛若丸に忠義を尽くしました。
このように、五条大橋の戦いは、義経と弁慶の主従の固い絆のはじまりとして、今も語り伝えられています。
義経は源義朝(みなもとのよしとも・1123年~1160年)の九番目の子として生まれたため、「九朗(くろう)」という別名がありました。
そして、後に「判官(ほうがん)」を務めたことで、「九郎判官義経(くろうほうがんよしつね)」とも呼ばれていました。

検非違使
「判官」とは「検非違使(けびいし)」という平安時代の京都の治安維持を行った役人の中の「尉(じょう)」という役職の通称です。
「判官(尉)」は、実際に犯人を捜査し、裁判を執り行う重要な役割を果たしていました。
そして、義経をもとにした物語や作品は「判官物(ほうがんもの)」として、歌舞伎や浄瑠璃などさまざまな形で現在まで受け継がれています。

藤原秀衡
1160年に起きた平治の乱で父・義朝が敗れ、殺されたため、義経はのちに平泉(現在の岩手県南西部)へ移り、奥州藤原氏の第3代当主・藤原秀衡(ふじわらのひでひら・1122年~1187年)に保護されました。

源頼朝
その後、異母兄である源頼朝(1147年~1199年)が治承・寿永の乱(じしょう・じゅえいのらん・1180年~1185年)で、敵対する平家を討つために挙兵した際、義経が平泉から駆け付けました。
頼朝はこれを大変喜び、当初は兄弟の仲も良好だったそうです。
その後も義経は幾度もの合戦めざましい活躍を見せ、最終的に平家を滅ぼしました。
しかし、義経が頼朝を命令を無視し独断で戦を指揮したことや、頼朝の許可なく後白河法皇(ごしらかわほうおう・第77代天皇)から「判官」という役職を賜ったことなどで頼朝は義経を次第に疎ましく思うようになり、やがて敵対するようになりました。
頼朝は、義経が自分より力を持ち、いずれ自分を倒しに来るのではないかと警戒していたのではないかともいわれています。
義経は頼朝の追及を受けて、かつて庇護を受けた奥州藤原氏の藤原秀衡を頼って平泉へ逃れます。
しかし、間もなく秀衡が亡くなり、奥州藤原氏第4代当主となった藤原泰衡(ふじわらのやすひら・1155年~1189年)は頼朝の強い圧力に屈したため、義経は妻子を殺害したのち自ら命を絶ちました。
また、家来の弁慶は、頼朝方の軍勢が襲来した際、薙刀で敵を激しく迎え撃ち、敵の矢を全身に受けながらも一歩も引かずに立ち続け、そのまま絶命したことから「弁慶の立往生」と称えられています。
このような経緯があり、人々は、兄・頼朝に冷遇され、悲劇的な最期を遂げた義経に強い同情を抱くようになりました。
その結果、「判官(ほうがん)」という義経の官職名と、「贔屓(ひいき)=特別に応援したり、肩を持ったりすること」という言葉を合わせて、「弱い立場の人や悲劇の主人公に同情して味方すること」を「判官贔屓(ほうがんびいき)」と呼ぶようになりました。
この言葉は、室町時代末期から江戸時代初期にかけて使われ始めたと考えられており、1638年に成立した俳句集「毛吹草(けふきぐさ)」に登場しています。
「判官贔屓」の使い方の例文
「判官贔屓」は、弱いものが強いものと戦ったときに、弱いものを応援したり贔屓したりするときに使う言葉です。
使い方の例文は以下のとおりになります。
●甲子園で何度も優勝している学校よりも、初出場の学校を応援してしまうのは判官贔屓だよね
●弱小チームが強豪チームと対戦するときは判官贔屓で盛り上がる
●負けそうなチームを見るとつい判官贔屓で応援してしまうよね
●ダメな子ほど、判官贔屓で可愛く見えてしまう
「判官贔屓」は日本人だけ?
「判官贔屓」は源義経が由来でできた言葉ですから、日本人に根付いた価値観です。
しかし、日本人だけの価値観なのかというとそうではなく、海外でも似たような言葉があります。
英語では「underdog effect(アンダードッグ効果)」という言葉があります。
アンダードッグ(underdog)とは、「負け犬・かませ犬」という意味があり、スポーツの試合や選挙などで「勝ち目のない人やチーム」を指します。
そして、アンダードッグ効果は、日本の判官贔屓と同じように、不利な立場や劣勢な人を応援したくなるという心理現象を指します。
また、フランス語の「ressentiment」という言葉に似ていると思われることが多いようです。
日本語では「怨恨」と言う意味ですが、フランス語をそのまま読んで「ルサンチマン」と言うこともあります。
ルサンチマンは、弱者が強者に対して抱く「憤り、恨み、劣等感、嫉妬、増悪」などの感情を指す言葉です。
「ルサンチマン」と「判官贔屓」はどちらも弱者の感情に関する言葉ですが、以下のような違いがあります。
●ルサンチマン
弱者が強者に抱く感情です。
弱者である自分は強者には勝てないという憎しみや嫉妬、復讐心のような内向的かつ自己中心的なものです。
●判官贔屓
弱者に対し同情や肩入れなどの感情移入することです。
弱者への同情や共感が主となり、他者を応援しようという外向的な感情です。
つまり、ルサンチマンは弱者のネガティブな気持ちを指し、判官贔屓は弱者を応援するポジティブな気持ちを指すという違いがあります。
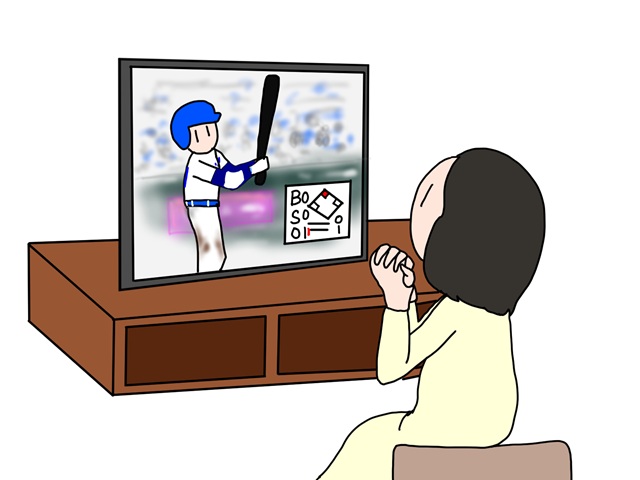
「判官贔屓」がどのようなものかわかりましたね。
鎌倉幕府の初代将軍となった源頼朝は強者であり、頼朝に疎まれて逃げるしかなかった義経は弱者でした。
弱者である義経に同情したり、肩入れしたくなる気持ちを表す「判官贔屓」という言葉は、室町時代末期から江戸時代初期にかけて日本人の間で使われるようになりました。
甲子園で「勝てないだろう」と思われている弱小チームをつい応援してしまうのも、こういった価値観や感情が長い年月を経て受け継がれているのでしょうね。
関連:【鎌倉幕府成立は何年?】歴史や理科の教科書の変更点【昔と今の教科書】

コメント