
みなさんは、衣替えはどのタイミングでしていますか?
学校や会社で制服を着る人は、日にちを決められているところもありますので、同じタイミングで衣替えをするかもしれませんが、そうではない場合はいつ行えばいいのでしょうか?
今回は、2025年の衣替えの時期などについてご紹介します。
衣替えの意味とは?
衣替えの読み方は「ころもがえ」です。
「衣更え」や「更衣」と書くこともあります。
衣替えの意味は、季節の変化に応じて衣服を替えることです。
また、収納場所の衣服を、夏服から冬服または冬服から夏服に入れ替えることも「衣替え」といいます。
衣替えの由来とは?
衣替えは、平安時代(794年~1185年)に中国の風習を取り入れた宮中行事が由来といわれています。
中国では旧暦の4月1日に冬から夏の衣類へ、10月1日に夏から冬の衣類へ替える風習がありました。
日本でもこの風習が取り入れられ、「更衣(こうい)」と呼ばれました。
しかし、更衣という名称は天皇に仕える女官の職名でも使われてたため、紛らわしいので「衣替え(ころもがえ)」と呼ぶようになったと言われています。
室町時代(1336年~1573年)から江戸時代(1603年~1868年)の初め頃は、夏と冬の衣服を年に2回替えるだけでしたが、江戸幕府によって武家では四季に応じて年4回の衣替えが制度化され、以下のように衣類の種類や着用する期間が細かく定められていました。
旧暦4月1日~5月4日
●袷(あわせ・裏地付きの着物)を着る期間

裏地付きの着物
旧暦4月1日は「綿貫(わたぬき)」といって、それまで着ていた「綿入れ(わたいれ・生地の間に綿を入れた着物)」から綿を抜いて「袷(あわせ・裏地付きの着物)」にします。
そのため、旧暦4月1日の衣替えのことを「綿貫」ということもあります。
綿を抜いた袷は5月4日まで着ますが、肌寒い日があれば、袷の下に小袖(こそで)を重ね着していました。
旧暦5月5日~8月末
●帷子(かたびら・裏地なしの着物)を着る期間
旧暦5月5日に、帷子へ衣替えをします。
帷子は夏用の涼しい着物で、さらに暑い日は「絽(ろ)」や「紗(しゃ)」「羅(うすもの)」という帷子よりも薄い着物を着ることもありました。
旧暦9月1日~9月8日
●袷(あわせ・裏地付きの着物)を着る期間
旧暦9月1日に帷子から袷に衣替えをします。
旧暦9月9日~3月末
●綿入れ(わたいれ・生地の間に綿を入れた着物)を着る期間
旧暦9月9日に袷に綿を入れる「綿入れ」を行い、冬の寒さに備えます。
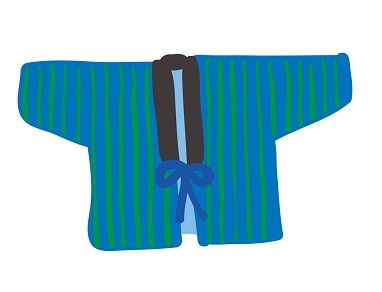
綿入れ
明治6年(1873年)に太陽暦(グレゴリオ暦)に改暦されると、明治政府は軍人や警察官など制服を、6月1日に冬服から夏服へ、10月1日に夏服から冬服へ衣替えすることにしました。
そして、次第にこれが一般の人たちにも広まり、制服のある学校や企業、スーツ着用の企業なども6月1日と10月1日に衣替えをするようになったのです。
また、6月1日と10月1日に一斉に衣替えをするのではなく、それぞれ前後2週間程度の移行期間が設けられており、この期間は冬服でも夏服でもどちらでも良いとする学校や会社などがほとんどです。

2025年「衣替え」の時期(春と秋)はいつ?
現在の衣替えは、
夏服へ衣替えをする6月1日
冬服へ衣替えをする10月1日
の年2回が一般的です。
ということで、2025年の衣替えの目安は、
夏服へ衣替えをする6月1日(日)
冬服へ衣替えをする10月1日(水)
春と秋に衣替えをすることもありその場合、
春の衣替えは4月1日
秋の衣替えは9月1日
を目安にしている人が多いようです。
春の衣替えの目安
2025年の春の衣替えの目安は4月1日(火)
春の衣類を着用する期間は4月1日(火)~5月31日(土)
夏の衣替えの目安
2025年の夏の衣替えの目安は6月1日(日)
夏の衣類を着用する期間は6月1日(日)~8月31日(日)
秋の衣替えの目安
2025年の秋の衣替えの目安は9月1日(月)
秋の衣類を着用する期間は9月1日(月)~9月30日(火)
冬の衣替えの目安
2025年の冬の衣替えの目安は10月1日(水)
冬の衣類を着用する期間は10月1日(水)~2026年3月31日(火)
また、日本は北と南で気温差があるため衣替えの時期も異なる場合があります。
例えば、一般的に
北海道では、
夏服は6月中旬ごろ~9月中旬ごろ
冬服は9月中旬ごろ~6月中旬ごろ
沖縄では、
夏服が5月1日~10月31日
冬服は11月1日~4月30日
衣替えの日はあくまで目安ですので、気温によって衣替えの時期を決めることもあります。
制服などは規則に従うことになりますが、そうではない私服や普段着の場合は、気温や体調を考慮して個人の判断で行うといいですね。
収納時のコツとは?
収納時のコツは以下のとおりです。
収納前に洗濯をする
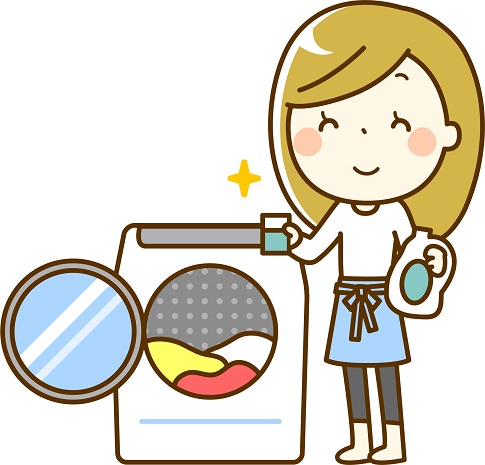
「一度しか着ていないから、洗濯はしない」という人もいるようですが、見えない汚れや汗などがついていますので、洗濯をせずに収納すると虫食いの原因になります。
洗濯できない衣類はクリーニングに出すようにしましょう。
収納前に虫干しをする
空気が乾燥し、天気が良い日に陰干しすることを「虫干し」といい、衣類に虫がついたりカビが発生することを防ぐために行います。
収納する日は天気の良い日に
衣替えをする日は、湿気が少なく乾燥した日、天気が良い日を選びましょう。
雨の日や湿気の多い日に衣替えをすると、虫がついたりカビが発生したりしやすくなります。
丁寧にたたみましょう

衣類をぐちゃぐちゃに収納してしまったら、次に着る時にしわだらけになっていますので、丁寧にたたんでから収納するようにします。
コートやスーツ、スカートなど、型崩れが心配なものはたたまずにハンガーにかけたままの方が良いものもありますので、収納する前に確認しておきましょう。
ふんわりと収納する
丁寧にたたんだ衣類を、収納ケースや箪笥にぎゅうぎゅうに入れると、しわや型崩れの原因になってしまいますので、ふんわりと余裕をもって収納しましょう。
中身がわかるように収納する
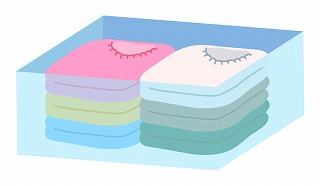
衣装ケースを透明なものにするとか、中になにが入っているのか書いておくとか、中身がわかるように収納することで、急に必要になった時や、次の衣替えの時に手間を省くことができます。
防虫剤や湿気取りシートを使う
衣類を収納する際は、収納ケースや箪笥などに防虫剤や湿気取りシートを入れて、虫食いやカビの発生を防ぎます。
クリーニングの保管サービスを利用する
最近は、クリーニングに出した際に長期間保管してくれるサービスがあります。
自宅の収納スペースが少ない場合は、次の衣替えまで保管してもらっておくと良いですね。
「衣替え」はいつの季語?
すでに説明した通り、衣替えは年に2回もしくは4回行いますが
「衣更え」
「更衣」
「衣替え」
は夏の季語になります。
有名な俳句は以下のものがあります。
●松尾芭蕉
『ひとつぬひで 後に負ぬ 衣がへ』
(ひとつぬいで うしろにおいぬ ころもがえ)
「旅の途中なので、衣替えの日になっても着替えの夏ものがない。着ていた一枚を脱いでうしろに背負って、これで衣替えが済んだことにしよう」という意味です。

「衣替え」がどういうものかわかりましたね。
「もう冬服は必要ないだろう」と思って衣替えをしたのに、急激に気温が下がってしまうことがありますし、夏服を仕舞ったのに暑い日が戻ってくることもあります。
季節の変わり目は体調を崩す人も増えますので、「この日から衣替えだから」と日付だけにこだわらずに、体調も考慮して衣替えの日を決めてくださいね!
関連:四季(春夏秋冬)の期間はいつからいつまで?季節の区切り方とは?
関連:【俳句の季語一覧】小学生向け 春夏秋冬新年 月ごと(1月~12月)の季語

コメント