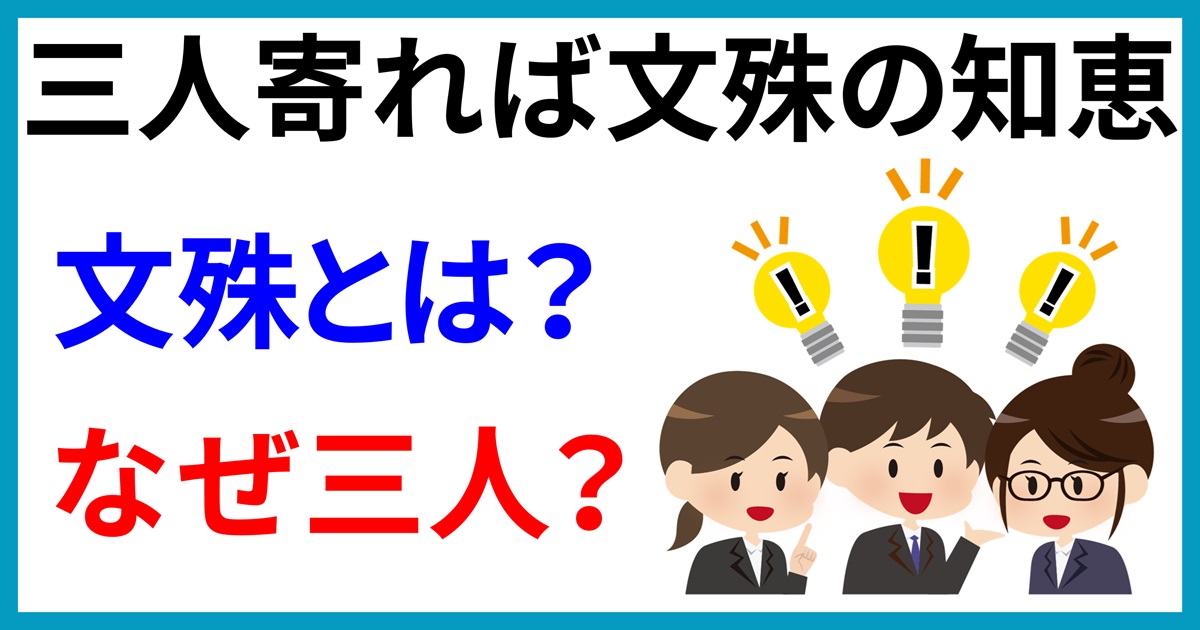
「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあります。
このことわざの「文殊」とは、どういう意味なのでしょうか?
また、なぜ三人なのでしょうか?
「三人寄れば文殊の知恵」の意味や、使い方の例文をご紹介します。
「三人寄れば文殊の知恵」の文殊の意味とは?
読み方は「さんにんよればもんじゅのちえ」です。

文殊菩薩
「文殊」は「文珠」とも書き、どちらも文殊菩薩(もんじゅぼさつ)を意味します。
文殊菩薩は、智慧を司る菩薩です。
菩薩とは「悟りを求めて他人を救う修行者」を指す仏教用語で、サンスクリット語の「ボーディサットヴァ(Bodhisattva)」が由来です。
関連:仏の名前「如来」「菩薩」「明王」「天部」「観音」「阿修羅」「阿弥陀」の意味と違いとは?
また、「三人」は具体的な数字として使うことが一般的ですが、「複数人」という意味で使うこともあります。
「知恵」は「智慧」とも書きます。
智慧は仏教用語です。
一般的には「智慧」と「知恵」は同じ意味で使われていますが、仏教では区別されています。
「智慧」は、真実や本質を見極める深い洞察力を指します。
「知恵」は、持っている知識を使って物事を判断したり、問題を解決する能力を指します。
このように、「智慧」と「知恵」は違う意味ですが、一般的にはどちらも「知恵」の意味で使われています。
つまり、「三人寄れば文殊の知恵」は、
「凡人でも三人(複数人)が集まって相談をすれば、文殊菩薩のように素晴らしい知恵がでる」
という意味になります。
また、四字熟語の「三人文珠(さんにんもんじゅ)」も同じ意味になります。

荘子
「三人寄れば文殊の知恵」の語源については諸説ありますが、中国の思想家である荘子(そうし・紀元前369年ごろ~紀元前286年ごろ)の「一人の賢者がいても役に立たないが、三人の愚者がよれば賢者の知恵が生まれる」という思想が由来という説が有名です。
この考え方から「三人寄れば文殊の知恵」が生まれたといわれています。
なぜ三人?
「三人寄れば文殊の知恵」がなぜ三人なのかは不明で、いくつかの考え方があるようです。

話し合いが成立するから
一人では話し合いができず、二人ではどちらかに意見が偏るが、三人いれば話し合いが成立する。
「三」という数字が好まれるから
たとえば、「三種の神器(さんしゅのじんぎ)」や「仏教の三宝(さんぽう)」など、「三」を特別な数字として好んで使われていた。
三種の神器とは、日本神話の時代から現代まで受け継がれている三つのものや、三つの家電製品を指します。
仏教の三宝は、仏、法、僧を指し、仏教において最も大切な宝といわれています。
関連:【三種の神器】意味と歴史とは?どこにあるの?見てはいけない理由
「三人寄れば文殊の知恵」の使い方の例文
「三人寄れば文殊の知恵」の使い方の例文をいくつかご紹介します。
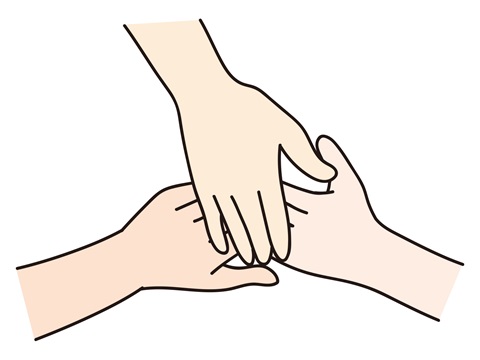
●一人で悩んでも問題は解決しないから仲間にも声をかけてごらんよ、三人寄れば文殊の知恵と言うでしょう?
●自由研究がなかなかはかどらなかったけれど、友達と三人で協力したらあっという間だったよ、まさに三人寄れば文殊の知恵だね!
●プロジェクトに行き詰ったのなら、みんなで話し合って解決策を考えようよ。三人寄れば文殊の知恵だよ。
●一人で悩んでいたけれど友達に相談したら良い解決策が見つかって、三人寄れば文殊の知恵を実感したよ。
●このクイズは難問だね。三人寄れば文殊の知恵だからみんなで答えを導きだそう!
三人寄れば文殊の知恵の類義語は?
類義語は、以下のものがあります。
三本の矢(さんぼんのや)
「三本の矢」とは、何人もの人間が力を合わせれば、非常に強い力を発揮できることのたとえです。
誰の言葉かというと、戦国時代の武将である毛利元就(もうりもとなり・1497年~1571年)です。

毛利元就
元就が死ぬ間際、三人の息子を枕元に呼び寄せました。
最初に一本の矢を息子たちに渡して折らせ、次に三本の矢を束にして折るように命じましたが、三人の息子は誰も折ることが出来ませんでした。
一本であればすぐに折れる矢も、三本が束になれば頑丈になり折れなくなることから、三人の息子が力をあわせれば誰にも負けることはないと諭したそうです。
衆知を集める(しゅうちをあつめる)
多くの人の知恵を集めるという意味です。
衆議一決(しゅうぎいっけつ)
大勢の人の意見や議論を経て、全員で相談して決定することという意味です。
一人の好士より三人の愚者(いちにんのこうしよりさんにんのぐしゃ)
「好士」は、優れた人物のことです。一人の優れた人物よりも、愚者が三人集まったほうが知恵が集まるという意味です。
三人寄れば文殊の知恵の対義語は?
対義語は、以下のものがあります。
船頭多くして船山に登る(せんどうおおくしてふねやまへのぼる)
指図する人間が多いと統率が取れず、見当違いの方向に物事が進んでしまうことのたとえです。
三人寄っても下種は下種(さんにんよってもげすはげす)
下種とは、心が卑しい人のことです。
三人集まって考えても、心が卑しい人ばかりではどうにもならないという意味です。
英語でなんという?
「三人寄れば文殊の知恵」と同じような意味の英語の慣用句があります。
●two minds are better than one
直訳すると「二つの頭は一つより良い」ですが、
「問題を解決するのなら、一人よりも二人が良い」という意味になります。
two=二つ
minds=心、思考
better=より良い、より優れている
than=~よりも
one=一つ

「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがどういうものかわかりましたね。
一人で悩んでいてもどうにもならないことでも、誰かに助けを求めれば良い解決策がみつかることはよくある話です。
何かに悩んだ時、行き詰ったときなどは「三人寄れば文殊の知恵」ということわざを思い出して、周りに相談すると良いかもしれませんね!
関連:【座右の銘100選】座右の銘にしたい「ことわざ・格言・名言」一覧
関連:「見ざる聞かざる言わざる」三猿の意味と由来とは?本当は四猿?

コメント