
みなさんは「お茶漬け」を食べるときお茶とお湯のどちらを入れますか?
「お茶漬け」の意味や定義はどんなものでしょうか?
今回は「お茶漬け」についてその歴史や由来とともに解説します。
お茶漬けの意味や定義とは?
お茶漬けの意味は「ご飯にお茶をかけたもの」です。
お茶は、煎茶や番茶、ほうじ茶、抹茶など、日本茶を指すことが一般的です。
しかし、出汁や烏龍茶などをかけた場合も「お茶漬け」といいます。
また、お茶や出汁などと一緒に、漬物や海苔、魚、梅干などいろいろな具をご飯に乗せたものも「お茶漬け」といいます。

お茶漬けと似たものに「湯漬け(ゆづけ)」があります。
湯漬けはご飯に白湯(さゆ・お湯のこと)をかけたもので、お茶漬けのルーツといわれています。
漬物や海苔など具をのせた後に白湯をかける場合、厳密には「湯漬け」に分類されますが、「お茶漬け」と呼ぶことが多いです。
このように、「お茶漬け」の明確な定義というものはありません。
関連:お茶(緑茶・煎茶・番茶・玉露・ほうじ茶・抹茶)の種類の違いと意味とは?
お茶漬けの歴史と由来とは?
お茶漬けがいつごろから食べられるようになったのか、定かではありません。
縄文時代の終わりごろから弥生時代にかけて日本で稲作が始まりましたが、稲作の始まりとともに、ご飯にお湯または水をかけて食べることはあったのではないかと考えられています。

記録として残っているのは、平安時代(794年~1185年)になってからです。
源氏物語や枕草子、今昔物語などの文学作品や文献に「湯漬け」や「水飯(すいはん)」が登場します。
「湯漬け」はご飯に白湯をかけたもの、「水飯」は米飯に水をかけたもので、お茶漬けのルーツとされています。
この頃のご飯は、現在のように炊いた後に保温する技術がなかったため、時間の経過とともにどんどん冷えて、乾燥してしまいました。
そのような状態でも美味しく食べる方法として、お湯や水をかけるようになったと考えられています。

お茶をご飯にかけるようになったのは江戸時代(1603年~1868年)になってからといわれています。
商家などの使用人は仕事の合間に食事をするので、短い食事時間で早く済ませるためにお茶漬けを食べるようになりました。
このころになると番茶や煎茶が一般に普及し、ご飯に熱いお茶をかけて食べたことから「お茶漬け」と呼ばれるようになったようです。

食事の内容も質素なもので、使用人にとって唯一のおかずになるのが漬物だったため、ご飯にお茶や水をかけ、そこに漬物を乗せて食べていたそうです。
お茶漬けを提供する「茶漬屋」というお店も登場し、手軽に早く食事ができるので庶民の間で広く親しまれました。
江戸時代後期になると、厳選した水でお茶を淹れてお茶漬けにしたり、漬物のほかに魚、佃煮、梅干しなどを具にするお店も登場しました。

昭和27年(1952年)に永谷園が、インスタント茶漬けの「お茶づけ海苔」を発売します。
乾燥させた具と出汁やお茶の粉末を混ぜたものが小袋に入っており、ご飯にかけてお湯を注げばそのままお茶漬けとして食べることができる製品です。
現在は永谷園のほかにもマルハニチロや丸美屋食品などもインスタント茶漬けを販売しており、梅や鮭、たらこ、わさびなどいろいろな具の種類があります。
インスタント茶漬けも様々な種類が販売されており、地域の特産品などを使った「地域限定茶漬け」なども人気になっています。
お茶漬けに入れるのはお茶とお湯どちら?

インスタント茶漬けの場合は出汁やお茶の粉末がすでに入っており、袋には「お湯をかける」と食べ方の説明があります。
本来であればお湯をかけるだけで良いのですが、お茶をかけて食べる人もいます。

お店でお茶漬けを食べる時は、お茶やお湯でではなくお店のこだわりで出汁をかけることもあります。
自分で作るときは、番茶や煎茶のほかに、昆布茶や抹茶などをかける人もいるそうです。
このように作り方に決まりはなく、食べ方の好みも人それぞれですから「お茶漬けはお茶とお湯、どちらでも良い」ということになります。
お茶漬けの日とは?
5月17日は「お茶漬けの日」です。
インスタント茶漬けの「お茶漬け海苔」が60周年を迎えた記念に、平成24年(2012年)に永谷園が制定しました。
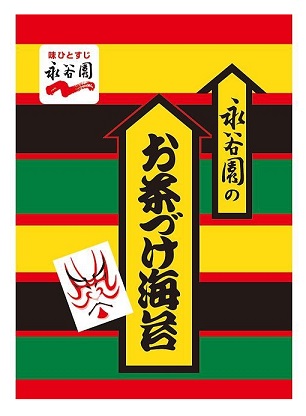
「お茶漬けの日」は煎茶の製法を発明した永谷宗七郎(宗円)(ながたにそうしちろう(そうえん)・1681年~1778年)の命日で、その偉業をたたえて命日である5月17日に制定しました。
永谷園の創業者である永谷嘉男(ながたによしお)は永谷宗七郎(宗円)の子孫です。
お茶漬けは英語で何て言う?
ちなみにお茶漬けのことを英語でなんというのでしょうか?
お茶漬けは英語圏にはありませんので、単語などはなく、以下のように説明することになります。
・boiled rice with tea (お茶とご飯)
・boiled rice soaked with tea (お茶で浸したご飯)

お茶漬けは、体調が悪い時に食べてもいいですね。
二日酔いや食欲が無い時にもサラサラと食べることができますので、インスタント茶漬けを常備しておくと便利ですよ。
暑い夏には、水や氷水をかけて食べる人もいますし、作り方にも決まりはありませんので、自分好みのお茶漬けを見つけるのも良いかもしれませんね。
関連:お茶の種類(緑茶・煎茶・番茶・玉露・ほうじ茶・抹茶)の違いと意味とは?
関連:【2025年】新茶と一番茶の時期とは?新茶と一番茶、二番茶、三番茶の意味と違い
関連:茶柱が立つと縁起がいいのはなぜ?茶柱が立つ理由と確率とは?

コメント
コメント一覧 (4件)
ブログ楽しく拝見させて頂きました。
私もお茶漬けが好きで自分で作って食べています。主にご飯に緑茶をかけ、塩、海苔、あられを入れて食べています。お茶のみをかける事もありますし、その場合暑い時期には冷たいお茶をかける事もあります。
お茶は緑茶に限らずほうじ茶、麦茶、烏龍茶等なんでも美味しいですね。
ブログはお茶漬けの歴史が分かり大変面白かったです。お茶漬けのルーツが縄文、弥生時代にまで遡る事には驚きでした。
また機会があれば次回も投稿して頂ければ嬉しいです。どうもありがとうございました。
コメントありがとうございます。
とても励みになります!
何の気なしに、お茶漬けって白湯?お茶が正しい?と調べて最初に出てきたので読みました。
自分の祖父母が明治生まれで、奉公に出た人だったのでとても厳しい人でした。
食のマナー、気遣いは特に。
香の物は単に箸休めではなく、一枚だけ残して最後は茶碗をこそぐようにとか、お茶を少しだけ茶碗に入れて汚れを落としてからご馳走様をしなさいとか。食事をした後を片付ける人のことまで考えなさいと。今は水道も食洗機もあります。
基準は地方、時代と共に変化するものなのでしょう…。
楽しく読ませていただきました。
コメントありがとうございます。
明治生まれのご祖父母様の食事の作法のお話、大変興味深く拝読いたしました。
貴重なお話ありがとうございました。