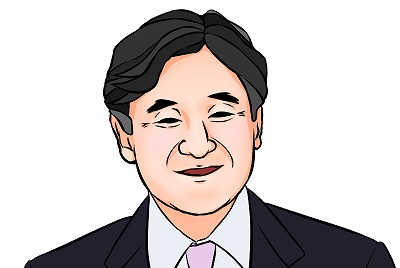
日本の象徴として天皇陛下がおられます。
今上天皇(現在の天皇陛下)のお子様は愛子さまですから、次の天皇は愛子さまでは?と思う人もいらっしゃるかもしれません。
しかし、愛子さまは女性なので皇位継承権(次の天皇になるための資格)をお持ちではありません。
それはどういうことなのか、女系天皇と女性天皇の違いなどをわかりやすく解説します。
天皇に女性がなれないのはなぜ?

日本の初代天皇は「神武天皇(じんむてんのう)」で、紀元前660年に即位されました。
今上天皇は126代天皇ですので、歴代天皇はこれまでに126人いらっしゃったということなのですが、その中に、女性の天皇は8人いらっしゃいました。
ですので「女性は天皇になれない」というわけではありませんでした。
では、なぜ愛子さまには皇位継承権がないのでしょうか?
それは、昭和22年(1947年)に「皇室典範(こうしつてんぱん)」第一条で「皇位は皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められたからです。
過去に女性の天皇は8人いらっしゃいましたが、どなたも皇室典範が定められるずっと以前に天皇になられた方です。
最後に女性天皇となられた「後桜町(ごさくらまち)天皇」の在位は江戸時代の1762年~1770年だったのです。

後桜町天皇
また、皇室典範で「男系の男子にしか皇位継承権がない」と定められていますが、過去に天皇になられた8人の女性は、どなたも「男系女子」の「女性天皇」であり、「女系女子」はいらっしゃいません。
女系と女性の違いとは?
まず、「男系女子」についてですが、これは「父方が天皇に繋がる女子」のことであり、今上天皇のお子様である愛子さまも「男系女子」です。
さらに、ご結婚をして皇室から離れましたが、上皇陛下のお子様である黒田清子(くろださやこ)さんも「男系女子」ですし、秋篠宮家の佳子さまも「男系女子」です。
では、「女系」と「女性」の違いはどこにあるのでしょうか?
「女系」とは?
「女系」とは、母方に天皇がいらっしゃる皇族のことで、もし天皇になられた場合は「女系天皇」となります。
たとえば、
「母親が天皇」
「母親のお父様が天皇」
「母親のおじ様が天皇」
など、母親が天皇と繋がっていることをいいます。
たとえば、愛子さまは、お父様はが今上天皇なので「男系女子」ですが、愛子さまが将来、民間の男性とご結婚なさり、お子様が生まれた場合、そのお子様は男児であれ女児であれ「女系」になります。
そして、そのお子様が天皇に即位された場合は男児であれ女児であれ「女系天皇」となります。
「女性」とは?
「女性」とは文字通り女性皇族のことで、もし天皇になられた場合は「女性天皇」となります。
「女性天皇」とは、男系女系にかかわらず、女性が天皇になると女性天皇になります。
たとえば、愛子さまが将来、天皇になられた場合は「女性天皇」ということになります。
いずれにしても、現在の皇室典範では「皇位は皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められているので、「女系天皇」も「女性天皇」もありえないということになります。
女系・女性天皇を認めない理由
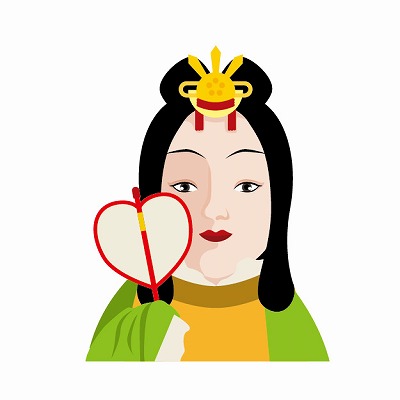
現在、皇位継承権があるのは男系男子である
・今上天皇の弟である秋篠宮皇嗣殿下
・秋篠宮皇嗣殿下のご長男である悠仁さま
・上皇陛下の弟である常陸宮さま
の3人です。
3人しか皇位継承者がいらっしゃらないのは、とても深刻な問題です。
昔はどうだったのか振り返ってみると、明治時代までは皇后とは別に認められた「側室」と呼ばれる女性たちがいました。
明治天皇と皇后の間にはお子様ができませんでしたが、5人の側室との間に5男10女を設けました。

明治天皇
大正天皇は側室をもたず、それ以降、民間人と同じように一夫一婦制となりますが、大正天皇は4人の男のお子様を設けました。
明治時代以前は側室もおられましたし、もしも男児に恵まれなくても、天皇家ではなく「宮家(みやけ)」の男児が天皇に即位することで「男系」が保たれてきました。
「宮家」とは、天皇から特別に「宮号(みやごう)」を与えられた皇族の一家のことです。
現在は、
「秋篠宮家」
「常陸宮家」
「三笠宮家」
「高円宮家」
がありますが、皇室典範が定められる前はもっと多くの宮家がありました。
皇室典範が定められたのは終戦直後で、昭和22年(1947年)にGHQ(連合軍総司令部)の占領政策によって、11の宮家が皇籍を離れ、民間人となりました。
宮家については以下の記事をご覧ください。
その結果、令和元年(2019年)には皇位継承者が3人となり、「女性天皇を認めよう」という動きがでてきているのです。
「女性天皇」が認められれば、愛子さまだけではなく佳子さまも皇位継承者となりますが、それを反対する最大の理由は「万世一系(ばんせいいっけい)」という考え方です。
「万世一系」とは、父方の家系をさかのぼると、初代天皇である神武天皇に繋がるという考え方です。
もしも「女性天皇」が民間人と結婚した場合、生まれてくるお子様は「女系」となり、父方をさかのぼっても神武天皇には繋がりません。
「万世一系」が途絶えてしまうことは避けたい、126代にわたって受け継がれてきた伝統を途切れさせるわけにはいかない、などの理由が大きいのです。
過去の歴代女性天皇
過去の歴代女性天皇は以下の表のとおりです。
| 代 | 女性天皇 (即位期間) |
父親 |
次期天皇 |
| 33 | 推古天皇 (592-628) |
29代 欽明天皇 |
舒明天皇 |
| 35 | 皇極天皇 (642-645) |
30代 敏達天皇の男孫 |
孝徳天皇 |
| 37 | 斉明天皇 (655-661) |
30代 敏達天皇の男孫 |
天智天皇 |
| 41 | 持統天皇 (690-697) |
38代 天智天皇 |
文武天皇 |
| 43 | 元明天皇 (707-715) |
38代 天智天皇 |
元正天皇 |
| 44 | 元正天皇 (715-724) |
40代 天武天皇の皇子 |
孝謙天皇 |
| 46 | 孝謙天皇 (749-758) |
45代 聖武天皇 |
淳仁天皇 |
| 48 | 称徳天皇 (764-770) |
45代 聖武天皇 |
光仁天皇 |
| 109 | 明正天皇 (1629-1643) |
108代 後水尾天皇 |
後光明天皇 |
| 117 | 後桜町天皇 (1762-1770) |
115代 桜町天皇 |
後桃園天皇 |
※「皇極天皇と斉明天皇」「孝謙天皇と称徳天皇」はそれぞれ同一人物です。
8人10代の女性天皇がいらっしゃいましたが、どなたも父方が神武天皇に繋がる「男系女子」です。
8人の中でご結婚なさったのは推古天皇、皇極天皇(斉明天皇)、持統天皇、元明天皇の4人で、他の4人は未婚でした。
また、「女性天皇」のお子様の中には、天皇に即位なさった方もいらっしゃいますが、この場合「女系天皇」とはなりません。
なぜなら、「女性天皇」が多い飛鳥時代(592年~710年)から奈良時代(710年~794年)には「男性皇族は民間人を妻にできるが、女性皇族は男性皇族としか結婚できない」という決まりがあったからです。
そのため、「女性天皇」のお子様であっても、父方をたどれば神武天皇に繋がるため「男系」が保たれたのです。

「女系天皇」と「女性天皇」を混同してしまう人が多いようですが、全く異なる存在なのですね。
およそ2700年に渡って「男系」が受け継がれているのは、世界中を見渡しても日本の天皇家だけなのだそうです。
現在「女性は天皇になれない」のは、皇室典範という法律で定められているからで、皇室典範の見直しが行われれば「女性天皇」が誕生するかもしれません。
しかし、その先をどうするのか考えると、そう簡単に見直すわけにもいかないようですね。
関連:紀元節とは?現在の呼び名は?2025年今年は皇紀何年?
関連:女性宮家とは?女性宮家創設の必要性と「女性天皇・女系天皇」の違いとは?

コメント
コメント一覧 (2件)
天皇男系継承の由来は、特殊能力遺伝子の継承から来ているのではないではないでしょうか?元々は、祭祀ですし。
コメントありがとうございます!