
「テレコ」という言葉を聞いたことはありますか?
ビジネスシーンで使う言葉?
それとも、一部の人にしかわからない業界用語?
何かの固有名詞?もしかして方言?!
または英語?
いろいろ考えてしまいますね。
今回は「テレコ」についてわかりやすく解説します。
「テレコ」の意味とは?
「テレコ」とは 関西の方言で、「入れ違い」という意味があります。
関西弁として一般的に使われている言葉です。
また、 物流や運送業界でも「入れ違い」という意味で使われています。
テレコの類語としては、「入れ違い」の他、
「互い違い」
「入れ替え」
「あべこべ」
「食い違い」など
が用いられます。
表面をデコボコにした生地を「テレコ生地」と呼んだり、「テープレコーダー」を略して「テレコ」と呼ぶ場合もありますが、この記事では、入れ違いの意味のテレコについてご紹介いたします!
「テレコ」の使い方とは?
関西では日常的に「テレコ」が会話の中で登場します。(以下は標準語で書いています)
●待ち合わせしていた友人とテレコになってしまった。
●テレビの配線がテレコだったから壊れてしまったよ!
●靴下がテレコになっているよ。

物流や運送業界では「入れ違い」という意味で以下のように使います。
●A社とB社、テレコになってしまった(A社とB社の荷物を入れ違えて納品してしまった)
●今日の配達分がテレコになっている(今日の配達分の荷物が、順番が入れ違いになっている)
テレコの語源は歌舞伎用語から?

「テレコ」の語源は歌舞伎用語だといわれています。
もともと、歌舞伎では二つの異なる筋の脚本をひとつにまとめ、関連性を持たせながら一幕ごとに交互に進行することを「てれこ」と言っていました。
このことから、交互になること、互い違いになることを「てれこ」と言うようになったようです。
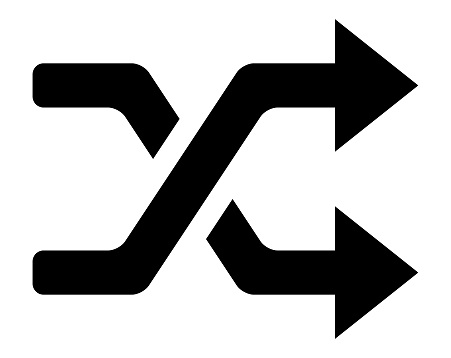
語源は以下のような説があります。
●「手(テ)入れ(レ)」(手を加えるという意味)と「交(コ)互に」が合わさって「テレコ」になった説
●「手入れ」と接尾語の「こ」が合わさって「テレコ」になった説
接尾語とは、ほかの言葉の下にいて一語を形成する言葉です。
「テレコ」の場合は「かわりばんこ」「取り替えっこ」などと同様の「こ」が合わさっています。
歌舞伎で用いる場合はひらがなで「てれこ」と書き、それ以外ではカタカナで「テレコ」と書くことで区別しているそうです。
英語で何て言う?
テレコは英語でないことがわかりましたが、ちなみにテレコのことを英語でなんと表現するのでしょうか?
「テレコ」は方言ですが、「互い違い」「入れ違い」「入れ替え」「あべこべ」「食い違い」などは英語にすると以下のようになります。
●Alternate(互い違い)
●Passing each other(入れ違い、すれ違い、など)
●Replacement(入れ替え、差し替え、取り替え、など)
●Other way around(あべこべ、逆に、逆さま、など)
●Discrepancy(食い違い、不一致、矛盾、など)

関西では日常会話で普通に使われている言葉ですが、関西以外の地域の人が会話の中で「テレコ」と聞いても、ピンとこないかもしれません。
ほかの地域の人からすると何を言っているのかわからないことでも、その地域の人にとっては当たり前の言葉だったりすることがよくありますよね。
日本という小さな島国の中でたくさんの方言があるというのは、とても不思議で面白いですね!
関連:関東と関西の違い!食べ物や言葉、文化の違いをまとめてみました!
関連:「関西」「近畿」「畿内」「上方」「なにわ」の意味と違いとは?
関連:歌舞伎の家柄の関係と違いとは?ランク付けした場合の序列は?
関連:能、狂言、歌舞伎とは?違いを簡単にわかりやすく説明すると

コメント