
「うどん」といえば、老若男女日本人が大好きな国民食の一つですよね!
温かいうどん、冷たいうどん、豪華なトッピングをしたり、シンプルに出汁だけで食べたり、いろいろな食べ方があります。
この記事では、私たちが大好きなうどんの発祥と歴史、有名なご当地うどん(日本三大うどん)の種類と好きなうどんをランキング形式でご紹介します!
うどんとは?
うどんは漢字で「饂飩」と書きます。
うどんとは、小麦粉を少量の塩水と混ぜて練り、ある程度の太さを持つ麺のことをいいます。

JAS規格(日本農林規格)によると
麺の太さが直径1.7mm以上がうどんです。
そして、うどんと材料が同じそうめんとひやむぎは太さで区別されています。
そうめん・・・直径1.3mm未満
ひやむぎ・・・直径1.3mm以上1.7mm未満
となっています。
うどんの発祥と歴史とは?
うどんの起源は中国といわれていますが、いつ日本に伝わったのかは定かではなく、諸説あります。
混飩(こんとん)が起源
奈良時代(710年~794年)、遣隋使によって中国から渡来した「混飩」という、小麦粉の団子に餡が入った団子菓子が起源という説があります。
混飩を温かい汁に入れて食べるようになり「温飩(おんとん)」と呼ばれるようになりました。
これが転じて「おんとん」→「うんとん」→「うどん」になったと言われています。
空海が広めた
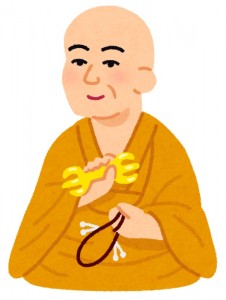
平安時代(794年~1185年)に、空海(後に弘法大使と呼ばれる・真言宗の開祖)が、遣唐使とともに中国へ渡り、うどんの技術を日本に持ち帰って貧しかった故郷の人々を救ったといわれています。
讃岐うどんで有名な讃岐地方(香川県)は空海の故郷です。
博多が発祥の地

承天寺
仏教の修行で宋(そう・当時の中国)へ行っていた円爾(えんに・1202年~1280年、臨済宗の僧)は、鎌倉時代の1242年、博多に承天寺(じょうてんじ)を創建しました。
円爾は宋から持ち帰った水車による製粉技術によってうどんを作り、うどんを博多から日本中に広めたことから、博多がうどん発祥の地といわれています。
福岡県福岡市博多区の萬松山(ばんしょうざん)承天寺には、「饂飩蕎麦発祥之地碑」があります。

饂飩蕎麦発祥之地碑
このように発祥には諸説ありますが、鎌倉時代(1185年~1333年)ごろに、練った小麦粉を細く切った「切麦(きりむぎ)」と呼ばれるものが登場し、これが現在のうどんの原型といわれています。
切麦はうどんよりも細いので、そうめんやひやむぎの原型ともいわれています。

切麦が太く現在のうどんのような形になり、庶民に食べられるようになったのは江戸時代(1603年~1868年)初期の頃といわれています。
江戸時代には各地にうどんを提供するお店ができ、次第に家庭でもうどんを食べるようになります。
この時に、太めのうどん、細めのうどん、冷たいうどん、温かいうどんなど地域によっていろいろな調理法が生まれたようです。
そしてその地域で独自の進化をしたことで現在のように地域によってさまざまな「ご当地うどん」が誕生したといわれています。
有名なうどんの種類
有名なご当地うどんといえば、「日本三大うどん」です。
日本三大○○には様々なものがありますが、それを決めるための明確なルールは存在せず、観光地や名産品をアピールするために考えられたものといわれ、時代や選ぶ人、地域によって答えが異なる場合があります。
日本三大うどんも、ひとつ目とふたつ目は変わらないのですが、3つめが地域によって異なります。
香川県の讃岐うどん
ひとつ目は、香川県の特産でもある讃岐うどんです。

香川県のうどん消費量は全国第一位で、「うどん県」と呼ばれることもあります。
讃岐うどんの一番の特徴は強いコシです。
そして、数多くあるうどんの中でも「讃岐うどん」の知名度はとても高いです。
秋田県の稲庭うどん
ふたつ目は秋田県の特産でもある稲庭(いなにわ)うどんです。

稲庭うどんの特徴は、手延べ製法で作られた乾麺です。
うどんとしては細く平べったい形をしていて、なめらかな食感です。
3つ目は地域によって異なる
3つ目は、いずれも有名なご当地うどんですが地域によって異なり、以下のものが挙げられます。
群馬県の水沢うどん

水沢うどんの特徴は、透明感のある麺です。
生地を伸ばして寝かせることを繰り返すため、強いコシと弾力ある麺になり、そのコシと弾力を楽しむためにざるうどんとして食べられることが多いです。
長崎県の五島うどん

「五島手延べうどん」とも呼ばれています。
五島うどんの特徴は、椿油を塗って熟成させて作る細麺です。
艶やかでなめらかな食感になります。
愛知県のきしめん

きしめんの特徴は、薄く幅広い麺で「平打ちうどん」とも呼ばれます。
滑らかでコシが弱く、やわらかい食感です。
富山県の氷見うどん

氷見うどんの特徴は、しっかりとした歯ごたえと、餅のような粘りのある食感です。
三重県の伊勢うどん

三大うどんではありませんが、三重県の伊勢うどんもとても有名です。
太くて柔らかい麺を、出汁と伊勢だまりを合わせた独特の色の濃いタレで食べます。
好きなうどんランキング!
うどんには、「きつねうどん」「天ぷらうどん」「カレーうどん」などなど数えきれないほどありますね!
好きなうどんランキングで見てみましょう!
1位 きつねうどん

うどんに甘辛く煮た油揚げをトッピングした「きつねうどん」が1位です。
甘辛い油揚げと優しい味のスープの相性が良く、多くの人に愛されています。
とてもシンプルなうどんですが、うどんといえば「きつね」をイメージするほど定番で、食べやすいことも人気の理由のひとつです。
2位 天ぷらうどん

うどんに天ぷらをトッピングした「天ぷらうどん」が2位です。
天ぷらはえび天やかき揚げが定番ですが、ナスやカボチャ、ゴボウ、オクラなどの野菜天、とり天、磯辺揚げ、イカ天、あなご天など、地域やお店によってさまざまです。
天ぷらとうどんのスープの相性が良くてボリュームがあり、見た目も豪華なので人気があります。
3位 カレーうどん

うどんにカレーをかけた「カレーうどん」が3位です。
和風だしで作ったカレーとうどんの相性がとても良いです。
カレーが大好きだという人も多く、ご家庭でも残ったカレーをリメイクして手軽に作ることができるので人気があります。
4位 肉うどん

甘辛く煮た肉をトッピングした「肉うどん」が4位です。
肉は、牛肉、豚肉、鶏肉など、地域やお店によって様々です。
甘辛い肉とうどんのスープの相性が良く、肉汁とうどんのスープが交わるとさらに美味しいと感じる人が多く人気があります。
5位 鍋焼きうどん

一人用の小鍋またはアルミ鍋にうどんと出汁を入れ、椎茸、かまぼこ、油揚げ、天ぷら、生卵などをトッピングして煮た「鍋焼きうどん」が5位です。
トッピングする具は他にも、牛肉、鶏肉、豚肉、つくね、白菜、ネギ、人参、ゴボウなど、地域やお店によって様々です。
鍋でうどんを煮込んでいるのでスープがうどんに染み、いろいろな食材を一緒に食べることができるので人気です。
熱々で提供されるので、特に寒い季節は食べたくなる人が多いようです。

いかがでしたでしょうか?
うどんの誕生がいつなのか、正確なことはわからないのですね。
讃岐うどんがとても有名なので、発祥の地も讃岐なのかと思っていたのですが・・・福岡県には「饂飩蕎麦発祥之地碑」があるということで、うどん発祥の地は福岡県という方も多いようです。
うどんはご家庭でも簡単に調理することができ、その調理方法もバリエーションが豊富です。
オリジナルのうどんの食べ方を研究するのも、楽しいかもしれませんね。
関連:【日本三大!】花火、夜景、祭り、温泉、うどん、庭園、がっかり、桜、滝など
関連:そばの種類とは?更科、田舎、藪、砂場、十割、二八の意味って何?
関連:「ざるそば」「もりそば」「せいろそば」の違いとは?味?見た目?
関連:そうめんやひやむぎにピンクや緑色の色付きの麺が入っているのはなぜ?

コメント