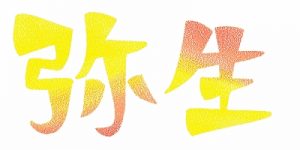
「弥生」というと、何月のことかわかりますか?
昔の日本人は、季節に合った言葉を月の名前につけていたようです。
「弥生」という言葉の意味や由来、語源などを知ると、その季節の風景が想像できるかもしれません。
今回は、「弥生」についてご紹介します。
弥生って何月?読み方は?
弥生は「3月」のことです。
読み方は「やよい」です。
もともと弥生は旧暦の3月を指す言葉でした。
現在は、旧暦3月=新暦3月と考え、弥生を新暦の3月の別名(異名・異称)として使用しています。
しかし、旧暦は太陰太陽暦といって月の満ち欠けを基準とした暦を使用していたため、太陽の動きを基準とした新暦(太陽暦)に単純に当てはまるわけではありません。
旧暦の3月を新暦に換算すると一ヶ月ほどズレが生じ3月下旬から5月上旬ごろになります。
関連:旧暦と新暦で日付がずれるのはなぜ?旧暦と新暦での四季(春夏秋冬)の期間の違い
弥生の意味と由来、語源とは?

「弥生」の
「弥」は「いよいよ・ますます」
「生」は「草木が生い茂る」
という意味があります。
つまり、「弥生」は冬が終わって草木が芽吹き、生い茂る季節を表しています。
また、「弥生」の語源は、
「木草弥や生ひ茂る月(きくさいやおいしげるつき)」
が短くなって
「弥生(いやおい)」
になり、さらに変化して
「やよい」
になったという説が有力とされています。
弥生の別名、異名、異称は何?
それでは3月(弥生)の別名、異名、異称を見ていきましょう。
晩春(くれのはる・ばんしゅん)
「春の最後の月」という意味があります。
旧暦の季節の分け方は、以下の通りになります。
1月・2月・3月が「春」
4月・5月・6月が「夏」
7月・8月・9月が「秋」
10月・11月・12月が「冬」
3月は春の最後の月にあたります。
雛月(ひいなつき)
3月3日雛祭りを含む月という意味があります。
桃月(とうづき)
桃の花が咲く月という意味があります。
花惜月(はなおしみづき)
春の花が散る季節でもあり、花を惜しむ月という意味があります。
花つ月(はなつづき)
花の見ごろが続く季節という意味があります。
花見月(はなみづき)
3月は桜が咲く季節で、お花見の季節という意味があります。
他にも、意味や由来は定かではありませんが弥生の異名はたくさんあります。
●季春(きしゅん)
●五陽(ごよう)
●禊月(けいげつ・けつげつ)
●発陳(はっちん)
●称月(しょうげつ)
●残景(ざんけい)
●病月(へいげつ・びょうげつ)
●緑秀(りょくしゅう)
●餞春(せんしゅん)
●宿月(しゅくげつ)
●桐春(とうしゅん)
●竹秋(ちくしゅう)

「弥生」がどのような月なのかわかりましたね。
「弥生」というと「弥生時代」を思い浮かべるかもしれません。
「弥生時代」は、東京府本郷区向ヶ岡弥生町(現在の東京都文京区弥生)の貝塚で土器(弥生土器)が発見されたことに由来しているそうです。
「弥生時代」と「3月」は関係がないんですね。
関連:【月の異名の意味と由来】睦月・如月・弥生・皐月・水無月・文月・葉月・長月・神無月・霜月・師走

コメント