
鬼といえば、赤鬼と青鬼が多いような気がするのですが・・・実は、ほかに黄鬼、緑鬼、黒鬼などがいます。
なぜ、赤、青、黄、緑、黒と色が違うのでしょうか?
今回は赤鬼、青鬼、黄鬼、緑鬼、黒鬼の色の違いと意味についてわかりやすく解説します。
鬼ってなに?

鬼は、「隠(おん・おぬ)」が語源といわれています。
「隠」は「この世のものではない、見えない存在」という意味があり、人の力を超えるもの、人に災いをもたらすものとされています。
姿かたちは人間のようですが、頭に角が生え、体が大きく、怪力で、「恐ろしいもの」というイメージで描かれることが多いです。
鬼の色の違いと意味とは?
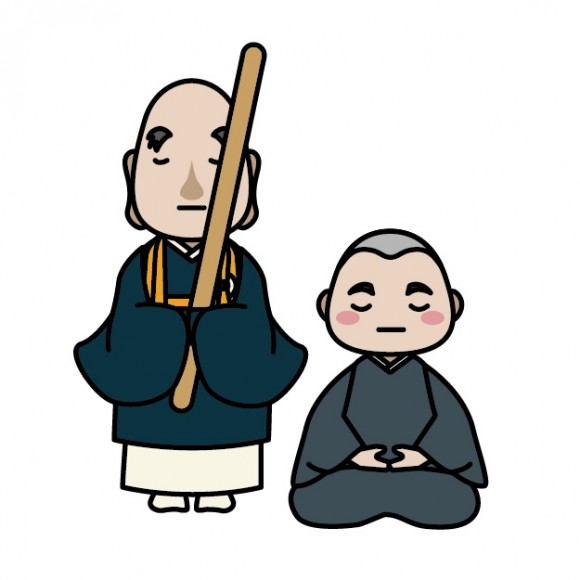
鬼の色の意味は、仏教に由来します。
仏教では「五蓋(ごがい)」という言葉があります。
「五蓋」は、仏教の瞑想修行を邪魔する5つの煩悩の総称で、
・貪欲(とんよく)
・瞋恚(しんに)
・掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)
・惛沈(こんちん)・睡眠(すいみん)
・疑(ぎ)
があります。
5つの煩悩が赤鬼、青鬼、黄鬼、緑鬼、黒鬼に当てはめられいます。
そのため、節分の豆まきのときには自分が打ち勝ちたい煩悩の色の鬼に豆を投げると良いといわれています。

それでは、それぞれの鬼の色の意味について見ていきましょう。
赤鬼

赤鬼は五蓋の「貪欲(とんよく)」に当てはめられます。
欲望や渇望など強い欲望を表し、すべての悪の象徴です。
すべての悪の象徴とされる赤鬼に豆をぶつけると、自分の中の悪い心が取り除かれるといわれています。
青鬼

青鬼は五蓋の「瞋恚(しんに)」に当てはめられます。
悪意や憎しみ、怒りなどの象徴です。
悪意や憎しみ、怒りなどは貧相で欲深い心を表しているので、青鬼に豆をぶつけることでそれらを取り除き、福徳に恵まれるといわれています。
黄鬼(白鬼)

黄鬼は五蓋の「掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)」に当てはめられます。
心の動揺や後悔の象徴です。
黄鬼に豆をぶつけることで、過去の後悔から解放され、自己中心的な甘い考えを取り除き、公平な判断ができるようになるといわれています。
また、黄鬼ではなく「白鬼」とされることもあります。
緑鬼

緑鬼は五蓋の「惛沈(こんちん)・睡眠(すいみん)」に当てはめられます。
倦怠、眠気、不健康の象徴です。
沈んだ心、やる気・気力がない、ダラダラしてしまう・・・そういう自身の不摂生を反省しながら緑鬼に豆をぶつけることで、健康的で規則正しい生活を心がけることができます。
黒鬼

黒鬼は五蓋の「疑(ぎ)」に当てはめられます。
疑心暗鬼の象徴です。
黒鬼に豆をぶつけることで、卑しい気持ちを追い払い、心の平穏を願います。 
5つの煩悩を表す色が鬼に当てはめられていることがわかりましたね。
これまでは鬼の色を特に気にすることなく豆まきをしていた方も、今後は是非、自分が打ち勝ちたい煩悩の色の鬼に豆をぶつけてみてはいかがでしょうか?
お子さんと一緒に鬼のお面を手作りする方は、その意味を話しながら色を選ぶと楽しいかもしれませんね。
関連:節分の由来や意味とは?柊鰯って何?恵方巻きはなぜ食べる?
関連:節分に豆まきをする由来や意味とは?食べる豆の数はいくつ?
関連:秋田県のなまはげの由来とは?赤と青の違いと包丁と桶を持っている理由
関連:青龍・黒龍・白龍・赤龍・朱龍・黄龍・金龍・銀龍の色の種類と意味とは?龍と竜と辰の違い

コメント