
長寿祝いでよく見聞きするのは「還暦」お祝い」ではないでしょうか?
60歳になったお祝いに、赤いちゃんちゃんこや赤い帽子を着用することから印象に残っている人も多いかもしれません。
ですが、還暦以外にも長寿祝いはいろいろあります。
今回は、長寿祝いとその年齢、読み方、意味、お祝い色についてわかりやすく解説します。
長寿祝いとは?
「長寿祝い」は、文字通り長寿をお祝いすることです。
「賀寿(がじゅ)」
「年祝(としいわい)」
ともいわれます。
奈良時代(710年~794年ごろ)に中国から伝わってきたとされ、そのころは40歳、50歳、60歳と、10歳ごとにお祝いをしていたそうです。
室町時代(1336年~1573年ごろ)の末期ごろに、現在の形になりました。
長寿祝いは、還暦は満年齢でお祝いしますが、それ以外は数え年でお祝いします。
数え年とは、0歳の一年間が存在せず、生まれたその時が1歳で、お正月が来るとひとつ年齢を重ねる数え方です。
たとえば、2024年9月に生まれた赤ちゃんはその時点で1歳です。そして、2025年1月になると2歳になります。
以下のリンク先に今年の数え年を一覧にまとめましたのでご活用くださいね。
関連:2025年(令和7年)数え年早見表!生まれた年から調べる!
長寿祝いはいつやるの?

先ほど還暦以外の長寿祝いは数え年でお祝いすると書きましたが、最近は、満年齢でお祝いする方も増えてきています。
例えば、古希は数え年で70歳(満69歳)のときにお祝いしますが、満年齢で70歳のときにお祝いするということです。
私たちは普段の生活で、満年齢を使って生活していますから、数え年という昔の風習にこだわらない人が増えてきているそうです。
昔の風習を大事にする人のお祝いであれば数え年で、あまり気にしない人のお祝いであれば満年齢で行うなど臨機応変に使い分けましょう。
また、お祝いの日にちは、長寿を迎える方のお誕生日に行ってもいいですし、その年の、お正月やお盆、敬老の日など、人が集まりやすい日を選んでもいいです。
ご家族やごきょうだいで相談して最適な日を決めるといいですね。
長寿祝い一覧
それでは、長寿祝いを年齢順に紹介します。
年齢は、すべて数え年で紹介しています。
還暦は他の長寿のお祝いと違い満60歳でお祝いします。
還暦 数え年61歳(満60歳)
読み方:かんれき
お祝い色:赤・朱
干支(十干十二支・じっかんじゅうにし)が60年で一巡し、生まれた年の干支に戻ることから暦が還るという意味があります。
還暦には赤ちゃんに還るという意味もあり、赤いちゃんちゃんこや赤い帽子、赤い座布団などを着用します。
赤には魔除けの意味があるため、昔は産着に赤色が使われていました。
緑寿 66歳
読み方:ろくじゅ
お祝い色:緑
2002年に日本百貨店協会が提唱しました。
77歳、88歳、99歳の賀寿はあるのに、66歳の賀寿がなかったので作られたようです。
「緑(みどり)」は「ろく」と読めることから「緑々寿(66寿)」としたもので、略して「緑寿」となりました。
古希 70歳

読み方:こき
お祝い色:紫
中国の詩人、杜甫(とほ)の「人生七十 古来稀なり」からきています。
当時、70歳は稀(まれ)な年齢であるという意味があります。
喜寿 77歳

読み方:きじゅ
お祝い色:紫

「喜」という漢字を草書体で書くと、七を3つ書き、それが七十七と読めることから喜寿となりました。
傘寿 80歳
読み方:さんじゅ
お祝い色:黄(金茶)・紫
「傘」の略字「仐」が八十に見えることから傘寿となりました。
傘寿のお祝い色は、黄と紫どちらでもいいです。
半寿 81歳
読み方:はんじゅ
お祝い色:黄(金茶)
「半」の字を分解すると八十一に見えることから半寿となりました。
また、将棋盤のマス目が9×9=81あることから「盤寿(ばんじゅ)」とも言います。
米寿 88歳

読み方:べいじゅ
お祝い色:黄(金茶)
「米」の字を分解すると八十八に見えることから米寿となりました。
別名「米の祝い」とも言われ、日本が米文化であることと、末広がりの八の字をふたつ重ねることでおめでたいと言われています。
卒寿 90歳

読み方:そつじゅ
お祝い色:紫・白
「卒」の略字「卆」が九十に見えることから卒寿となりました。
傘寿のお祝い色は、紫と白どちらでもいいです。
白寿 99歳

読み方:はくじゅ
お祝い色:白
「百」から「一」を取ると「白」になり、数も100から1を引いて99になります。
また、あと1歳で100歳になるという意味も込められています。
百寿 100歳
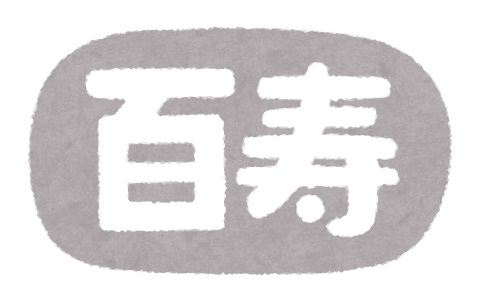
読み方:ひゃくじゅ・ももじゅ
お祝い色:白
100年は一世紀を表すことから「紀寿(きじゅ)」といいます。
ほかに、「百賀(ひゃくが・ももが)」と言ったり、寿命を上中下の三段階ににわけたときに100歳は最も上位であることから「上寿(じょうじゅ)」とも言います。
茶寿 108歳
読み方:ちゃじゅ
お祝い色:なし
「茶」の字を分解すると十十八十八に分かれ、20+88=108になります。
他に「不枠(ふわく)」ともいいます。
「枠」の字を分解すると十八九十に分かれ、10+8+90=108になります。
皇寿 111歳

読み方:こうじゅ
お祝い色:なし
「皇」の字を分解すると白一十一に分かれます。
「白」は百から一を引いたものと考え99で、99+1+10+1=111になります。
また、111が「川」の字と読めるため「川寿(せんじゅ)」ともいいます。
天寿 118歳
読み方:てんじゅ
祝い色:なし
「天」の字が一一八にに分かれ、118になります。
頑寿 119歳
読み方:がんじゅ
祝い色:なし
「頑」の字を分解すると二八百一八に分かれ、2+8+100+1+8=119になります。
大還暦 数え年121歳(満120歳)

読み方:だいかんれき
祝い色:なし
2度目の還暦ということで、大還暦と呼ばれています。
いかがでしたでしょうか?
奈良時代に伝わってきた長寿祝いが現在も続いているということは、日本人の心に長寿の方を敬い、お祝いする気持ちが受け継がれているということだと思います。
素晴らしい日本の風習をこれからも受け継いでいきたいですね。
関連:年齢の名称・異称・別名・別称。弱冠・不惑・三十路・還暦は何歳?
関連:【結婚記念日一覧】結婚記念日の数え方・呼び方・意味・英語表現とは?プレゼントは何を贈る?
関連:満年齢と数え年の違いとは?なぜ満年齢と数え年があるの?
関連:満年齢・数え年どっちでお祝いする?還暦・厄年・七五三・長寿のお祝い

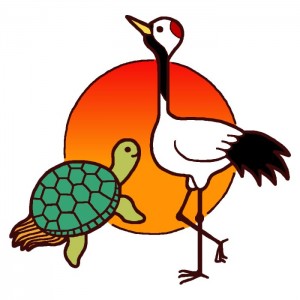


コメント
コメント一覧 (2件)
日本では、90歳の祝いとして、卒寿という言葉を用いています。
字面からすると、卒=卆=90です。
しかし、漢字の意味を考えると大変なことになります。
卒寿は、寿をこれで(卒)終わりましょうという意味になります。
形を見て心を見ず。
90歳のお祝い言葉として、「粋寿」はいかがでしょうか。お米を伴った豊かな九十歳です。
コメントありがとうございます。「粋寿」とてもいいですね!