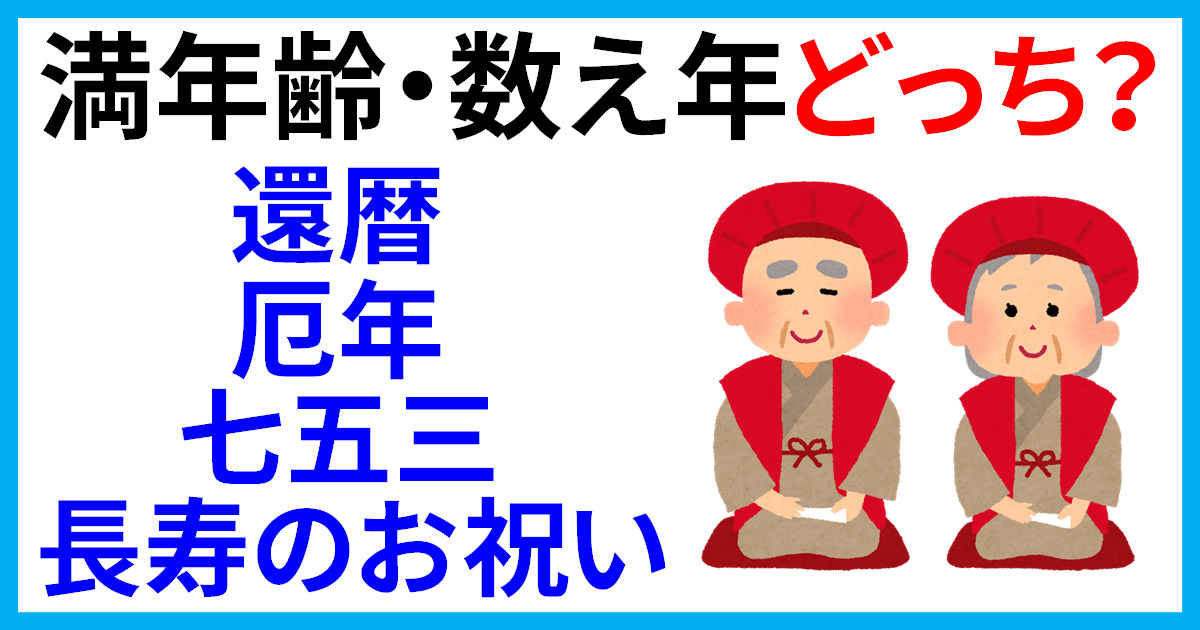
私たちは普段、年齢を「満年齢」で数えますが、「数え年」という数え方もあります。
現在はあまり使うことのない「数え年」ですが、今でも「数え年」で行われるイベントがあります。
還暦・厄年・七五三・長寿のお祝いは「満年齢」と「数え年」どちらなのでしょうか?
満年齢とは?
「満年齢」とは、生まれた時を0歳とし、誕生日を迎えるごとにひとつ年齢が増える数え方のことです。
生まれた一年後の誕生日に、1歳になります。
「満20歳」などと表記します。
数え年とは?
「数え年」とは、生まれたその日にすでに1歳で、元日(1月1日)に年を重ねるという数え方です。
例えば、2024年4月10日に生まれた人は、その時点で1歳です。
そして、2025年1月1日に2歳になります。
数え年で自分が今何歳なのか知りたいときは、
「元日から誕生日前までは満年齢+2歳」
「誕生日当日から12月31日までは満年齢+1歳」
と計算してみましょう。
以下のリンク先に今年の数え年を一覧にまとめましたのでご活用くださいね。
関連:2025年(令和7年)数え年早見表!生まれた年から調べる!
還暦・厄年・七五三・長寿のお祝いは満年齢・数え年どっち?
現在は満年齢をメインに生活をしている私たちですが、人生の節目に行われるイベントは、満年齢と数え年のどちらなのでしょう?
ひとつずつみていきましょう!
還暦

還暦は、 「満年齢」の60歳でお祝いします。
還暦は、干支(十干十二支・じっかんじゅうにし)が60年一巡し、生まれた年の干支に戻ることから暦が還るという意味があります。
関連:年齢の名称・異称・別名・別称。弱冠・不惑・三十路・還暦は何歳?
関連:【2025年】今年の干支は巳(へび)!干支の順番の由来と覚え方
厄年

厄年は、 一般的には「数え年」です。
男性は25歳、42歳、61歳
女性は19歳、33歳、37歳、61歳
が厄年です。
厄年の年齢を「本厄(ほんやく)」といいます。
そして、
前の年を「前厄(まえやく)」
後の年を「後厄(あとやく)」
といい、本厄と同じように気を付けなければならない年齢とされています。
厄払いは一般的に「前厄」「本厄」「後厄」の3年続けて行います。
厄払いも「数え年」で行いますが、神社やお寺によっては 「満年齢」で行うところもありますので、事前に確認をしておくと良いでしょう。
関連:厄年の意味と男女の年齢。厄払いはいつ行けばいい?効果や祈祷料、服装について
七五三

七五三は、 一般的に「数え年」です。
しかし、 最近は「満年齢」で七五三を行うご家庭も増えています。
男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳で行います。
関連:七五三はなぜ7歳・5歳・3歳にお参りするの?男の子と女の子で年齢が違う理由
長寿のお祝い
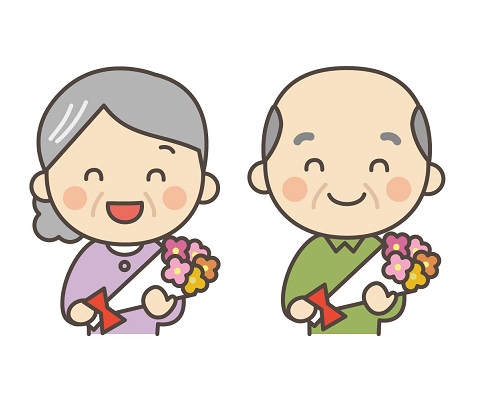
還暦は「満年齢」でしたが、 それ以外の長寿のお祝いは「数え年」で行います。
数えば、
70歳の「古希(こき)」
77歳の「喜寿(きじゅ)」
88歳の「米寿(べいじゅ)」
など、長寿のお祝いはたくさんあります。
一般的に「数え年」でお祝いをしますが、 最近は「満年齢」でお祝いをするご家庭も増えているようです。
関連:【長寿祝い一覧】年齢・読み方・意味・お祝い色とは?還暦/古希/喜寿/傘寿など
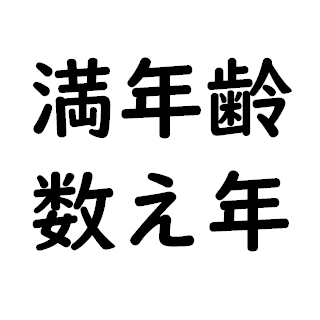
いかがでしたでしょうか?
日本にはなぜ満年齢と数え年があるのかわかりましたね。
還暦だけは「満年齢の60歳」で行いますが、厄年、七五三、長寿のお祝いは「数え年」で行うのですね。
しかし、神社やお寺、ご家庭によって異なるので、事前に確認しておくと良いですね。
もともとは「数え年」で行っていたことも、現在は「満年齢でもOK」という考え方になっていますから、「数え年」はいつか消えて行くのかもしれません。
いつか消えていく可能性があっても、古くからの伝統として受け継いでいけると良いですね。
関連:満年齢と数え年の違いとは?なぜ満年齢と数え年があるの?

コメント