
日本には、桃の節句や端午の節句など季節ごとに節目となる行事がありますが、これらの節句の中の一つに「重陽の節句」というものがあります。
江戸時代には、五節句の最後をしめくくる行事としてもっとも盛大に行われていましたが、今は影を潜めている重陽の節句。
この記事では、重陽の節句の読み方と意味、行事食や、菊の花を飾る理由についてわかりやすく解説します。
重陽の節句の読み方と意味とは?
読み方は「ちょうようのせっく」です。
重陽の節句は「五節句(ごせっく)」の一つです。
五節句の「節」には季節の節目や変わり目という意味があり、「節句(せっく)」は季節の節目に五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄などを祈り、神様へお供え物をしたり、邪気を祓ったりする行事のことをいいます。

また、季節の節目に神様にお供えすることから「節供(せっく)」と書くこともあります。
五節句は、唐の時代(618年~907年)の中国ではすでに制度として成立しており、日本には奈良時代(710年~794年)に伝わって来ました。
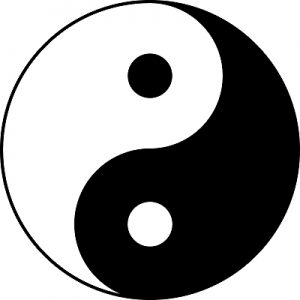
中国の陰陽五行思想では、奇数は陽、偶数はその逆で陰と考えられていました。
奇数の月と奇数の日は、奇数(陽)が重なって偶数(陰)になるため縁起が悪い日とされました。
それを避けるために季節ごとの旬の食べ物を食べ、生命力をもらい、その力で邪気を祓う目的で行われていた行事が五節句の由来です。
五節句は江戸時代に式日(祝日)として定められ、以下の5つの節句のことをいいます。
1月7日を「人日(じんじつ)の節句」
3月3日を「上巳(じょうし)の節句」
5月5日を「端午(たんご)の節句」
7月7日を「七夕(しちせき)の節句」
9月9日を「重陽(ちょうよう)の節句」
9月9日は数字の中でも一番大きな陽数が重なる日となるため、「重陽の節句」と呼ばれるようになりました。
2024年の重陽の節句はいつ?
2024年の重陽の節句は9月9日(月)です。
もともと重陽の節句は旧暦9月9日に行われていました。
旧暦と新暦は一ヶ月ほどのズレがあり、新暦に換算すると10月中旬ごろにあたり、そのため現在とは季節感が異なります。

長崎くんち
九州北部などでは、重陽の節句とあわせて「お九日(くんち)」という秋の収穫祭が、10月や11月頃に盛大に祝われています。
「お九日」の語源は、重陽の節句の「9日」を方言で「くんち」といったことから来ているといわれています。
関連:九州のお祭り「くんち」の語源や意味、由来とは?日本三大くんちとは?
菊の花を飾るのはなぜ?

五節句は、その季節にまつわる植物の名前で呼ばれることがあります。
それぞれ順番に次のような別名があります。
1月7日「七草の節句」
3月3日「桃の節句」
5月5日「菖蒲(しょうぶ)の節句」
7月7日「笹の節句」
9月9日「菊の節句」
先述した通り、旧暦9月9日は新暦で10月中頃になるので、菊が最も美しい季節であることから「菊の節句」と呼ばれ、菊の花を飾ります。
重陽の節句は、新暦と旧暦の季節感のずれのため、菊の花の旬が合わなくなり次第に廃れていきました。
しかし、寿命が延びると言われていた菊を主役に据え、不老長寿や繁栄を願う行事として現在も行われています。
重陽の節句の食べ物・料理
秋の収穫祭の意味合いも持っていた為、重陽の祝い膳には秋の味覚が多く登場します。
栗ご飯

江戸時代の頃から秋の味覚の代表的な食材「栗」を使った栗ご飯を食べる風習があります。
そのため、菊の節句は別名「栗の節句」とも呼ばれていたそうです。
秋茄子

この時期の茄子が最も美味しい季節なので、祝い膳には焼きナスや煮浸しとして登場したようです。
また「おくんちに茄子を食べると中風にならない」とも言われていました。
中風とは、現在で言う脳血管障害の後遺症の事をいい、半身不随やまひ、手足のしびれなどの症状のことを言います。
食用菊

重陽の節句の主役でもある菊ですが、食用菊をおひたしやお吸い物にして食していたようです。
その他

その他にもお膳と一緒に「菊酒」を嗜むなど、節句の主役である菊を使った楽しみ方がたくさんあります。
「菊湯」に入ったり、「菊枕」で眠り邪気払いをしたり、前日のうちに菊の花に綿をかぶせておき、翌朝に菊の香りや露を含んだ綿で身を清め長寿を願うという「菊の着せ綿」という事も行っていたそうです。
後の雛とは?

また、重陽の節句の催しとして密かに行われている風習に「後の雛(のちのひな)」というものがあります。
これは江戸時代の頃に庶民の間で広まった風習で、桃の節句に飾った雛人形を半年後の重陽の節句に虫干しも兼ねて飾り、健康や長寿、厄除けを願っていたというものです。
桃の節句では桃の花を添え子供の成長を祝いますが、菊の節句では菊の花を添える為、華やかな中にも大人の落ち着きのある菊の雰囲気から「大人の雛祭り」とも言われています。

「重陽の節句」は、今では影が薄くなってしまったの風習ですが、様々な思いが込められた日本の行事の一つです。
季節の節目を大切にし、今年は雛人形を眺めながら菊酒を嗜むなどちょっと大人の楽しみ方をしてみたいですね。
関連:行事食の意味と由来とは?春夏秋冬(1月~12月)季節の食べ物と旬の食材一覧
関連:陰陽五行説を簡単にわかりやすく解説します!陰陽五行説の意味や由来とは?

コメント