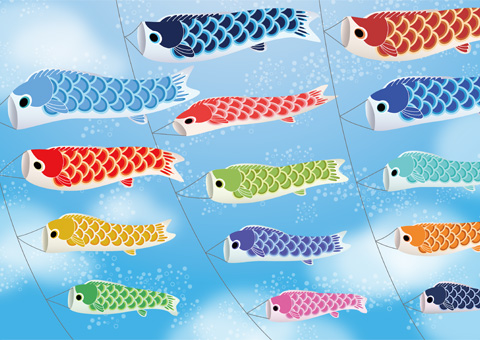
「五節句」という言葉をご存知ですか?
ご存知ではなくても、桃の節句(お雛祭り)や端午の節句(子供の日)と言えば知っている方がほとんどだと思います。
この2つの節句を含めた一年間に五つある節句を「五節句」といいます。
今回は五節句の意味や由来、それぞれの別名と食べ物などについてわかりやすく解説します。
五節句の意味とは?五節句はいつ?

「五節句」の読み方は「ごせっく」です。
五節句の「節」には、季節の変わり目・節目という意味があります。
「節句(せっく)」は、季節の節目に五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄などを祈り、神様へお供え物をしたり、邪気を祓ったりする行事のことをいいます。
また、季節の節目に神様にお供えすることから「節供(せっく)」と書かれることもあります。
五節句は以下のとおりです。
●1月7日 人日(じんじつ)の節句
●3月3日 上巳(じょうし)の節句
●5月5日 端午(たんご)の節句
●7月7日 七夕(しちせき)の節句
●9月9日 重陽(ちょうよう)の節句
五節句の由来は?
五節句は、唐の時代(618年~907年)に中国から伝わってきたものです。
中国の陰陽五行思想では、
1,3,5,7,9 の奇数は「陽」で縁起が良く
2,4,6,8 の偶数は「陰」で縁起が悪い
と考えられていました。
しかし、奇数の月と奇数の日は奇数が連なるのでおめでたい反面、奇数(陽)が重なって偶数(陰)になるため縁起が悪い日とされました。
そのため、季節ごとの旬の食べ物を食べ生命力をもらい、その力で邪気を祓う目的で行われていた行事が「五節句」の由来です。

七草粥
1月1日は元日なので別格とされ、1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の5つが「五節句」となっています。
中国の唐の時代にはすでに制度として整えられており、日本へは奈良時代(710年~794年)に伝わって宮中行事になったと言われています。
江戸時代(1603年~1868年)の初期に、幕府が五節句を公的な行事・祝日として定めました。
初めは大名や旗本などがお祝いをしていましたが、やがて一般の人々にまで広まっていき、農作業の節目で行われていた古来からの風習が融合し、現在のような形になったと考えられています。
明治5年(1872年)に旧暦から新暦に改暦されるときに五節句の制度は廃止されましたが、年中行事(毎年決まった時期に行われる行事)として定着しています。

「11月11日はなぜ五節句ではないの?」という疑問も生まれるかと思います。
まず、日本に伝わってくる以前から中国でも11月11日は節句ではありませんでした。
なぜ、中国で11月11日が節句にならなかったのか定かではありませんが、陰陽五行思想では最大の陽の数字である9が重なる9月9日の「重陽の節句」が最も縁起が良く、その年最後の節句と考えられていたようです。
日本にも季節の変わり目の「節句」は数多くあったので、もしかすると現在まで伝わっていないだけで「11月11日」になにかしらの行事が行われていたかもしれませんが、江戸幕府が定めた公的な行事・祝日として定めた「五節句」の中に11月11日は含まれていません。
五節句の別名と食べ物
五つの節句の日付と別名、食べ物は次のようになります。
1月7日 人日(じんじつ)の節句

春の七草
別名:「七草の節句」
行事食:七草粥
七草粥を食べて一年の豊作と、無病息災を願います。
関連:人日の節句の意味とは?七草粥を食べるのはなぜ?春の七草の覚え方
3月3日 上巳(じょうし)の節句

別名:「桃の節句」
行事食:ひなあられ、菱餅、はまぐり、白酒、ちらし寿司
お雛祭りの日で、女の子の誕生と成長を祝う日です。
関連:上巳の節句(桃の節句)って何?ひな祭りの由来とは?どんな食べ物を食べるの?
5月5日 端午(たんご)の節句

菖蒲
別名:「菖蒲(しょうぶ)の節句」
行事食:柏餅、粽(ちまき)
子供の日で、男の子の誕生と成長を祝う日です。
関連:【端午の節句】意味と由来とは?何をする日?「こどもの日」との違い
関連:【地域別】端午の節句の食べ物・行事食とは?なぜ柏餅、ちまきを食べる?
関連:【2025年】菖蒲湯に入るのはいつ?由来と意味とは?効能や、やり方、頭に巻くのはなぜ?
7月7日 七夕(しちせき)の節句

別名:「笹の節句」
行事食:そうめん
短冊に願いを込めて笹に飾ると願いが叶うといわれています。
関連:【2025年】七夕の節句の読み方と意味、歴史とは?別名は?食べ物はそうめん?
9月9日 重陽(ちょうよう)の節句
別名:「菊の節句」
行事食:栗ご飯、食用菊、秋茄子
一般的には馴染みがない節句ですが、宮中や寺院では菊を鑑賞する行事が行われています。
関連:【2025年】「重陽の節句」の読み方と意味とは?食べ物は何?菊の花を飾るのはなぜ?

明治6年(1873年)に旧暦から新暦に改暦されたときに五節句の日付はそのまま新暦の日付に引き継がれました。
旧暦と新暦の間にはおよそ1か月のずれがあるため、日付は一緒でも季節感にずれが生じてしまいます。
例えば、1月7日の人日の節句で食べる七草粥ですが、現在の1月7日に春の七草が自然に生えていることはありませんよね。
現在の1月7日を旧暦の日付に当てはめるとだいたい2月初旬から中旬ごろになりますから、春の七草を自然の中に見つけることができます。
また同様に、9月9日の「重陽の節句」は別名「菊の節句」ですが、旧暦だと現在の10月初旬から中旬ごろなので菊の花が美しく咲き誇る時期なのです。
このように、旧暦の行事をそのままの日付で新暦に当てはめたことで季節感にずれが生じてしまい、行事食についても旬の時期とは合わなくなってしまうのです。
関連:旧暦と新暦で日付がずれるのはなぜ?旧暦と新暦での四季(春夏秋冬)の期間の違い

いかがでしたでしょうか?
日本では奈良時代から始まった五節句が時の流とともに形を変え、現在も受け継がれているのですね。
同じ節句でも違う呼び名で慣れ親しんでいるものもありますし、宮城県仙台市の七夕まつりのように大々的にお祭りをする地域もあります。
お雛祭りや子供の日は、子供のころに意味や由来はわからなくても、お祝いしてもらえることがうれしかった記憶もあるのではないでしょうか?
意味や由来を知ったら、年中行事をよりいっそう楽しめるかもしれませんね。
関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方
関連:『雑節』の読み方と意味とは?2025年の雑節の日付一覧と食べ物
関連:行事食の意味と由来とは?春夏秋冬季節の食べ物と旬の食材一覧
関連:「お盆」や「七夕」の時期が地域によって違うのはなぜ?7月と8月の地域はどこ?

コメント
コメント一覧 (2件)
五節の由来、趣旨については理解できましたが、2点、疑問が生じました。
疑問1: 11月11日は何故節句にならなかったのでしょうか?
疑問2: 元来節句の日付は旧暦で決まっていたとすれば、新暦になるでその季節は37日間ズレることになります。そうなりますと「旬の食材」の概念も少し合わなくなるように思いますが。例えば「七草粥」は11月に食べていたのでしょうか?
コメントありがとうございます。
疑問にお答える形で記事を更新いたしました。
なお、1月7日の人日の節句は新暦から旧暦にすると時期は2月初旬から中旬ごろになりますので「七草粥」はその時期に食べられていたということになります。