
5月5日は「端午の節句」です。
端午の節句の意味や由来をご存じでしょうか?
また、何をする日なのでしょうか?
5月5日は「こどもの日」でもありますが、「端午の節句」と「こどもの日」にはどのような違いがあるのでしょうか?
今回は「端午の節句」に疑問についてわかりやすく解説します。
端午の節句の意味と由来は?
読み方は「たんごのせっく」です。
「端午の節句」は毎年5月5日で、男の子の誕生と健やかな成長を祝う日です。
もともとは中国の風習でした。
中国では5月に病気が流行しやすかったことから「5月は悪月(あくげつ)」と言われており、「5月5日は5が重なるから悪月の悪日(あくにち)」とされていました。

菖蒲(しょうぶ)
そこで、病気や厄を払う薬草と考えられている菖蒲(しょうぶ)を自宅の門や玄関に飾る軒菖蒲(のきしょうぶ)をしたり、菖蒲を浸したお酒を飲んだり、菖蒲湯に入るなど厄除けや健康祈願をしていました。

また、奇数は陽、偶数は陰と考えられており、5月5日のように奇数の月と奇数の日は、奇数(陽)が重なって偶数(陰)になるため縁起が悪い日とされていました。
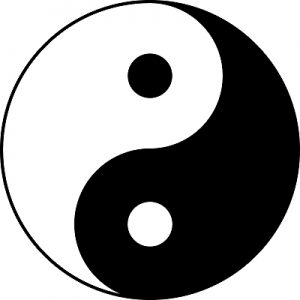
それを避けるために季節ごとの旬の食べ物を食べ生命力をもらい、その力で邪気を祓う目的で「五節句(ごせっく)」という行事が行われました。
五節句は以下のとおりです。
●1月7日(人日の節句・七草の節句)
●3月3日(上巳の節句・桃の節句)
●5月5日(端午の節句・菖蒲の節句)
●7月7日(七夕の節句・笹の節句)
●9月9日(重陽の節句・菊の節句)
このように、5月5日の「端午の節句」は五節句のひとつになっています。
関連:『五節句』はいつ?意味や由来とは?それぞれの別名と食べ物
「端午」は「端」は物のはし、つまり「始まり・最初」という意味があり、もともとは「月初めの午(うま・十二支のひとつ)の日」という意味でした。
その後、「午(うま)」は「午(ご)」と読むことから「五(ご)」に通じるので、5が重なる5月5日を端午の節句としたのがはじまりといわれています。
十二支の詳細についての詳細は以下をご覧ください。
関連:【2025年】今年の干支は巳(へび)!干支の順番の由来と覚え方
日本に端午の節句の風習が伝わってきたのは奈良時代のころです。
このころ日本では、田植えの時期である5月になると、五穀豊穣を祈願するために若い女性たちが神社に籠って田植えの前に穢(けが)れを祓う「五月忌み(さつきいみ)」という風習がありました。
そして、穢れを祓う五月忌みの風習と、中国から伝来した端午の節句の厄除けや邪気を払う風習が結びいたと考えられています。

鎌倉時代(1185年~1333年)になると、武道を重んじるという意味のある「尚武(しょうぶ)」と、厄除けに使っている「菖蒲(しょうぶ)」が同じ読み方であることから武士の間では縁起が良いと盛んに行われるようになり、端午の節句は別名「菖蒲の節句」とも呼ばれるようになりました。
端午の節句は、江戸時代になると幕府が年中行事として定られ、庶民にも広まっていきます。

奈良時代には女性が行うものでしたが、武士の間で縁起が良いものとされ、時の流れとともに変化し、江戸時代には男の子の誕生と成長を祝う節句として定着したのです。
端午の節句は何をする日?

端午の節句は、鯉のぼりや五月人形などを飾り、柏餅やちまきを食べ、男の子の誕生を祝い、健やかな成長を祈るのが一般的です。
家族写真を撮ったり、豪華な食事をするご家庭もあります。
また、無病息災を願って菖蒲湯に入る風習もあります。

菖蒲湯
菖蒲湯についての詳細は以下をご覧ください。
関連:【2025年】菖蒲湯に入るのはいつ?由来と意味とは?効能や、やり方、頭に巻くのはなぜ?
「端午の節句」と「こどもの日」の違いとは?
「端午の節句」と「こどもの日」は同じ5月5日です。
「こどもの日」は昭和23年(1948年)に制定された祝日ですが、その際、もともと「端午の節句」の日であった5月5日を希望する声が多かったためこの日に決まったといわれています。
理由としては、5月5日の端午の節句が男の子を祝う日だったためです。
また、定かではありませんが、北海道や東北では5月5日よりも前の日付だと寒いとの反対が多かったためこの日に決まったともいわれています。
「端午の節句」と「こどもの日」は同じ日なので、どちらもこどものための行事と考えてしまいますが、正確には以下のような違いがあります。
端午の節句
奈良時代に中国から日本に伝わった風習で、男の子の誕生や成長を祝う「男の子の節句」です。
ちなみに「女の子の節句」は3月3日の「上巳の節句(桃の節句)」です。
上巳の節句についての詳細は以下をご覧ください。
関連:【2025年】上巳の節句(桃の節句)とひな祭りの由来とは?どんな食べ物があるの?
こどもの日
昭和23年(1948年)に制定された国民の祝日です。
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨としており、「こども(男の子と女の子)とお母さんの日」です。
「こども」とひらがな表記なのは、当事者である子どもにわかりやすくするためといわれています。
このような違いがあるのですね。
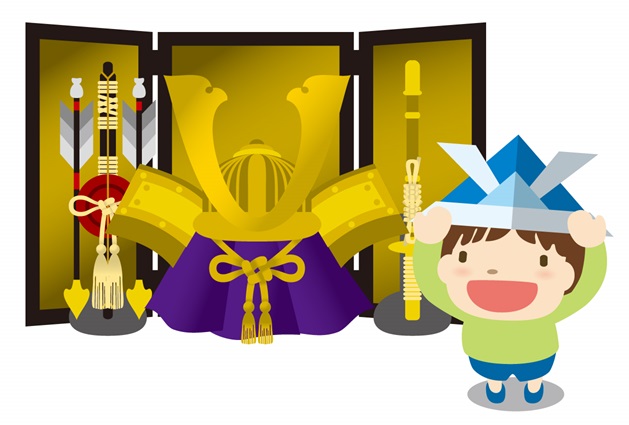
「端午の節句」がどのような日かわかりましたね。
「端午の節句」は「こどもの日」と同じ5月5日なので祝日です。
「端午の節句」と「こどもの日」は行事の内容が違いますが、どちらも子どもたちのこれからの幸せを願う気持ちがあると思います。
5月5日は、日本中で子どもたちの幸せな笑顔を見ることができると良いですね!
関連:五月人形を飾る意味とは?鎧や兜・金太郎・張子の虎・弓矢と太刀など
関連:【2025年】五月人形はいつ出す?飾る時期はいつからいつまで?
関連:「鯉のぼり」飾る時期と片付ける時期はいつ?吹き流しの意味とは?
関連:菖蒲湯に入るのはいつからいつまで?どんな意味や効能があるの?菖蒲を頭に巻くのはなぜ?

コメント