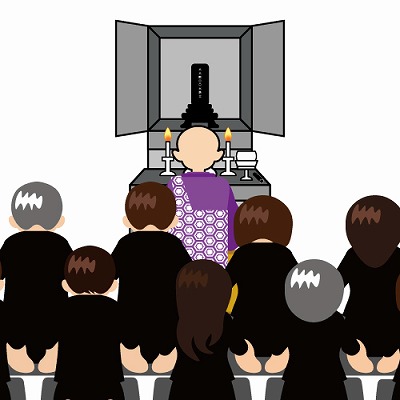
日本人の多くは、仏教徒ですね。
仏教の宗派はさまざまですが、ほとんどのご家庭ではお寺にお墓や納骨堂があり、お仏壇が自宅にある方もいらっしゃることでしょう。
誰かが亡くなれば、お寺に連絡をして住職に来ていただきます。
もしかしたら、この時初めて、
「法事(ほうじ)」
「法要(ほうよう)」
「初七日(しょなのか)」
「四十九日(しじゅうくにち)」
などの言葉を耳にする方もいらっしゃるかもしれません。
もしもの時に慌てなくていいよう、それぞれの意味をご紹介します。
法要とは?法事との違いとは?
法要と法事は同じこと・・・と思っている方もいらっしゃるようですが、厳密には違います。
法要とは?
「法要」とは遺族が故人を偲び、冥福を祈るために行う「追善供養(ついぜんくよう)」のことです。
法要を営むことによって、それが故人の善行となり、極楽浄土に往生できるといわれています。
そのため遺族は、故人が極楽浄土へ行けるよう、法要を行い追善供養をするのです。
ただし、浄土真宗ではご臨終と同時に極楽往生すると考えられており、法要は「故人を偲び仏法(仏に成る方法)に接するため」に営まれます。
法事とは?
「法事」とは、法要と、その後の会食までのことをいいます。
法事の中に法要も含まれているため、同じことと思ってしまう方が多いのかもしれませんね。
忌日・年忌法要とは?
仏教では、人が亡くなってから一定の日数、年数で法要を行います。
これを「忌日法要(きびほうよう)」「年忌法要(ねんきほうよう)」といいます。
忌日法要
忌日法要は、命日(めいにち・亡くなった日)を含めた日数で数え、以下のよう法要を行います。
●7日目「初七日(しょなのか)」
●14日目「二七日(ふたなのか)」
●21日目「三七日(みなのか)」
●28日目「四七日(よなのか)」
●35日目「五七日(いつなのか)」
●42日目に「六七日(むなのか)」
●49日目に「七七日(なななのか)」「四十九日(しじゅうくにち)」
●100日目に「百か日(ひゃっかにち)」
初七日と四十九日以外は、遺族だけで行うことが多く、家に住職に来ていただきます。
また、百か日は四十九日と一緒に行われ省略されることもあります。
初七日と四十九日については、このあと詳しく解説します。

年忌法要
年忌法要は、以下のようになります。
●一周忌
満一年目に、遺族、親族、友人知人などで行います。
住職に読経していただき、焼香します。
四十九日法要と同規模で行われることが多く、一周忌をもって喪が明けることになります。
●三回忌
満二年目に、遺族、親族、友人知人などで行います。
住職に読経していただき、焼香します。
一周忌より規模は縮小されます。
一周忌と三周忌の詳細は以下をご覧ください。
関連:「三回忌」の法要はいつやるの?「一周忌」と「一回忌」の意味と違い
その後は
●七回忌(満六年目)
●十三回忌(満12年目)
●十七回忌(満16年目)
●二十三回忌(満22年目)
●二十七回忌(満26年目)
●三十三回忌(満32年目)
●五十回忌(満49年目)
それぞれ、遺族、親族で行います。
七回忌以降は、親族の中で同じ年に法要が行われる場合、まとめて行ってもよいとされています。
また、法要の規模は徐々に小さくしていくのが一般的で、三十三回忌か五十回忌をもって、年忌法要の終了とします。
初七日、四十九日の意味とは?

仏教では、死後は十王(じゅうおう)と呼ばれる10人の裁判官によって生前の裁きを受け、来世の行き先が決まると考えられています。
1回目~7回目までは7日ごとに裁判が行われます。
1回目が初七日、7回目が四十九日です。
以下それぞれの法要と十王、裁判の内容をご紹介します。
初七日(しょなのか・7日目)
十王:秦広王(しんこうおう)
生前の殺生について調べられます。
この世とあの世の境にある三途の川のほとりに到着する日で、この時の裁きによってどんな川(急流や緩流など)を渡るかが決まる大切な日です。
関連:三途の川の三途の意味とは?どうして六文銭が必要なの?石積みって何?
二七日(ふたなのか・14日目)
十王:初江王(しょこうおう)
生前の盗みについて調べられます。
三七日(みなのか・21日目)
十王:宋帝王(そうたいおう)
生前の不貞行為について調べられます。
四七日(よなのか・28日目)
十王:五官王(ごかんおう)
生前の悪い言動や嘘について調べられます。
五七日(いつなのか・35日目)
十王:閻魔大王(えんまだいおう)
これまでの裁判結果を踏まえて、極楽に行くのか六道(ろくどう・りくどう)に行くのか、次の行き先が決まります。
六道とは、
・天道(てんどう)
・人間道(にんげんどう)
・修羅道(しゅらどう)
・畜生道(ちくしょうどう)
・餓鬼道(がきどう)
・地獄道(じごくどう)
という、人が生まれ変わる6つの世界のことです。
六道の詳細はこちらをご覧ください。
関連:六道(天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)の意味とは?
六七日(むなのか・42日目)
十王:変成王(へんじょうおう)
閻魔大王が決めた行き先で、生まれ変わるための条件が詳しく決められます。
たとえば、閻魔大王が畜生道に決めたのなら、なんの動物で、どの地域に生まれるのかなどが決まります。
七七日(なななのか・49日目) 四十九日
十王:泰山王(たいざんおう)
これまでの裁判結果をもとに最終判決が下されます。
最終判決が下る最も大切な日とされており、遺族や親族のほか、故人と縁の深かった方を招いて法要を営み、最良の判決が下されるよう祈ります。
このようにして、多くの人は四十九日に行き先が決まり、裁判もここまでです。
四十九日に行き先が決まらなかった場合は、8回目、9回目、10回目の裁判を受けることになりなす。
百か日(ひゃっかにち・100日目)
十王:平等王(びょうどうおう)
一度下った判決の救済のための裁判です。
一周忌(いっしゅうき・1年目)
十王:都市王(としおう)
一度下った判決の救済のための裁判です。
三回忌(さんかいき・2年目)
十王:五道転輪王(ごどうてんりんおう)
一度下った判決の救済のための裁判です。
ここが最後で行き先が確定します。
十王の裁判は三回忌が最後です。
また、十王は、本来は仏の姿をしているといわれており、十王と仏は以下のように対応しています。
| 法要 | 十王 | 仏 |
| 初七日(7日目) | 秦広王 | 不動明王 |
| 二七日(14日目) | 初江王 | 釈迦如来 |
| 三七日(21日目) | 宋帝王 | 文殊菩薩 |
| 四七日(28日目) | 五官王 | 普賢菩薩 |
| 五七日(35日目) | 閻魔大王 | 地蔵菩薩 |
| 六七日(42日目) | 変成王 | 弥勒菩薩 |
| 七七日(49日目) | 泰山王 | 薬師如来 |
| 百か日(100日目) | 平等王 | 観音菩薩 |
| 一周忌(1年目) | 都市王 | 勢至菩薩 |
| 三回忌(2年目) | 五道転輪王 | 阿弥陀如来 |
このように、故人は四十九日に行き先が決まるまで修行をしていて、7日ごとに仏様に会って懺悔をしたり教えを受けたりするという考え方もあるようです。
四十九日の裁きが終わると、故人の魂はこの世を離れ、遺族は「忌明け(きあけ)」として、日常生活に戻ります。
最近は、遠方の親戚や友人知人に初七日に再び集まってもらうのは大変だということで、葬儀の後に初七日法要を行うことが多くなっています。

どれくらいの期間で法要を行えばいいのか心構えができていれば、心静かに故人を供養する助けになります。
親しい方が亡くなることは悲しいことですが、極楽浄土へ行けるよう、その方へ感謝の気持ちを込めて追善供養ができるといいですね。
関連:六道(天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)の意味とは?
関連:【卒塔婆】読み方と意味とは?卒塔婆の書き方と値段、処分の仕方
関連:喪中と忌中の期間はいつまで?喪中と忌中の違いとしてはいけないこと

コメント