
「かるた」といえば、子供の頃、誰もが一度は遊んだことがあるのではないでしょうか?
かるた遊びを通して、言葉や文字を覚えた人という方もいらっしゃるでしょう。
かるたには百人一首や人気のアニメやキャラクターなどが題材にしたものなどいろいろな種類がありますが、今回は、「いろはかるた」にクローズアップしてみました!
かるたの起源や語源、種類とは?
「かるた」は1543年の鉄砲伝来と同じ時期にポルトガルから伝わってきました。
語源はポルトガル語でカードを意味する「carta(かるた)」だといわれています。
しかし、この当時、すでにかるたと同じような遊びは存在していました。
日本には、平安時代(794年~1185年)には二枚貝の貝殻を合わせる「貝合わせ」という遊びがあり、この貝合わせがヨーロッパから伝わってきたカードゲームと融合したようです。
関連:【日本語じゃなかった!?】実は外来語だった意外な言葉一覧

「貝合わせ」とは蛤(はまぐり)の対になる殻の内側に同じ絵を描き、複数の伏せた貝殻の中から対になる物を探し、もっとも数が多かった人が勝ちという遊びです。
神経衰弱に似ていますね!
江戸時代の元禄年間(1688年~1704年)と享保年間(1716年~1736年)のかるたが現存していることから、この頃にはすでにかるたは日本に広まっていたと考えられています。
また、日本のかるたは16世紀末ごろに、筑前(現在の福岡県大牟田市)で作られはじめたといわれています。
大牟田市には「三池カルタ・歴史資料館」がありますのでそちらでかるたの歴史を学ぶことが出来ますよ。
カルタの中では「いろはかるた」が最も古典的で有名です。
江戸(東京)、上方(京都とその周辺)、尾張(愛知県西部)で内容が違い、「犬も歩けば棒に当たる」で始まる江戸かるたは「犬棒かるた」とも呼ばれています。
いろはかるたは、子どもが文字や言葉を覚えるための遊びでもあり、ことわざや教訓などが用いられています。

また、昨今、漫画の影響で「競技かるた」が人気になっていますが、これは百人一首を用いて競技するものです。
百人一首もかるたの一種で「歌かるた」と呼ばれています。
ほかには、群馬県で親しまれている「上毛かるた」や、津軽弁や博多弁など方言を使った「方言かるた」、子ども向けアニメや童話などをモチーフに作られたかるたなどもあります。
かるたの遊び方

かるたとは、読み札と絵札に分かれた札・カードを用いて遊ぶものです。
遊び方はみなさんご存知のとおり、読み手が読み札を読み上げ、参加者は前に並べた絵札の中から読み札と対になるものを探し、取ります。
最後の札まで終わった時、一番枚数を持っていた人が勝ちとなります。
いろはかるたとは?枚数は何枚?
いろはかるたは「いろは歌」の文字の順にことわざや教訓を当てはめたものです。
いろは歌は以下のようになります。
いろはにほへと ちりぬるを
わかよたれそ つねならむ
うゐ(い)のおくやま けふこえて
あさきゆめみし ゑ(え)ひもせす
作者や作られた時期など、正確なことはわかっていませんが、47文字の仮名が重複せずに作られており、11世紀ごろから手習い(文字を書くことを習うこと)の手本として用いられていたそうです。
いろはかるたの枚数は、江戸と上方(京都)は48枚、尾張は47枚です。
関連:「いろはにほへと」の続きと意味とは?作者は誰?覚え方は?
「いろは歌」は最後の「ゑひもせす」で、47文字になりますが、「ゑひもせす京」と言う風に「京」の字を加えて48文字とすることがあります。
なぜ最後に「京」を加えるのかについては正確なことはわかっていませんが以下のように諸説あります。
いろは歌が直音(ちょくおん・仮名1文字で表す音、い、ろ、は、等のこと)だけで構成されているので、「京(きょう)」の「きょ」という拗音(ようおん・仮名2文字で表す音、しゃ、みゅ、等のこと)を加えてることでその発音を覚えさせるために入れたという説。

道中すごろく
ほかに、東海道五十三次を舞台にした道中双六(どうちゅうすごろく)は、江戸がスタートで京都がゴールだったので最後に京を加えたという説があります。
しかし、「京」が入っているかるたは室町時代にはすでにあったといわれており、東海道五十三次は江戸時代に整備されたので、時代が合いません。
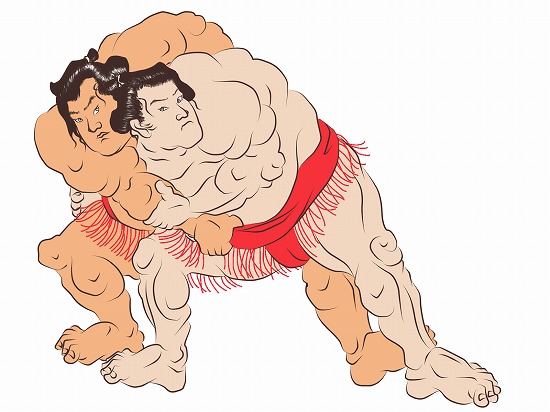
また、「京」と書いて「かなどめ」と読む相撲の力士の四股名があったことから「仮名のとめ(最後)」という意味で「京」を加えたという説がありますが、四股名も江戸時代ごろから用いられるようになったといわれており、こちらも時代が合いません。
逆にいろはかるたの最後が「京」だったので、「かなどめ」と読ませたのではないかといわれているぐらいです。
それでは江戸・上方(京都周辺)・尾張のいろはかるたを一覧にしてご紹介します!
いろはかるた(江戸・上方(京都)・尾張)の読み方と意味一覧
| 江戸 | 上方 (京都周辺) |
尾張 | |
| い | 犬も歩けば棒に当たる
読み: 意味: |
一寸先は闇
読み: 意味: |
一を聞いて十を知る
読み: 意味: |
| ろ | 論より証拠
読み: 意味: |
論語読みの論語知らず
読み: 意味: |
六十の三つ子
読み: 意味: |
| は | 花より団子
読み: 意味: |
針の穴から天覗く
読み: 意味:
|
花より団子
読み: 意味: |
| に | 憎まれっ子世にはばかる
読み: 意味: |
二階から目薬
読み: 意味: |
憎まれっ子頭堅し(神固し)
読み: 意味: |
| ほ | 骨折り損のくたびれ儲け
読み: 意味: |
仏の顔も三度
読み: 意味: |
惚れたが因果
読み: 意味: |
| へ | 下手の長談義
読み: 意味: |
下手の長談義
読み: 意味: |
下手の長談義
読み: 意味: |
| と | 年寄りの冷や水
読み: 意味: |
豆腐に鎹
読み: 意味: |
遠くの一家より近くの隣
読み: 意味: |
| ち | 塵も積もれば山となる
読み: 意味: |
地獄の沙汰も金次第
読み: ※「ぢごく」は「じごく」が正しい 意味: |
地獄の沙汰も金次第
読み: ※「ぢごく」は「じごく」が正しい 意味: |
| り | 律義者の子沢山
読み: 意味: |
綸言汗のごとし
読み: 意味: |
綸言汗のごとし
読み: 意味: |
| ぬ | 盗人の昼寝
読み: 意味: |
糠に釘
読み: 意味: |
盗人の昼寝
読み: 意味: |
| る | 瑠璃も玻璃も照らせば光る
読み: 意味: |
類をもって集まる
読み: 意味: |
類をもって集まる
読み: 意味: |
| を | 老いては子に従え
読み: ※「をいて」は「おいて」が正しい 意味: |
鬼も十八
読み: ※「をに」は「おに」が正しい 意味: |
鬼の女房に鬼神
読み: 意味: |
| わ | 破れ鍋に綴じ蓋
読み: 意味: |
笑う門には福来る
読み: 意味: |
若いときは二度ない
読み: 意味: |
| か | かったいの瘡うらみ
読み: 意味: |
蛙の面に水
読み: 意味: |
陰うらの豆もはじけ時
読み: 意味: |
| よ | 葦の髄から天井を覗く 読み: よしのずいからてんじょうをのぞく意味: 細い葦(あし)の茎の穴を通して天井を見て、天井の全部を見たような気になることから、自分の狭い知識や経験に基づいて物事を判断することのたとえ |
夜目遠目笠の内
読み: 意味: |
横槌で庭を掃く
読み: 意味: |
| た | 旅は道連れ世は情け
読み: 意味: |
立て板に水
読み: 意味: |
大食上戸餅食らい
読み: 意味: |
| れ | 良薬は口に苦し
読み: ※「れうやく」は「りょうやく」が正しい 意味: |
連木で腹切る
読み: 意味: |
連木で腹切る
読み: 意味: |
| そ | 総領の甚六
読み: 意味: |
袖振り合うも他生の縁
読み: 意味: |
袖振り合うも他生の縁
読み: 意味: |
| つ | 月とすっぽん
読み: 意味: |
月夜に釜を抜かれる
読み: 意味: |
爪に火をともす
読み: 意味: |
| ね | 念には念を入れよ 読み: ねんにはねんをいれよ意味: 注意したうえにさらに注意せよということ |
猫に小判
読み: 意味: |
寝耳に水
読み: 意味: |
| な | 泣きっ面に蜂
読み: 意味: |
済す時の閻魔顔
読み: 意味: |
習わぬ経は読めぬ
読み: 意味: |
| ら | 楽あれば苦あり
読み: 意味: |
来年の事を言えば鬼が笑う
読み: 意味: |
楽して楽知らず
読み: 意味: |
| む | 無理が通れば道理引っ込む
読み: 意味: |
馬の耳に風
読み: ※「むま」は「うま」が正しい 意味: |
無芸大食
読み: 意味: |
| う | 噓から出た実
読み: 意味: |
氏より育ち
読み: 意味: |
牛を馬にする
読み: 意味: |
| ゐ | 芋の煮えたもご存じない
読み: ※「ゐも」は「いも」が正しい 意味: |
鰯の頭も信心から
読み: ※「ゐわし」は「いわし」が正しい 意味: |
炒り豆に花が咲く
読み: 意味: |
| の | 喉元過ぎれば熱さを忘れる
読み: 意味: |
鑿と言えば槌
読み: 意味: |
野良の節句働き
読み: 意味: |
| お | お鬼に金棒
読み: 意味: |
負うた子に教えられて浅瀬を渡る
読み: 意味: |
陰陽師身の上知らず
読み: 意味: |
| く | 臭いものに蓋をする
読み: 意味: |
臭い物に蝿がたかる
読み: 意味: |
果報は寝て待て
読み: ※「くゎはう」は「かほう」が正しい 意味: |
| や | 安物買いの銭失い
読み: 意味: |
闇に鉄砲
読み: 意味: |
闇に鉄砲
読み: 意味: |
| ま | 負けるが勝ち
読み: 意味: |
まかぬ種は生えぬ
読み: 意味: |
待てば甘露の日和あり
読み: 意味: |
| け | 芸は身を助く
読み: 意味: |
下駄と焼き味噌
読み: 意味: |
下戸の建てた蔵はない
読み: 意味: |
| ふ | 文はやりたし書く手は持たぬ
読み: 意味: |
武士は食わねど高楊枝
読み: 意味: |
武士は食わねど高楊枝
読み: 意味: |
| こ | 子は三界の首枷
読み: 意味: |
此れに懲りよ道才棒
読み: 意味: |
志は松の葉
読み: 意味: |
| え | 得手に帆を揚げる
読み: 意味: |
縁と月日
読み: 意味: |
閻魔の色事
読み: 意味: |
| て | 亭主の好きな赤烏帽子
読み: 意味: |
寺から里へ
読み: 意味: |
天道人殺さず
読み: 意味: |
| あ | 頭隠して尻隠さず
読み: 意味: |
足元から鳥が立つ
読み: 意味: |
阿呆につける薬はない
読み: 意味: |
| さ | 三遍回って煙草にしょ 読み: さんべんまわってたばこにしょ意味: 夜回りで、三度見回ってから休憩にしようということから、休むことを急がず、念を入れて落ち度のないようにしようというたとえ |
竿の先に鈴
読み: 意味: |
触らぬ神にたたりなし
読み: 意味: |
| き | 聞いて極楽見て地獄 読み: きいてごくらくみてじごく意味: 話に聞くのと、実際に見るのとでは非常に差があるということ |
鬼神に横道なし
読み: 意味: |
義理と褌かかねばならぬ
読み: 意味: |
| ゆ | 油断大敵 読み: ゆだんたいてき意味: 注意を怠ると思わぬ失敗を招くので、十分に気を付けるようにということ |
幽霊の浜風
読み: 意味: |
油断大敵
読み: 意味: |
| め | 目の上のこぶ 読み: めのうえのこぶ意味: 目の上にできたこぶは視界を遮りとても邪魔であることから、何かと目障りで鬱陶しい人のたとえ |
盲の垣のぞき
読み: 意味: |
目の上のこぶ
読み: 意味: |
| み | 身から出た錆 読み: みからでたさび意味: 刀の錆は刀身から生じるところから自分の悪行が結果として自分を苦しめることになるということ。自業自得。 |
身は身で通る
読み: 意味: |
蓑売りの古蓑
読み: 意味: |
| し | 知らぬが仏
読み: 意味: |
吝ん坊の柿のさね
読み: 意味: |
尻食へ観音
読み: 意味: 旧暦の18日から23日までの六観音の縁日のあと、だんだん闇夜になるのを「尻暗い」といいましたが、それがののしり言葉となり「尻食らえ」というようになった |
| ゑ | 縁は異なもの味なもの
読み: ※「ゑん」は「えん」が正しい 意味: |
縁の下の舞
読み: ※「ゑん」は「えん」が正しい 意味: |
縁の下の力持ち
読み: ※「ゑん」は「えん」が正しい 意味: |
| ひ | 貧乏暇なし
読み: 意味: |
瓢箪から駒
読み: 意味: |
貧僧の重ね食い
読み: 意味: |
| も | 門前の小僧習わぬ経を読む
読み: 意味: |
餅は餅屋
読み: 意味: |
桃栗三年柿八年
読み: 意味: |
| せ | 急いては事を仕損じる
読み: 意味: |
雪隠で饅頭
読み: 意味: |
背戸の馬も相口
読み: 意味: |
| す | 粋は身を食う
読み: 意味: |
雀百まで踊り忘れぬ
読み: 意味: |
墨に染まれば黒くなる
読み: 意味: |
| 京 | 京の夢大阪の夢
読み: 意味: |
京に田舎あり
読み: 意味: |
なし
|

いかがでしたでしょうか?
同じ「いろはかるた」でも、関東と関西など地域で違いがあることがわかりましたね。
子どもに文字や言葉を覚えさせる目的があるということですが、たくさんのことわざが用いられているので、大人でも楽しく学ぶことができます。
お子さんと「いろはかるた」をする時には、ことわざの意味を説明しながら一緒に遊べるようになると、素敵だと思いませんか?
関連:「いろはにほへと」の続きと意味とは?いろは歌の作者は誰?覚え方は?
関連:【百人一首 一覧】それぞれの作者と意味とは?人気の和歌はどれ?百人一首のルール解説
関連:【日本語じゃないの?】外来語とは知らずに使っていた意外な日本語

コメント