
天気予報を見ていると時々耳にする「三寒四温」という言葉。
寒い冬が終わり、春に移り変わるころによく耳にすることがありますが・・・どうやらそれは本来の使い方ではないようです。
では、三寒四温の正しい使い方はどのようなものなのでしょう?
三寒四温の意味、季節や時期をご紹介します。
三寒四温の意味とは?
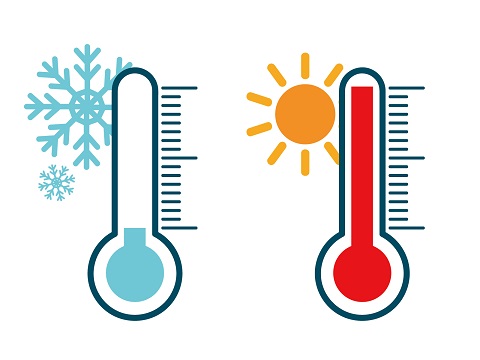
読み方は「さんかんしおん」です。
三寒四温とは、
冬の時期に寒い日が3日間ほど続くと、次に暖かい日が4日間ほど続き、また寒くなる・・・
というようにおよそ7日間の周期で寒い日と暖かい日が繰り返されるという意味です。
季節や時期は?
「三寒四温」は、もともと冬の時期に中国北東部や朝鮮半島に現れる気象現象ことを指します。
シベリア高気圧の影響で寒い日が3日間、次に暖かい日が4日間、ほぼ7日間の周期で寒い日と暖かい日が繰り返される現象のことをいいます。

中国から日本に伝わってきた後も「三寒四温」は、冬の気候を表す言葉として使われていました。
しかし、日本はシベリア高気圧だけではなく太平洋高気圧の影響も受けるので、冬の間に三寒四温がはっきりと現れることは稀で、一冬に一度あるかないかという程度です。
日本で三寒四温に似たような現象が起こるのは、2月の終わりから3月にかけてです。
そのため日本では、「三寒四温」という言葉は 2月下旬から3月の春先の時期に使われるようになったのです。
正しい使い方は?
「三寒四温」の気象現象が起こるのは2月の終わりから3月にかけてですが、手紙などの冬の挨拶では、1月~2月に以下のように使います。
「三寒四温の候、まずますご発展のこととお慶び申し上げます。」
「三寒四温を感じる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。」
そして、3月になると使わないのが一般的です。
関連:時候の挨拶・季節の挨拶 1月~12月(上旬・中旬・下旬)の手紙やビジネスで使える例文

しかし、「三寒四温」のような現象が起こるのは春先なので、天気予報や日常的な会話では春先に使われます。
天気予報などでは、2月下旬から3月にかけて、実際に三寒四温の気候になった場合に以下のように使います。
「3月第一週は、三寒四温の気候になります。」
「三寒四温で日々の寒暖差があるので、体調を崩さないよう気を付けてください。」
二通りの使い方を紹介しましたが、三寒四温をここまで厳格に使い分ける人はほとんどいません。
もともとの使い方を尊重して「冬に使うのが正しく、春先に使うのは間違いだ」という意見もありますし、実際の気候に合わせて「春先に使っても間違いではない」という意見もあります。
このように、三寒四温は「正しい使い方はこうです」と言い切ることが難しい言葉なのです。
三寒四温はいつの季語?

俳句の場合、「三寒四温」は冬の季語になります。
冬の季語は、立冬(毎年11月7日ごろ)~立春(毎年2月4日ごろ)に使われます。
「三寒四温」は冬の季語ですが、冬の終わりごろである1月~立春(毎年2月4日ごろ)まで使います。
関連:【俳句の季語一覧】小学生向け 春夏秋冬新年 月ごと(1月~12月)の季語

いかがでしたでしょうか?
三寒四温は、もともとは中国北東部や朝鮮半島の気候を表す言葉だったのですね。
本来は冬の言葉ですが、日本では一般的に春先に使う人のほうが多いようです。
本来の意味からははずれますが、三寒四温に似た現象が春先に起こるのなら、日本の気象現象として春先に使うのもいいのではないでしょうか。
外国から伝わってくる言葉や文化を上手に受け入れ、日本独自のものに変化させていくのも、日本人らしいですよね。
関連:「三寒四温」の逆(反対語)とは?秋の時期に使う言葉は何?
関連:「寒の戻り」「花冷え」とは?意味や時期、使い方。反対語は何?

コメント