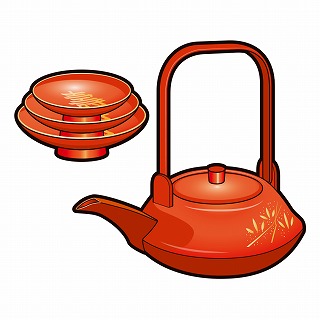
結婚式にはいろいろな挙式スタイルがありますが、ご自身の結婚式で「三三九度」を行ったという方も多いと思います。
ところで、なぜ三三九度は「三」と「九」なのでしょうか?
今回は、三三九度の意味とやり方についてわかりやすく解説します。
三三九度(三々九度)とは?
読み方は「さんさんくど」です。
「三献の儀(さんこんのぎ)」ともいい、日本の結婚式の神前式で行う儀式のひとつです。
神前式(しんぜんしき)は「神社挙式」ともいい、神社などに祀られている神様の前で結婚を誓う、日本の伝統的な挙式スタイルです。

三三九度のはじまりは定かではありませんが、室町時代(1336年~1573年)ごろに武家の結婚式の中でその形式が整えられたといわれています。
室町時代の武家では重要な儀式として、結婚式だけではなく、出陣(戦に行くこと)や帰陣(戦から戻ること)、お客を招いての宴などでも行われていました。
江戸時代(1603年~1868年)に入ってから、三三九度の作法が徐々に変化し、庶民の間にも広がっていきました。
現在は、主に結婚式で行われていますが、お正月や端午の節句、七五三などで行ったり、選挙の出陣式やお祭などで行うこともあります。
基本的なやり方や作法はすべて同じです。
三三九度(三々九度)の意味とは?
三三九度は三つの盃(さかずき)で三献(さんこん・三度)、神様にお供えした神酒(みき・しんしゅ)を頂くという意味があります。
お酒の種類に決まりはありませんが、主に日本酒が用いられます。
由来は「3×3=9」ということで「三三九度」と呼ばれるようになりました。

結婚式での三三九度は、新郎新婦が盃(さかずき)を交わすことで夫婦の契りを結ぶという意味です。
日本には古来より、同じ釜で煮炊きしたものを一緒に食べることによって、非常に強い絆が生まれるという信仰があります。
新郎新婦が同じ盃を使って神酒を飲むことで夫婦の絆が結ばれると考え、
「夫婦固めの盃(ふうふかためのさかずき)」
「親族固めの盃(しんぞくかためのさかずき)」
「夫婦盃(めおとさかずき)」
とも呼ばれています。
お正月や七五三、選挙などで行う三三九度も同様に親族や仲間の絆を深めの意味があり、縁起かつぎのために行うことが多いようです。
三三九度(三々九度)はなぜ「三」と「九」なの?
三三九度が「三」と「九」なのは、中国の陰陽五行思想の影響です。
奇数は陽数(1・3・5・7・9)といわれ、おめでたい数、縁起が良い数と考えられていました。
そして、偶数(2・4・6・8)は陰数(いんすう)といわれ、縁起が悪い数と考えます。
奇数の中でも三は「天・地・人(宇宙に存在する万物)」を表すめでたい数字といわれています。
さらに、三を重ねあわせた九(3×3=9)は陽数の最大の数なのでこの上なくめでたいという意味になるのだそうです。
三三九度(三々九度)のやり方
結婚式の三三九度
三三九度では、大・中・小三種類の盃を用います。
一番上が一の盃(小)
真ん中が二の盃(中)
一番下が三の盃(大)
になるように重ね、上から順番に使います。

まず、「一の盃(小)」は以下のように使います。
①
巫女が一の盃(小)を新郎に渡します。
②
巫女がお銚子から神酒を三回に分けて一の盃(小)に注ぐので、新郎は三回に分けて神酒を飲みます。
③
新郎は一の盃(小)を巫女に返し、その盃を巫女が新婦に渡します。
④
巫女がお銚子から神酒を三回に分けて一の盃(小)に注ぐので、新婦が三回に分けて神酒を飲みます。
⑤
新婦は一の盃(小)を巫女に返し、その盃を巫女が新郎に渡します
⑥
巫女がお銚子から神酒を三回に分けて一の盃(小)に注ぐので、新郎が三回に分けて神酒を飲みます。

続いて、二の盃、三の盃でも同じように行いますが、新郎新婦の順番は異なり、以下のようになります。
① 一の盃(小)・・・新郎→新婦→新郎
② 二の盃(中)・・・新婦→新郎→新婦
③ 三の盃(大)・・・新郎→新婦→新郎

また、現在は三度目が省略され、下のように行うこともあります。
① 一の盃(小)・・・新郎→新婦
② 二の盃(中)・・・新婦→新郎
③ 三の盃(大)・・・新郎→新婦
それぞれの盃にはそれぞれ意味があるといわれています。
●一の盃(小)
過去を表しており、新郎新婦の巡り合わせを先祖に感謝する意味があります。
●二の盃(中)
現在を表しており、新郎新婦がこれから力を合わせて生きていくことを意味しています。
●三の盃(大)
未来を表しており、新郎新婦両家の安泰と子孫繁栄の意味があります。

また、巫女が盃に神酒を注ぐ時に三回に分けますが、一度目と二度目はお銚子を傾けるだけで神酒を注ぎません。三度目で盃に神酒を注ぎます。
そして、新郎新婦が三回に分けて飲む際は、三口に分けて少しずつ飲み干す作法と、一口目と二口目は盃に口をつけるだけで、三口目で全て飲む作法があり、どちらでも良いとされています。
神酒は飲み干さなければならないのかというと、そうではありません。
お酒に弱い人や妊娠中の人など、お酒を飲むことを避けなければならない場合は、口を付けるだけにしてお酒を残しても問題はありませんので、事前に巫女やスタッフの方に伝えておくと良いでしょう。
結婚式以外の三三九度のやり方は以下のとおりです。
お正月や七五三などの三三九度
お正月の三三九度では、お屠蘇(おとそ)を用います。
お屠蘇は、日本酒やみりんで5種類~10種類の生薬を漬け込んで作る薬草酒のひとつで、正式には「屠蘇散(とそさん)」または「屠蘇延命散(とそえんめいさん)」といいます。
お屠蘇の詳細については以下をご覧ください。
関連:お屠蘇の意味と由来とは?お屠蘇の作り方、飲み方の作法と飲む順番
七五三などでは神酒を用いることが一般的です。

お屠蘇・神酒は、子どもの盃には子どもの成長を願って親が注ぎ、親の盃には親の長寿を願って子どもが注ぎます。
結婚式同様、一度目と二度目はお銚子を傾けるだけでお屠蘇・神酒を注がず、三度目で盃にお屠蘇・神酒を注ぎます。
飲み方も、結婚式同様、三口に分けて少しずつ飲み干す作法と、一口目と二口目は盃に口をつけるだけで、三口目で全て飲む作法があり、どちらでも良いとされています。
お子さんが小さい場合は参加させなかったり、実際に飲ませずに飲む真似だけをするというご家庭もあるようです。
三三九度を行う順番は以下のように年少者からです。(5人家族で例えています)
① 一の盃(小)
最年少者→二番目の年少者→三番目の年少者→四番目の年少者→最年長者
② 二の盃(中)
二番目の年少者→三番目の年少者→四番目の年少者→最年長→最年少者
③ 三の盃(大)
三番目の年少者→四番目の年少者→最年長→最年少→二番目の年少者
選挙の三三九度
選挙の三々九度は、室町時代の武家が、出陣の縁起かつぎとして行っていたことが由来です。
室町時代の出陣では、総大将が、
●打ち鮑(うちあわび・鮑を細長く切って打ち延ばして干したもの)
●勝栗(かちぐり・栗の実の皮をむかずに乾かしたもの)
●昆布(こんぶ)
の三品を食べ、酒を三度口にしました。
「敵を打って(打ち鮑)、勝って(勝栗)、よろこぶ(昆布)」という縁起かつぎで、酒を飲んだあとの盃を地面に投げて打ち砕き、出陣の合図にしていました。
現在の選挙では、選挙に立候補した候補者が総大将の立場となり、当選するようにという縁起かつぎとこれから始まる選挙戦をみんなで乗り切ろうという気合を入れる儀式として行われるそうです。
現在は三品を食べることを省略して酒だけ三度口にしたり、候補者と関係者が総大将の立場になるなど、作法はさまざまのようですよ。

三三九度がどういうものなのかわかりましたね。
神前の厳かな雰囲気の中、結婚式で新郎新婦が三三九度をする姿を見ると、これから夫婦として一緒に生きていく覚悟のようなものを感じます。
結婚式以外でも行うことがありますので、室町時代の武家から続く、人と人の絆を深める大切な儀式を、これからも受け継いでいきたいですね。
関連:2025年入籍や結婚式に良い日はいつ?結婚・入籍日カレンダー
関連:万歳の意味や由来とは?万歳三唱と一本締めや三本締めとの違いとは?
関連:一本締め、一丁締め、三本締めの違いとは?意味や使い分け、やり方について
関連:お屠蘇の意味と由来とは?お屠蘇の作り方、飲み方の作法と飲む順番

コメント