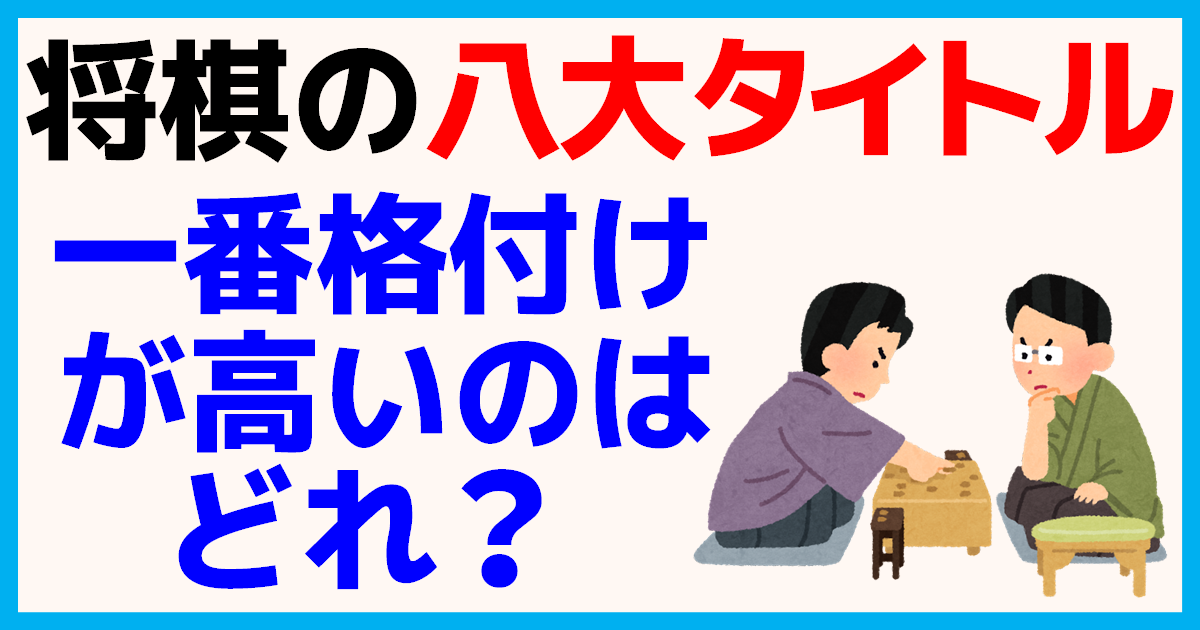
みなさんは「竜王戦」や「名人戦」などの「タイトル戦」についてご存知ですか?
将棋には八大タイトルというものがあるのですが、一番格付けが高いのはどのタイトルになるのでしょうか?
その序列(格付け)や賞金、主催者などを一覧にしてご紹介します!
将棋のタイトルとは?
将棋のタイトルとは、スポンサーがついて賞金が出る大会のことです。
現在、タイトルは8つあり「八大タイトル」と呼ばれています。
八大タイトルは以下のとおりです。
●竜王(りゅうおう)
●名人(めいじん)
●王位(おうい)
●王座(おうざ)
●棋王(きおう)
●叡王(えいおう)
●王将(おうしょう)
●棋聖(きせい)
「タイトル戦」とは、八大タイトルの各タイトル保持者と挑戦者が対局することです。
それぞれのタイトルの名前をとって「竜王戦」や「名人戦」などと呼びます。
棋士は普段「〇〇九段」のように名前の後に段位をつけて呼びますが、タイトルを取ると「〇〇王座」のように名前のあとにタイトルをつけて呼ぶようになります。
複数のタイトルを保持することもできます。
その場合は保持しているタイトルの数で「二冠」や「三冠」と呼びます。
「〇〇王位・王座・棋王」のように並べて呼ぶこともできますが、その際は、タイトルの序列順に呼びます。
また、「竜王」と「名人」は別格とされています。
「二冠」や「三冠」のように複数のタイトルを持っていても、優先的に「〇〇竜王」「〇〇名人」と呼びます。
「竜王」と「名人」両方持っている場合は、「〇〇竜王名人」と並べて呼びます。
※タイトルの格付けにつきましては、後ほどご説明させていただきます。

藤井聡太さんの場合、2020年7月16日に棋聖戦で渡辺明棋聖を破り、棋聖位を獲得したので、この時から「藤井聡太棋聖」となりました。
17歳11ヶ月での八大タイトル獲得は史上最年少で、屋敷伸之九段の記録(18歳6ヶ月)を30年ぶりに更新しました。
また、それまでの棋聖の最年少記録(18歳6ヶ月・屋敷伸之九段)も更新しました。
●二冠
2020年8月20日には王位戦で木村一基王位を破り、最年少の18歳1ヶ月で二冠を達成し「藤井聡太二冠(王位・棋聖)」になりました。
それまでの羽生善治九段の記録(21歳11ヶ月)を更新しました。
また、それまでの王位の最年少記録(21歳5ヶ月・郷田真隆九段)も更新しました。
●三冠
2021年9月13日には叡王戦で豊島将之二冠(竜王・叡王)を破り、史上最年少となる19歳1ヶ月で三冠を達成し「藤井聡太三冠(王位・叡王・棋聖)」となりました。
それまでの羽生善治九段の記録(22歳3ヶ月)を更新しました。
また、それまでの叡王の最年少記録(24歳10ヶ月・高見泰地七段)も更新しました。
●四冠
2021年11月13日には竜王戦で豊島将之竜王を破り、史上最年少となる19歳3ヶ月で四冠を達成し「藤井聡太四冠(竜王・王位・叡王・棋聖)」となりました。
それまでの羽生善治九段の記録(22歳9ヶ月)を更新しました。
竜王の最年少記録は羽生善治九段の19歳3ヶ月0日です。(藤井竜王は19歳3ヶ月25日)
●五冠
2022年2月12日には王将戦で渡辺明王将を破り、史上最年少となる19歳6ヶ月で五冠を達成し「藤井聡太五冠(竜王・王位・叡王・王将・棋聖)」となりました。
それまでの羽生善治九段の記録(22歳10ヶ月)を更新しました。
また、それまでの王将の最年少記録(23歳4ヶ月・中村修九段)も更新しました。
●六冠
2023年3月19日には棋王戦で渡辺明棋王を破り、史上最年少となる20歳8ヶ月で六冠を達成し「藤井聡太六冠(竜王・王位・棋王・叡王・王将・棋聖)」となりました。
それまでの羽生善治九段の記録(24歳2ヶ月)を更新しました。
棋王の最年少記録は羽生善治九段の20歳5ヶ月です。
●七冠
2023年6月1日には名人戦で渡辺明名人を破り、史上最年少となる20歳10ヶ月で七冠を達成し「藤井聡太七冠(竜王・名人・王位・棋王・叡王・王将・棋聖)」となりました。
それまでの羽生善治九段の記録(25歳4ヶ月)を更新しました。
また、それまでの名人の最年少記録(21歳2ヶ月・谷川浩司九段)も更新しました。
●八冠
2023年10月11日には王座戦で永瀬拓矢王座を破り、史上初となる21歳2ヶ月で八冠を達成し「藤井聡太八冠(竜王・名人・王位・王座・棋王・叡王・王将・棋聖)」となりました。
また、それまでの王座の最年少記録(21歳11ヶ月・羽生善治九段)も更新しました。
八大タイトルの最年少記録については以下の記事で一覧にまとめています。
関連:将棋の八大タイトル最年少記録一覧!八大タイトル○冠の最年少記録一覧

これまでの最多は、藤井聡太さんの「八冠」で、羽生善治さんの「七冠」が続きます。
ただし、羽生善治さんが七冠を達成した平成8年(1996年)当時は、叡王がなくタイトル数は7つだったため、全7タイトルをすべて取って「七冠」を達成しています。
八大タイトルはそれぞれ、一年に一度挑戦することができます。
各タイトルの予選で優勝した棋士が、タイトル挑戦の権利を得ることができます。
対戦数はタイトルによって異なり、先に勝ち越した方が勝者となります。
将棋のタイトルで一番格が高いのは?序列や賞金とは?
八大タイトルの序列は、賞金額で順番が決まっており、以下のようになっています。
※賞金額が公表されていないものは推定金額を書いています。
① 竜王戦(りゅうおうせん)
開催時期:10月~12月
賞金額:4320万円
対局数:7番勝負(先に4勝した方が勝者)
主催:読売新聞社
現在のタイトル保持者:藤井聡太
竜王戦は、名人戦と並んでプロ将棋界の頂点といわれています。
② 名人戦(めいじんせん)
開催時期:4月~7月
推定賞金額:2000万円
対局数:7番勝負(先に4勝した方が勝者)
主催:毎日新聞社と朝日新聞社
現在のタイトル保持者:藤井聡太
名人戦は、竜王戦と並んでプロ将棋界の頂点といわれています。
③ 王位戦(おういせん)
開催時期:7月~9月
推定賞金額:1000万円
対局数:7番勝負(先に4勝した方が勝者)
主催:ブロック紙3社連合(北海道新聞社・中日新聞社・西日本新聞社)
現在のタイトル保持者:藤井聡太
④ 王座戦(おうざせん)
開催時期:9月~10月
推定賞金額:800万円
対局数:5番勝負(先に3勝した方が勝者)
主催:日本経済新聞社
現在のタイトル保持者:藤井聡太
⑤ 棋王戦(きおうせん)
開催時期:2月~3月
推定賞金額:600万円
対局数:5番勝負(先に3勝した方が勝者)
主催:共同通信社
現在のタイトル保持者:藤井聡太
⑥ 叡王戦(えいおうせん)
開催時期:3月~5月
推定賞金額:300~600万円
対局数:5番勝負(先に3勝した方が勝者)
主催:不二家と日本将棋連盟
現在のタイトル保持者:伊藤匠
叡王戦は2015年に初めて一般棋戦(いっぱんきせん・タイトル戦以外の公式戦)として開催され、2017年度からタイトル戦になりました。
八大タイトルの中では最も新しいタイトル戦です。
2020年の第5期までは主催がドワンゴで序列は3番目でしたが、2021年の6期から主催が変わり序列は6番目になっています。
⑦ 王将戦(おうしょうせん)
開催時期:1月~3月
推定賞金額:300万円
対局数:7番勝負(先に4勝した方が勝者)
主催:スポーツニッポン新聞社と毎日新聞社
現在のタイトル保持者:藤井聡太
⑧ 棋聖戦(きせいせん)
開催時期:6月~7月
推定賞金額:300万円
対局数:5番勝負(先に3勝した方が勝者)
主催:産経新聞社
現在のタイトル保持者:藤井聡太

さて、これら八大タイトルの中で一番格が高いのはどれになるのでしょうか?
一番格が高いのは、最も歴史が古い「名人」と、最も賞金額が高い「竜王」といわれています。
日本将棋連盟では「名人」と「竜王」を同格としています。
名人と竜王どちらの格が高いのか?ということになると、明確な決まりがないため、将棋ファンの間でも意見が分かれるそうですが、「名人」と「竜王」が別格であることは間違いないようです。
ただし、すでに説明したように「竜王」と「名人」両方持っている場合は、「〇〇竜王名人」というように賞金額の高い「竜王」が先に来ます。
他のタイトルの格は、賞金金額の高いほうが格上ということになっています。
永世称号とは?
永世称号とは、プロ棋士引退後に名乗ることができるもので、タイトルを指定の期間または回数保持することで得ることができます。
(※将棋界への貢献などにより、特例として現役のまま名乗ることが許される場合もあります。)
各タイトルの指定期間または回数保持については後ほど説明します。
羽生善治さんは、将棋界初の永世七冠として2018年に国民栄誉賞を受賞しました。
関連:国民栄誉賞とは?賞金や年金はあるの?受賞者一覧!辞退した人とその理由
「七冠」だけですと、7つのタイトルを保持しているということになりますが、「永世七冠」というのは、7つのタイトルを指定の期間または回数保持し、引退後に永世称号を名乗ることができる資格を得たということになります。
羽生善治さんの場合、2017年からタイトル戦に加わった叡王戦以外の7つすべての永世称号を名乗ることができます。
※「永世叡王」の称号は2023年に規定されたばかりのため、現在保持者はいらっしゃいません。
永世称号の条件はタイトルによって異なりますのでひとつずつ見ていきましょう。
※タイトル戦は年に一度行われるので、一期は一年間です。
永世竜王
タイトル保持期間は、連続5期または通算7期
永世竜王は、渡辺明、羽生善治
永世名人
タイトル保持期間は、通算5期
永世名人は、木村義雄、大山康晴、中原誠、谷川浩司、森内俊之、羽生善治
永世王位
タイトル保持期間は、連続5期または通算10期
永世王位は、大山康晴、中原誠、羽生善治、藤井聡太
名誉王座
タイトル保持期間は、連続5期または通算10期
名誉王座は、中原誠、羽生善治
王座戦のみ「永世称号」ではなく「名誉称号」なのは、囲碁が関係しています。
囲碁にもタイトル戦があり、指定の期間または回数タイトル保持をすると「名誉称号」を与えられます。
将棋の「王座戦」よりも囲碁のほうが先にあったため、囲碁にあわせて「名誉称号」になったといわれています。
永世棋王
タイトル保持期間は、連続5期
永世棋王は、渡辺明、羽生善治
永世王将
タイトル保持期間は、通算10期
永世王将は、大山康晴、羽生善治
永世叡王
タイトル保持期間は、通算5期
永世叡王は、まだいらっしゃいません。
永世棋聖
タイトル保持期間は、通算5期
永世棋聖は、大山康晴、中原誠、米長邦雄、羽生善治、佐藤康光、藤井聡太

将棋のタイトルがどのようなものかわかりましたか?
ひとつのタイトルを取るだけでもすごいことですが、複数のタイトルを保持したり、ひとつのタイトルを長年にわたって保持したりすることは、とても難しいことなのではないでしょうか?
棋士がそこに辿り着くには、私たちには想像もできないほどの努力をなさっているのでしょうね。
関連:将棋の八大タイトル最年少記録一覧!八大タイトル○冠の最年少記録一覧
関連:将棋の日2025年はいつ?意味と由来とは?イベント情報
関連:「段」は数字が大きいほど上なのに「級」は数字が小さいほど上なのはなぜ?
関連:囲碁の七大タイトルで一番格付けが高いのは?序列や賞金を紹介します!

コメント
コメント一覧 (2件)
永世棋王は渡辺明二冠が2017年の42期棋王戦で5連覇(2020年,45期棋王戦で8連覇)しているので羽生九段だけではありません。
ご指摘感謝いたします!
助かりました!