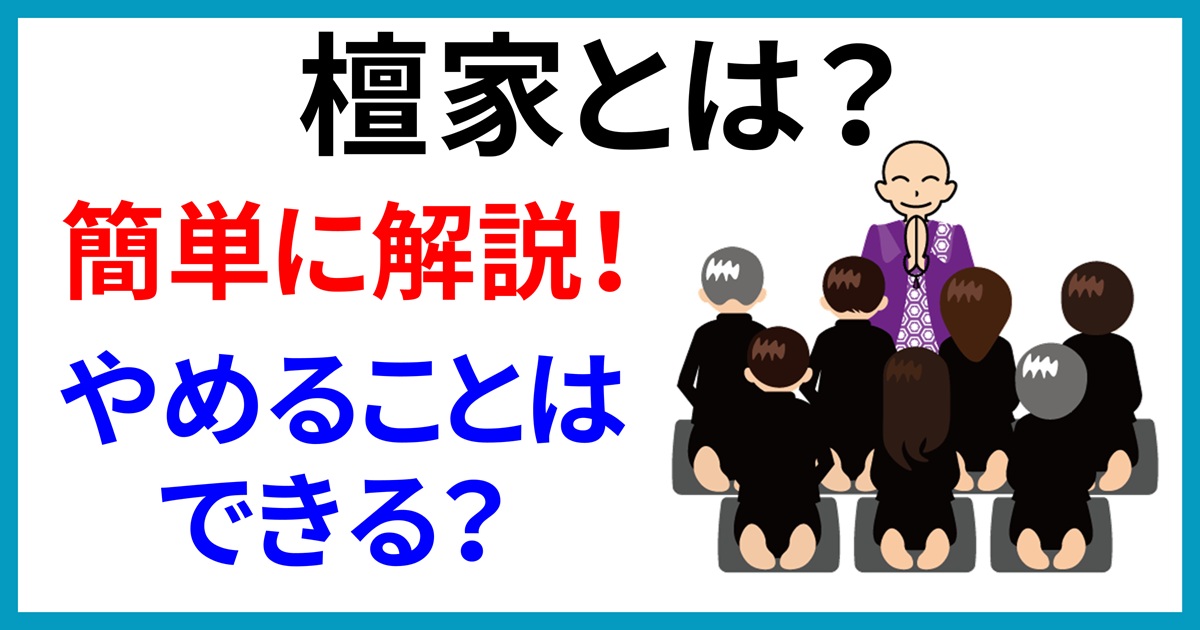
日本人の多くは、どこかのお寺の檀家になっているそうです。
では、檀家とはなんでしょうか?
檀家をやめることはできるのでしょうか?
檀家について簡単にわかりやすく説明します。
檀家とは?簡単にわかりやすく説明
読み方は「だんか」です。
サンスクリット語で「与える」や「施す」という意味の「dāna(ダーナ)」が語源です。
檀家には、お寺や僧侶を支援する人、お布施をする人などの意味があります。
「dāna」は中国で「檀那(だんな)」という漢字が当てられ、飛鳥時代(592年~710年)に仏教伝来とともに中国から日本へ伝わりました。
檀那は「旦那」とも書き、裕福な人や、人を雇う主人を指すようになり、現在は夫を意味する言葉として一般的に使われています。
その後、江戸時代(1603年~1868年)の檀家制度によって「檀那(個人を指す)」から「檀家(家や世帯を指す)」に変化しました。
※檀家制度については後ほど説明します。
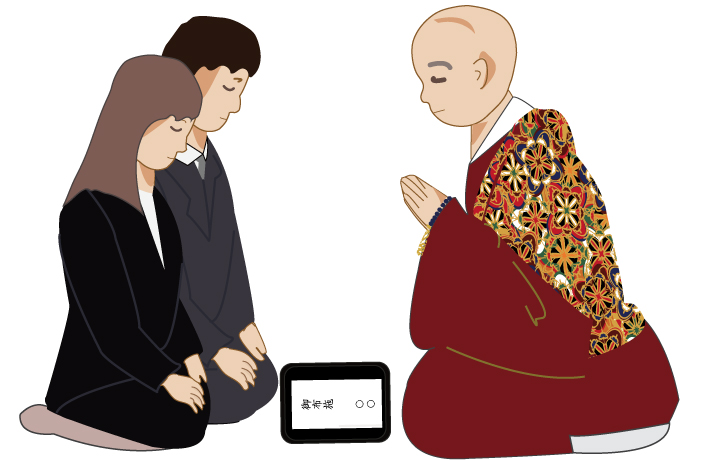
檀家とは、特定のお寺にお布施や会費などを納める代わりに、葬式や法事などを執り行ってもらう家のことで、基本的に家単位で檀家になります。
宗派によって「檀家」の呼び方が異なり、
- 浄土真宗では「門徒(もんと)」
- 浄土宗では「信徒(しんと)」
- それ以外の宗派は「檀家」
と呼びます。
また、檀家が所属するお寺を「菩提寺(ぼだいじ)」と呼びます。
檀家の由来
檀家という仕組みは、江戸時代(1603年~1868年)に出来ました。
江戸時代初期、日本にはキリスト教を信仰する人々がおり、その勢力を拡大させていました。
しかし、キリスト教は「すべての人は神のもとに平等」という教えであり、当時の身分制度(士農工商)と根本的に合わないものでした。

そのため江戸幕府は、身分秩序と政治体制を守るため、1612年にキリスト教を禁止する禁教令(きんきょうれい・キリスト教禁止令)を出しました。
そして、キリスト教を信仰していないことを証明するために檀家制度を定め、各家庭ごとに特定のお寺に所属することを義務付けました。
檀家制度は、
- 「寺請制度(てらうけせいど)」
- 「寺檀制度(じだんせいど)」
と呼ぶこともあります。
禁教令は明治6年(1873年)に廃止されましたが、現在もお寺と檀家の関係は続いており、現在でも檀家として菩提寺を持つご家庭は多いのです。
檀家になるには?メリット・デメリット
檀家になることを「入檀(にゅうだん)」といいます。
入檀したいお寺を決め、入檀の手続きを行うことで檀家になることができます。
檀家になることのメリットは、
- お盆など繁忙期でも優先してもらえる
- 葬儀、法事、供養のすべてを菩提寺が行ってくれる
- お墓の管理を菩提寺に任せることができる
- 仏事に関することの相談が気軽にできる
などがあります。

檀家になることのデメリットは、
- 入会金や年会費などが必要になる場合がある
- 寄付金を求められることがある
- 他のお寺に葬儀などを依頼できない
- お寺ごとのルールを守らなければならない
などがあります。
檀家の費用と相場
入会金
入会金は、「入檀料(にゅうだんりょう)」と呼ばれます。
入檀料の相場は、お寺によって異なりますが、相場は10万円~30万円です。
また、墓を建てることを入檀の条件にしているお寺もますので、事前に確認をしておきましょう。
年会費
年会費は、お寺の維持費や墓地の管理費など、お寺の運営のために利用されるお金です。
相場は年間5,000円~2万円です。
毎月約500円~1,500円程度になります。
寄付金
寄付金は、お寺の修繕や改修の際などに求められることがあります。
金額は任意の場合が多いですが、お寺によっては金額が決まっていたり、一口いくらなど、目安の金額が示されることがあります。
その他費用
このほかに、葬儀や法事を行うたびにお布施を渡すことになります。
お布施の相場など詳細についてはこちらをご覧ください。
関連:新盆・初盆の意味とは?時期とやることは?お布施の相場やお返しは?
関連:葬儀でのお布施の渡し方のタイミングやマナー、書き方や相場(金額)について
関連:【卒塔婆】読み方と意味とは?卒塔婆の書き方と値段、処分の仕方
檀家をやめることはできる?
もちろん檀家をやめることはできます。
檀家をやめることを「離檀(りだん)」といいます。
離檀の理由は、
- 親が亡くなってお墓の後継者がいないから
- 遠方へ引っ越すから
- 経済的負担が大きいから
- 宗教観が変化したから
などさまざまです。
家族や親族と話し合って離檀すると決めたら、菩提寺に相談しましょう。
これまで菩提寺として先祖供養を行ってくれたことへの感謝を伝え、檀家をやめたい理由を説明し、離檀するにはどうすれば良いのか相談します。
離檀することを決めたとはいえ、菩提寺には「相談をする」という姿勢を忘れないようにしましょう。
一方的に「離檀することに決めました」と事後報告するのはトラブルの元です。
離檀を菩提寺から引き止められることもありますが、これまでの感謝をきちんと伝え、丁寧に離檀の理由を説明し、菩提寺に理解してもらいましょう。
離檀の際には「離檀料」を菩提寺に渡します。
相場は3万円~15万円で、これまでお世話になった感謝の気持ちとして渡します。
離檀するには菩提寺にあるお墓を撤去して更地に戻す「墓じまい」をする必要があります。
納骨堂を解約する場合も「墓じまい」といいます。
墓じまいについては以下の記事を御覧ください。
関連:墓じまいの流れを簡単にわかりやすく解説!墓じまいしないとどうなる?
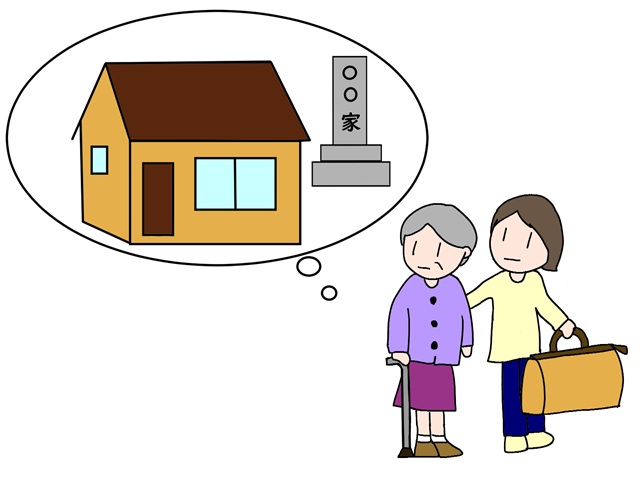
檀家とはどういうものなのか、わかりましたね。
江戸時代から始まった制度なので多くのご家庭では先祖代々お世話になっている菩提寺があるようですね。
さまざまな事情により檀家をやめるご家庭もありますが、その際には、これまでお世話になってきた菩提寺への感謝の気持ちを忘れないようにしたいですね。
関連:「僧侶」「住職」「和尚」「お坊さん」の意味と違いとは?
関連:「神道」と「仏教」を簡単に説明!その関係と違いと共通点とは?

コメント