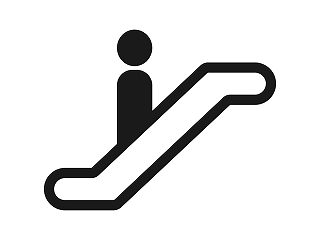
同じ日本国内でも関東と関西では驚くほど習慣が違うことがあります。
それは言葉づかいや食べ物、季節の行事など多岐にわたります。
小さな違いですがエスカレーターを乗る位置にも関東と関西では違いが見られます。
関東では自分から見て「左側」に立ち、右側を空けて人が通れるようにし、関西では「右側」に立ち左側を人が通れるようにする人が多いようです。
では、なぜ関東と関西でエスカレーターの立ち位置が違うのでしょうか?また境界線はどこにあるのでしょうか?
関東が左側の理由
なぜ関東が左側に立つようになったのか、はっきりとした理由がわかっていませんが、諸説あります。
刀の鞘(さや)を腰に差していた時の名残があるから
今昔変わりなく、日本人は右利きの人が多いです。
武士や侍が腰に刀の鞘(さや)を差す場合、右利きの人は左側に差していました。

そのため、道の右側を通るとすれ違う時に鞘が他の人の鞘に当たってしまう恐れがあります。
それを避けるため左側を通ったといわれており、その名残りで左側に立つようになったのではないか、という説があります。
右側通行のルールにあわせたから
道路交通法第10条第1項(対面交通の原則)では、歩道または路側帯と、車道の区別がない道路を歩く場合、歩行者は右側を歩くこと、となっています。
(但し、道路の右側端を通行することが危険であったり、やむを得ない場合はこの限りではありません)
この「歩行者は右側を歩く」という交通ルールに基づいて、エスカレーターに乗るとき、歩く人は右側を歩き、立ち止まる人は左側に立つようになったという説があります。
関西が右側の理由
関西が右側に立つようになった理由も諸説あります。
胸元に入れた財布を盗まれないようにするため

昔は、財布を着物の胸元に入れていましたが、着物の合わせが右前なので、自分から見て右側から胸元に手を入れて財布を出し入れしていました。
そのため、商人が多い関西では、右側から手を入れられて財布が盗まれないよう、他人に対して右側に立つようになったという説があるそうです。
右前とは、着物や着る際に、着る人から見て右側の襟が下になることをいい、左側が上になります。
阪急梅田駅で右に立つようアナウンスがあったから

大阪阪急梅田駅は昭和42年(1967年)、3階乗り場に通じる長いエスカレーターを設置しました。
その時、エスカレーターの利用者に対して、急いでいる人のために左側を空けるようアナウンスを流したと言われています。
この阪急梅田駅の右側に立つ習慣が大阪全体に浸透したのではないか、という説です。
このアナウンス自体は、右手が不自由な人は左側に立って左手で手すりを持たざるを得ない、という指摘を受け平成10年(1998年)に終了しています。
大阪万博で国際ルールに則り、右側に立つようになった
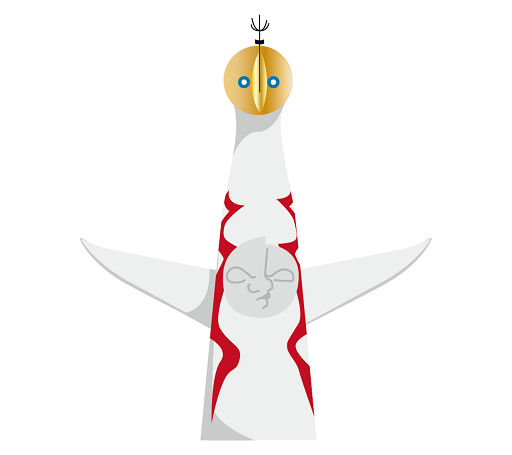
世界的にみるとエスカレーターは右側に立ち、左側を空けることが多いようです。
大阪万博が昭和45年(1970年)に開催された時、会場では国際ルールを採用して右側に立ち、左側を空けるよう、呼びかけをしました。
そのため、右側に立つことが大阪に浸透したのではないか、という説があります。
立ち位置の境界線はどこ?
東京は左側に立ち、大阪は右側に立つ習慣があるというのは間違いないでしょう。
また、はっきりと断言はできませんが、関西で右側に立つ習慣があるのは大阪府とその周辺の京都府・奈良県・兵庫県で、同じ関西でも滋賀県や和歌山県では左側に立つようです。
(※関西は、大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県の2府4県)

京都は県外や海外からの観光客が多いため、先に乗っている人に臨機応変に合わせる、という人も多いようですよ。
関西以外の西日本では左側に立つ習慣があり、全国的にみるとほとんどの地域で左側に立ち、右側を空けるようです。

歩いてエスカレーターを使う人が原因で転倒事故が増えていることから、最近は立ち止まってエスカレーターに乗ることを推奨されているようです。
埼玉県では事故防止のため、利用者に立ち止まってエスカレーターに乗ることを義務付ける条例が施行されました(2021年10月1日施行)。
この条例は全国初の取り組みで、利用者だけでなく管理者にも周知徹底が求められています。
立ち止まって乗ることが基本となるため、従来のように左右どちらかを空ける必要はなくなります。
近い将来エスカレーターの真ん中に乗るのが標準になる日がくるかもしれませんね。
これまでの習慣を変えるのは簡単なことではありませんが、諸事情で左右どちらかにしか立てない人や、親子連れなど両側に並んで利用する人もいますから、みんなが安全に利用できるようになると良いですね。
関連:日本が左側通行になったのはいつから?その理由とは?左側通行の国はどこ?
関連:関東と関西の違い!食べ物や言葉、文化の違いをまとめてみました!
関連:関東と関西はどこからどこまで?それぞれ何県あるの?「関」の意味とは?

コメント
コメント一覧 (8件)
東京の電車は走るのが遅いですが、大阪の電車は速いです。
過去何度か西武線等に何度か乗りましたが、かなり速度が遅いと思います。
最初乗ったときは、「快速」あるいは「急行」だったと思いますが、信号待ちか何かで遅れているのかと思ったくらいです。
もちろん、ラッシュ時でしたので、通常とは違うのかもしれませんが?
逆に、東京の友人たちが大阪で南海電車に乗ったときには、「こんなに速く走ったら、危険だろう。」と言っていました。
コメントありがとうございます。
関西は商人の心で右の着物に財布を入れていたから、それを取られない様に、右に並んでると聞きました!江戸は、刀が金より戦いとの思いで、左に並ぶと教えてもらいました!
コメントありがとうございます!
貴重な情報ありがとうございましたm(_ _)m
昔はともかく今でも片方は歩くものという誤った考え方が常識になっている人は多いです。通路を空けろ位の勢いで我が物顔で横の停止者にガンガンぶつかりながら歩く人もしばしば、意識不足ですね。階段は歩く、エスカレーターは止まる エスカレーターは階段より早く移動する目的物ではない事を意識改革したいものです。
コメントありがとうございます!
京都市の京都駅以外は7、8割の人は左を歩くとおもいます。
前、京都市交通局の方に聞いてみると、昔、都があって侍の文化が残って「関西は右」という風潮はあまり広まっていないと思います。しかし、京都駅に行くと通勤時間や休日は右(京都以外の人が多いため)、休日は左が多い傾向です。
読んでいただくとありがたいです
貴重な情報ありがとうございます!