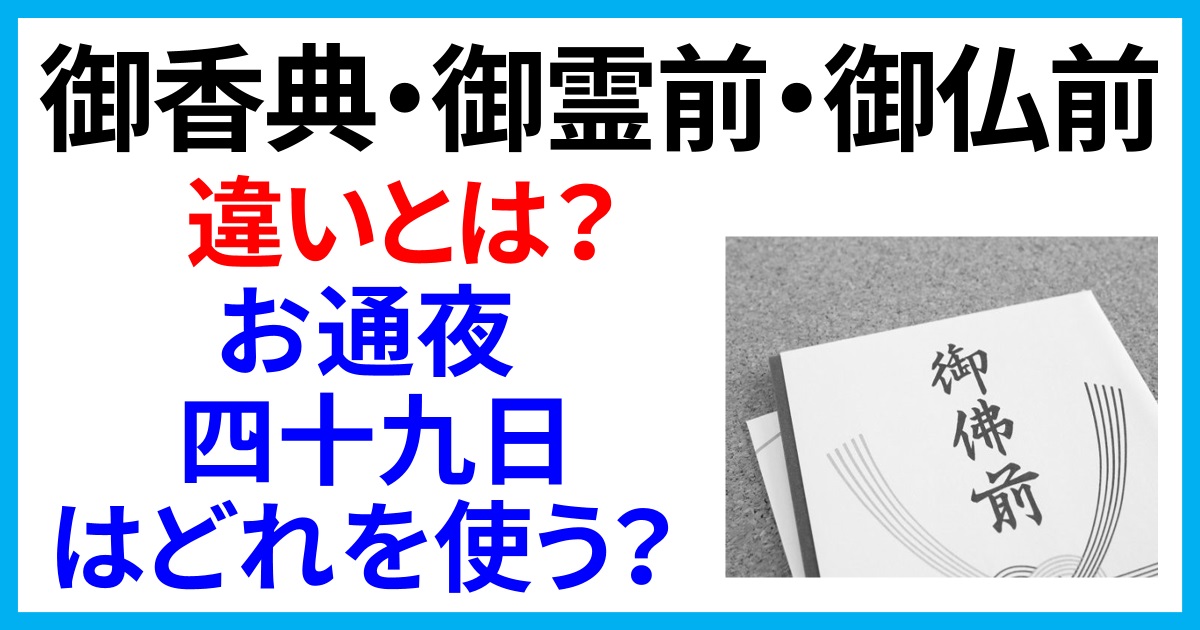
突然やってくるお通夜や葬儀、そしてその後に行われる四十九日法要。
それらに参列するとき、不祝儀袋はどういうものを選んでいますか?
今回は、「御香典」「御霊前」「御仏前」の違いについてわかりやすく解説します。
突然のことに慌てないよう、参考になさってくださいね。
不祝儀袋とは?

読み方は「ぶしゅうぎぶくろ」です。
お通夜や葬儀、法事などの際、現金を包む水引のついた袋です。
「香典袋(こうでんぶくろ)」「お悔み用ののし袋」などとも呼ばれています。
不祝儀袋にはさまざまな表書き(おもてがき)があり、
今回の「御香典」「御霊前」「御仏前」も不祝儀袋の表書きです。
水引については以下のリンク先をご覧ください。
関連:水引(みずひき)とは?結び方の種類や意味とは?水引の使い分け
御香典と御霊前と御仏前の意味とは?
それでは、「御香典」「御霊前」「御仏前」の読み方と意味を見ていきましょう。
御香典
読み方は一般的に「おこうでん」と読みますが、「ごこうでん」と読む人も多くいます。
「香」は線香を、「典」はお供え物を意味します。
お通夜や葬儀、告別式のいずれかに持参するもので、故人にお花や線香のかわりに金銭をお供えします。
「御香典」とは、「御霊前」や「御仏前」を含む、お供え全般のことをいいます。
葬儀という突然の出費に対して、お互いに助け合うという意味もあり、ご遺族に「葬儀費用の一部にあててください」という気持ちが含まれています。
御霊前
読み方は「ごれいぜん」です。
故人の御霊(みたま・霊)の前に供える金品のことを表しています。
御仏前(御佛前)
読み方は「ごぶつぜん」
御仏(みほとけ・仏さま)の前に供える金品のことを表しています。
御霊前と御仏前の違いとは?お通夜、四十九日はどれ?
仏教の場合、一般的には、
お通夜や葬儀では「御霊前」
四十九日を過ぎたら「御仏前」
と書きます。
四十九日法要の御香典は「御霊前」になりますので気をつけましょう。
これは、「人は亡くなると霊になり、四十九日法要を終えると成仏し極楽浄土へ向かう」と考えられているからです。
四十九日以降の法要では「御仏前」と書きます。
また、仏教の中でも、 真宗(浄土真宗や真宗大谷派など)は、四十九日の前でも「御仏前」と書きます。
これは、真宗では「人は亡くなったらすぐに成仏し浄土へ向かう」と考えられているからです。
ですので、お通夜や葬儀の時にも「御仏前」と書いたものを準備しましょう。
宗派が分からない場合は「御香典」と書くのが無難ですね。

それぞれの違いがわかりましたか?
ほとんどの仏教では四十九日が過ぎるまでは「御霊前」、過ぎたら「御仏前」
真宗など一部の仏教では通夜から「御仏前」
宗派が分からない場合は「御香典」
と覚えておきましょう。
宗派や地域によって細かいしきたりやマナーもあるようですので、もしも確認できるような間柄であるのなら、ご遺族に失礼のないよう尋ねるのもいいかもしれません。
関連:お葬式の時にごはんに箸を立てるのはなぜ?お骨を箸渡しするのはなぜ?
関連:「僧侶」「住職」「和尚」「お坊さん」の意味と違いとは?

コメント