
4月29日は「昭和の日」です。
「昭和の日」の前は「みどりの日」、その前は昭和天皇の「天皇誕生日」という祝日だったのを覚えている方も多いと思います。
昭和の日は、もともと昭和天皇の誕生日だったわけですが・・・なぜ明治の日や大正の日、平成の日はないのでしょうか?
今回はそんな疑問についてわかりやすく解説します。
昭和の日とは?

昭和の時代、4月29日は「天皇誕生日」という祝日でした。
しかし、昭和64年(1989年)1月7日に昭和天皇が崩御され、平成へと年号が変わり、上皇陛下のお誕生日である12月23日が「天皇誕生日」という祝日になりました。
このとき、ゴールデンウィークの一角を構成する、4月29日の祝日を廃止することによる国民生活への影響が懸念されたことから、4月29日を「みどりの日」という祝日として存続することにしました。
「みどりの日」という名前は、昭和天皇が自然をこよなく愛され、生物学者としてもご活躍されたことが由来です。
その後、多くの国民の要望を受けて、平成17年(2005年)の祝日法改正により、4月29日は「昭和の日」となり、「みどりの日」は5月4日に移動しました。
祝日法では昭和の日を「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧(かえり)み、国の将来に想いをいたす」としています。
「昭和の日」は、昭和天皇とともにあった激動の時代を改めて見つめなおす日になっているのですね。
明治の日がない理由
11月3日は「文化の日」です。
実は、この「文化の日」は明治天皇の誕生日なのです。

明治天皇
11月3日は明治時代(1868年~1912年)には「天長節(天皇誕生日のこと)」という祝日でした。
明治天皇が崩御されると、国民は「近代日本の礎を築いた明治天皇の功績を後世に伝えていくために11月3日を祝日としてほしい」と運動を起こし、昭和2年(1927年)に「明治節」という名称で祝日になりました。
しかし、敗戦後の昭和22年(1947年)、当時日本を占領していたGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、「明治節」を廃止しました。
日本弱体化を考えていたGHQは、天皇と国民の繋がりを少しでも排除しようとしたのでしょう。
明治節が廃止された後、明治天皇の誕生日である11月3日を「憲法記念日」にしようという動きがありました。
日本国憲法の前の大日本帝国憲法の公布日は2月11日でした。
現在、2月11日は「建国記念の日」ですが、もともとは「紀元節」といって、日本の初代天皇とされる神武天皇の即位日でした。

神武天皇
神武天皇の即位日という、縁起の良い日を選んで大日本帝国憲法を公布したことに倣(なら)って、新憲法(現在の日本国憲法)の公布日を明治節である11月3日にしたともいわれています。
そして、公布日である11月3日を「憲法記念日」にするという話があったそうです。
しかし、11月3日は明治節でもあったため、天皇と国民の繋がりを少なくさせたいと考えているGHQは、国にとって重要な憲法記念日と、明治天皇の誕生日を結びつけたくなかったので強く反対しました。
その後、GHQが「11月3日を憲法記念日以外の祝日にするなら何が良いか」と打診してきたので、昭和23年(1948年)に、近代文化が目覚ましい発展を遂げた明治の時代を念頭に「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とし「文化の日」が制定されたのです。
明治という激動の時代を乗り切り、日本を近代国家に育てた偉大な天皇ですので国民が「祝日として残してほしい」という運動を起こしたのも、わかる気がしませんか?
関連:「昭和天皇」と言うのに「平成天皇」「令和天皇」と言わないのはなぜ?
関連:【2025年】建国記念の日はいつ?建国記念日との違いとは?なぜ「政令で定める日」なの?
関連:【2025年】憲法記念日はいつ?由来と意味とは?文化の日との深い関係
大正の日がない理由

大正天皇の誕生日は8月31日です。
しかし、8月31日は祝日として残っていません。
なぜでしょう?
大正天皇が崩御されたあと「名称を変えて残そう」という運動がなかったことや、大正時代は15年間と短かったこと、明治天皇や昭和天皇のように後世に伝えたい偉業がないなど、さまざまな考え方があるようですが、祝日法で定められませんでした。
平成の日がない理由
平成の時代の天皇は、上皇陛下(じょうこうへいか)です。
「上皇陛下」は第125代天皇・明仁(あきひと)陛下の称号で、平成31年(2019年)4月30日に退位されました。
すでに説明したとおり、昭和の日は、昭和天皇が御存命のころは「天皇誕生日」という祝日でしたが、崩御されて「みどりの日」になり、その後「昭和の日」という祝日に名称が変更されたのでしたね。
また、文化の日も、明治天皇が御存命のころは「天長節」という祝日でしたが、崩御されてから「明治節」となり、その後「文化の日」という祝日に名称が変更されました。
このような経緯があるため、御存命中の上皇陛下の誕生日を祝日にするのがふさわしいのかどうかという議論があるようです。
ほかに、上皇陛下の誕生日を祝日にすることで、今上天皇(現在の天皇)との間で二重権威が生じる懸念があるともいわれています。
上皇様は退位なさってからは一切の御公務から退かれており、国の象徴としての天皇は今上天皇ただおひとりです。
しかし、上皇様の誕生日を祝日にした場合、退位なさったはずの上皇様にも権威が生じ、今上天皇の権威が損なわれる可能性があるといわれています。
また、歴代天皇の誕生日がすべて祝日になっているわけではないので、今後「平成の日」という祝日が作られるかどうかも現時点ではなにも決まっていません。
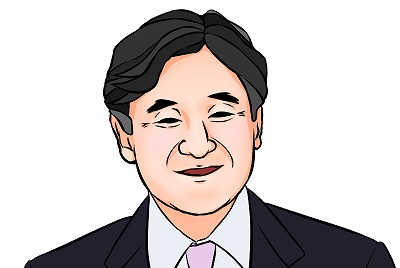
明治の日や大正の日、平成の日ががない理由がわかりましたね。
現在の天皇誕生日は2月23日になっており、今上天皇は126代目です。
もしも今までの天皇誕生日がすべて祝日となっていたら・・・大変なことになりそうですよね。
大正天皇の誕生日が祝日として残っていないのが特別なのではなく、明治天皇と昭和天皇の誕生日が祝日として残っているのが特別なのです。
明治天皇も昭和天皇も国民にとても愛されていたことがわかりますね。
関連:「昭和天皇」と言うのに「平成天皇」「令和天皇」と言わないのはなぜ?
関連:天皇誕生日(祝日)は今後変わる?年号が変わるたびに増える?
関連:玉音放送の全文と意味(現代語訳)とは?簡単にわかりやすく解説

コメント
コメント一覧 (3件)
この理由は間違っている。
大正天皇のお生まれになったのは8月31日、この日は明治天皇崩御に伴う服喪期間に含まれており、お祝い事が憚られたため、大正天皇の天長節は実際の誕生日と異なり、10月31日になっていた。
本当の誕生日ではないため、あえて残さなかったと考えるべきだろう。また、8月31日は義務教育学校では夏休みに当たり、あえて休みの日にすることはないと考えられたことも影響している。
明治節の廃止や、憲法記念日がいつになるかについてGHQの関与を明言して下さっているのは良いと思います。戦争の生き証人が死に絶えるまで隠されていた戦争の真実を、日本人は勉強するべきです。
今後は6月と12月の新たな祝日の日に期待します。