
4月29日「昭和の日」
5月4日「みどりの日」
5月5日「こどもの日」
ゴールデンウィークは祝日が目白押しですが、今回は、そんなゴールデンウィークの中の祝日「憲法記念日」の意味と由来をご紹介します。
憲法記念日はなぜ5月3日になったのでしょうか?
また、憲法記念日は文化の日との深い関わりがあるようなのですが、それは一体どういうことなのでしょうか?
文化の日との違いも合わせてご紹介します。
憲法記念日はなぜ5月3日?意味と由来とは?
「憲法記念日」は、毎年5月3日です。
2025年の「憲法記念日」は5月3日(土)です。
読み方は「けんぽうきねんび」です。
「日本国憲法が施行されたことを記念し、国のさらなる成長を期待する」という意味が込められています。
日本国憲法は、昭和22年(1947年)5月3日に施行されました。
そして、昭和23年(1948年)に施行日の5月3日が「憲法記念日」という祝日に制定されたのです。

日本国憲法の施行日は昭和22年(1947年)5月3日です。
また、公布日は半年前の昭和21年(1946年)11月3日です。
「施行(しこう・せこう)」とは
「法令の効力を発生させること」です。
「施行日」は簡単にいうと「法令の効力が実際に発生する日」です。
「公布(こうふ)」とは
「法令や条約などを公示(広く知らせること)すること」です。
「公布日」は簡単にいうと「新しくできた法律を国民に発表する日」です。
つまり、昭和21年11月3日に新しくできた日本国憲法の内容を国民に発表し、昭和22年5月3日に日本国憲法の効力が発生したということになりますね。
公布から施行まで半年間ありますが、これは、半年間の間に国民に日本国憲法の内容を知ってもらうための期間です。
日本国憲法に限らず、法律は公布から施行まである程度の期間が設けられています。
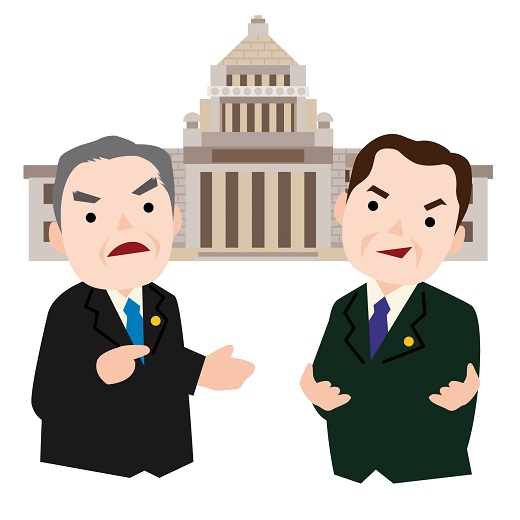
日本国憲法は、まず初めに公布日をいつにするか話し合われたそうです。
5月1日にした場合、メーデー(世界各地で行われる労働者の祭典)と重なってしまいます。
また、5月5日にした場合は、端午の節句(たんごのせっく)と重なってしまいます。
そこで「5月1日と5日の間の、5月3日にしたら良いのではないか」と話がまとまり、日本国憲法の施行日は5月3日に決まったそうです。
その後、施行日の半年前である11月3日が公布日になりました。
このような経緯で、日本国憲法の施行日は昭和22年(1947年)5月3日、公布日は前年の昭和21年(1946年)11月3日となったといわれています。
関連:メーデーの意味と由来とは?日本はどうして祝日ではないの?
関連:「端午の節句」の意味と由来「こどもの日」の違いとは?なぜ柏餅、粽(ちまき)を食べるの?
憲法記念日と文化の日の深い関係とは?
現在、11月3日は文化の日という祝日ですが、明治時代には「天長節(てんちょうせつ)」といって明治天皇の誕生日をお祝いする祭日でした。

明治天皇が崩御(ほうぎょ・亡くなること)された後、国民が「近代日本の礎を築いた明治天皇の功績を後世に伝えていくために11月3日を祝日としてほしい」ということで運動を起こし、昭和2年(1927年)に「明治節」という祭日になりました。
しかし、敗戦後の昭和23年(1948年)、当時日本を占領していたGHQの命令により、「明治節」は廃止されました。
GHQは、日本国民と天皇の繋がりを少しでも排除したかったのがその理由といわれています。

日本国憲法の前の「大日本帝国憲法」の公布日は2月11日でした。
現在、2月11日は「建国記念の日」ですが、もともとは「紀元節(きげんせつ)」といって、日本の初代天皇とされる神武天皇(じんむてんのう)の即位日です。
神武天皇の即位日という、縁起の良い日を選んで大日本帝国憲法を公布したことに倣(なら)って、新憲法(現在の日本国憲法)の公布日を明治節である11月3日にしたともいわれています。
そして、「憲法記念日」はもともと公布日である11月3日にするという話もあったそうですが、GHQが強く反対しました。
GHQは天皇と国民の繋がりを少なくさせたい、なくしたいと考えていたため、国にとって重要な憲法記念日と、明治天皇の誕生日を結びつけたくなかったからです。

そのかわり「憲法記念日じゃなければいい」ということで、「文化の日」という祝日になったそうです。
また、日本国憲法が平和と文化を重視していることも「文化の日」になった理由です。
このような経緯があり「憲法記念日」は公布日ではなく施行日の5月3日になったのですね。
関連:【2025年】建国記念の日はいつ?建国記念日との違いとは?なぜ「政令で定める日」なの?
関連:文化の日の由来とは?2025年の無料スポット!美術館・博物館など
憲法記念日と文化の日の違い
「憲法記念日」と「文化の日」の違いは以下の点です。
日にちが違う
憲法記念日は5月3日
文化の日は11月3日
趣旨が違う
憲法記念日の趣旨は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」
文化の日の趣旨は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」
制定された日が違う
憲法記念日は日本国憲法の施行日
文化の日は日本国憲法の公布日

日本国憲法については、学校の授業で習った覚えがありますが、5月3日になった理由は今回記事を書くに当たって初めて知りました。
戦後、GHQの厳しい指導のなかで天皇家につながる祝日を作ることは難しかったでしょうから、あえて11月3日を公布日にしたのかもしれません。
結果的に11月3日は憲法記念日とはなりませんでしたが、文化の日となってめでたく祝日になりました。
明治天皇が如何に国民から愛されていたかということを窺い知ることができるエピソードですよね。
関連:「明治の日」制定の動き。明治天皇の誕生日はいつ?祝日はどうなる?
関連:天皇誕生日(祝日)は今後変わる?年号が変わるたびに増える?
関連:2月23日が天皇誕生日になったのはいつから?12月23日はどうなる?

コメント