
北国では本格的に雪が降り初め、ほかの地域では紅葉が見ごろを迎え、そして散っていく11月。
過ごしやすい秋から、寒さの厳しい冬へと季節が移り変わっていく時期でもありますね。
そんな11月にはどのようなイベントや行事があるのでしょう?
今回は、11月のイベント、行事、記念日、風物詩をまとめてみました!
11月のイベント一覧
1. 赤い羽根共同募金(10月1日~3月31日)

昭和22年(1947年)に市民主体で「国民たすけあい運動」としてスタートし、翌年から寄付をすると赤い羽根を渡すようになり「赤い羽根募金」「赤い羽根共同募金」と呼ばれるようになりました。
その後、社会福祉法という法律をもとに、中央共同募金会が主催して現在も続いています。
赤い羽根以外の色の募金もあるようですよ。
リンク:赤い羽根共同募金とは?使い道や期間、募金の相場はいくら?緑の羽根との違い
2. 文化の日(11月3日)

1948年(昭和23年)に祝日法により「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として制定された国民の祝日です。
全国の美術館や博物館が入場無料で利用できますので、この機会に足を運んでみるといいですね。
リンク:文化の日の由来とは?2025年の無料スポット!美術館・博物館など
3. 立冬(りっとう)(11月7日ごろ)

暦の上で冬が始まる日です。
季節の変わり目で昼夜の寒暖差が厳しいころでもありますので、体調管理をしっかりして冬に備えましょう。
リンク:立冬とは?2025年はいつ?食べ物は何を食べたらいいの?
4. 七五三(11月15日)

子どもが三歳、五歳、七歳のときに、子どもの健康と成長を願うために神社へ参拝する行事です。
11月15日にこだわらず、11月に入ると日本各地の神社で七五三のお参りをする家族連れを多く見かけますね。
リンク:七五三のお参りは時期はいつ?男の子と女の子のお祝いはどうするの?
リンク:七五三に千歳飴を食べるのはなぜ?その由来とは?千歳飴が長い理由と色の意味
リンク:七五三のお参りの時期はいつ?男の子と女の子のお祝いはどうするの?
5. 新嘗祭(にいなめさい)(11月23日)

五穀豊穣の収穫祭です。
新嘗の「新」は新穀(初穂)を、「嘗」はご馳走を意味し、天照大御神(あまてらすおおみかみ)はじめ天神地祇(てんじんちぎ すべての神々)に初穂をお供えします。
また、天皇陛下も初穂を召し上がりになり、神様の恵みによって初穂を得たことを感謝するお祭りです。
6. 勤労感謝の日(11月23日)
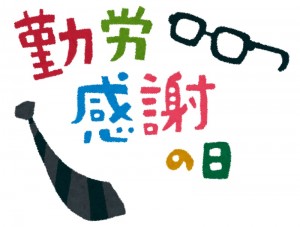
「勤労を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう日」として、昭和23年(1948年)に祝日として制定されました。
戦前は「新嘗祭」という祭日でしたが、戦後「勤労感謝の日」に変更されました。
一般的には勤労感謝の日として祝日を楽しみますが、同じ日に宮中では新嘗祭が行われているのですね。
リンク:勤労感謝の日の意味や由来とは?2025年おすすめイベント情報
7. 酉の市(11月の酉の日)

酉の市(とりのいち)とは、11月の酉の日に日本武尊(やまとたけるのみこと・古代日本の皇族)を祀(まつ)る神社を中心に行われる祭りや市のことです
酉の祭(とりのまち)や大酉祭(おおとりまつり)、お酉様(おとりさま)とも言われています。
縁起熊手を購入する人が多く、前年より大きな熊手を購入すると良いそうですよ。
リンク:【2025年】酉の市とは?熊手の値段の相場は?飾り方や処分について

11月3日と、11月23日、11月には2回祝日があります。
紅葉が美しく、気候も穏やかな時期の祝日は、みなさんもいろんなところへお出かけすることと思います。
「お休みだ!」と喜ぶだけではなく、その祝日にどういう意味があるのかを知ると、過ごし方や気持ちが少しだけ変わるかもしれませんね。

コメント
コメント一覧 (2件)
本当にありがとうございます 私は11月の行事を全部知りませんでしたから、本当に役に立っています
お役に立てて幸いです!