
5月といえば、ゴールデンウィークを思い浮かべますよね?
どんな風に過ごすか考えるだけでワクワクするという方もいらっしゃるのでは?
5月には、ゴールデンウィークのほかにいろいろなイベントがあります。
5月のイベント・行事・記念日・風物詩をまとめてみました!
5月のイベント一覧
1. 十三参り(3月13日~5月13日)

十三参り(じゅうさんまいり)とは、数え年で13歳になった子どもが、健やかに成長したことを感謝し、知恵と福徳を授かるために「虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)」にお参りする行事です。
京都や大阪を中心に行われてきた行事で、最近はほかの地域にも広がっているようです。
リンク:「十三参り」の意味とは?2025年はいつ?京都・大阪・東京の時期
2. 潮干狩り(4月~5月ごろ)

潮干狩り(しおひがり)とは、潮が引いた砂浜で、砂の中の貝などを採取することで、「貝掘り(かいほり)」「貝拾い(かいひろい)」ということもあります。
潮干狩りは3月から7月がシーズンで、最も適しているベストシーズンは4月~5月です。
潮干狩りに適した日時を調べたり、必要な持ち物を確認したり、事前にしっかり準備をして楽しんでくださいね!
リンク:潮干狩りに必要な道具や持ち物!潮干狩りの無料スポットを紹介
3. ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)

ゴールデンウィークとは4月下旬~5月上旬にかけて、国民の祝日が集中して発生する連休のことで、「大型連休」「黄金週間(おうごんしゅうかん)」ともいいます。
祝日と土日の繋がりがうまくいかない場合は最大3連休という年もありますが、有給休暇も組み合わせると10連休になる年もあります。
リンク:2025年のゴールデンウィーク(GW)はいつからいつまで?何連休になる?
4. メーデー(5月1日)

メーデーは、5月1日に世界各地で行われる労働者の祭典のことです。
80以上の国が5月1日を祝日として定めていますが、日本では5月1日に近い土日に開催するそうです。
労働者の権利を主張する日ということで、自分の働き方を見つめなおすきっかけになるかもしれませんね。
リンク:メーデーの意味と由来とは?日本はどうして祝日ではないの?
5. 八十八夜(5月2日ごろ)

八十八夜というと「茶摘み」という歌をついつい口ずさんでしまいそうですね
新茶が摘まれる季節でもあり、毎年この季節が待ち遠しい!という人もいらっしゃるようですよ。
リンク:【2025年】八十八夜の意味とは?なぜ夜?八十八夜のお茶が縁起物である理由
6. 憲法記念日(5月3日)
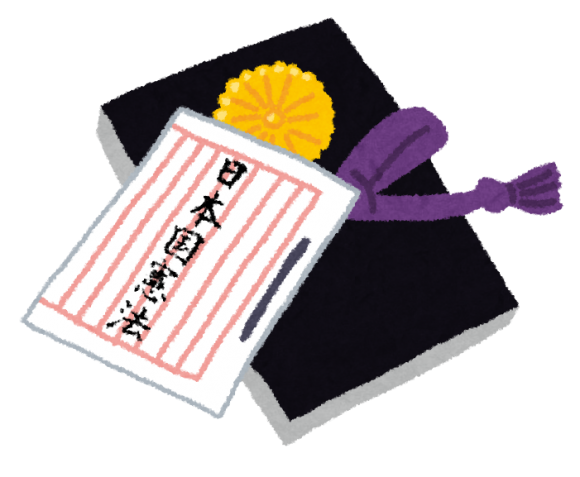
日本国憲法が昭和22年(1947年)5月3日に施行されたことを記念して、昭和23年(1948年)に「憲法記念日」という祝日として制定されました。
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨とした祝日です。
日本国憲法の3つの基本原則などを改めて確認しておきたいですね。
リンク:【2025年】憲法記念日はいつ?由来と意味とは?文化の日との深い関係
7. 博多どんたく(5月3日、4日)
「博多どんたく」とは、正式名称を「福岡市民の祭り 博多どんたく港祭り」といいます。
福岡県福岡市内のとても広い範囲で開催されますので、事前にどこでなにをしたいのかある程度決めていくと良いようです。
観客動員数は200万人を越え、国内最大級のお祭といわれていますよ!
リンク:博多どんたくのどんたくってどういう意味?しゃもじとお面の意味とは?どこでもらえるの?
8. みどりの日(5月4日)

もともと、昭和天皇の誕生日だった4月29日が「みどりの日」でした。
しかし、平成17年(2005年)の祝日法改正により、4月29日は「昭和の日」、5月4日が「みどりの日」になりました。
みどりの日には、日本各地で自然にしたしむイベントが行われたり、国公立の動物園や公園、植物園などが入園無料になったりします。
リンク:みどりの日の由来とは?5月4日に変わった経緯と昭和の日との違い
9. こどもの日(5月5日)

端午の節句(たんごのせっく)ともいわれ、鯉のぼりや五月人形などを飾り、男の子の健やかな成長を願います。
菖蒲湯に入ったり、粽(ちまき)や柏餅(かしわもち)を食べます。
リンク:「端午の節句」の意味と由来と「こどもの日」の違いとは?なぜ柏餅、粽(ちまき)を食べるの?
リンク:「鯉のぼり」飾る時期としまう時期は?吹き流しの意味とは?
リンク:【2025年】五月人形はいつ出す?飾る時期はいつからいつまで?
リンク:【2025年】菖蒲湯に入るのはいつ?由来と意味とは?効能や、やり方、頭に巻くのはなぜ?
10. 立夏(5月5日ごろ)

立夏(りっか)には「この日から夏が始まる」という意味があります。
この時期は春に咲いた花が散り、緑が生い茂ってくるころで、田植えや種まきが始まる時期でもあります。
リンク:「立夏」の意味とは?2025年はいつ?行事や食べ物は?
11. 三社祭(5月第3金、土、日)

三社祭(さんじゃまつり)は、毎年5月に行われる浅草神社の例大祭(毎年決まった日に行われる、その神社にとって最も重要な祭祀のこと)です。
町内の氏子が所有する約100基の神輿、浅草神社が所有する3基の神輿が担がれ、町内を渡御(とぎょ・神輿が進むこと)します。
江戸っ子気質の氏子たちの神輿は、担ぎ方が威勢よく、荒々しく激しいので見ごたえがありますよ!
リンク:浅草神社の「三社祭」はなぜ三社なの?三社の意味とは?
12. 梅雨入り(5月)

最初に梅雨入りするのは、平年値が5月9日ごろの沖縄県です。
その後、少しずつ北上していきます。
リンク:「梅雨入り」「 梅雨明け」平年値はいつ?基準や定義とは?
リンク:梅雨はなぜ「梅」という漢字を使うの?なぜ「つゆ」と読むの?梅雨の別名
13. 母の日(第2日曜日)

お母さんに感謝の気持ちを伝える日ですね。
カーネーションだけではなく、家電を贈ったり、美味しいものを食べに行ったり、旅行に行ったりと、いろいろな贈り物がありますね。
普段頑張ってくれているお母さんに、この日くらいはゆっくりしてもらいたいですね。
リンク:【2025年】母の日はいつから日本に広まった?由来は森永製菓!なぜカーネーション?

祝日が続くゴールデンウィークが5月の初めにあるので、ゴールデンウィークが終わってしまうとちょっと寂しくなったり、気が抜けて五月病になってしまう人もいらっしゃるかもしれませんね。
ですが、新年度はまだまだ始まったばかりですから、無理のない範囲で、気を引き締めて頑張っていきたいですね!
関連:【五月病】読み方と意味とは?なりやすい人の特徴と治し方!六月病や七月病もあるの?

コメント