
1月といえば、まず、お正月を最初に思い浮かべますよね。
「今年はこんな年にしよう」「今年の目標は〇〇だ」と、気持ちも新たに最初の一歩を踏み出す人も多いかもしれません。
1月はお正月以外にも、たくさんのイベントや行事があります。
新しい一年が始まる1月のイベント、行事、記念日、風物詩をまとめてみました!
1月のイベント一覧
1. 初日の出(元旦)

その年の最初の日の出のことを初日の出といいます。
初日の出を拝むことで、年神様へその年の豊作や幸せを願うのです。
リンク:初日の出を見る意味って何?初日の出とご来光の違いとは?
2. 若水(1月1日)

「若水(わかみず)」とは元旦(元日の朝)に初めて汲む水のことです。
若水を飲むと一年の邪気が祓(はら)えるといわれており、飲んだり料理に使ったりします。
リンク:若水の読み方と意味とは?いつの季語?若水汲み、福茶って何?
3. 四方拝(1月1日)

四方拝(しほうはい)は一般公開されておらず詳細は不明ですが、天皇陛下が元旦(元日の朝)に神々を拝んでその年の災いを祓い、五穀豊穣を願う神事です。
リンク:【2024年】天皇陛下の正月祭祀「四方拝」の意味とは?やり方や呪文とは?
4. 初夢(新年最初に眠ったときの夢)

初夢とはいつみた夢なのか諸説あるようですが、一般的には「新年最初に眠った日の夜に見た夢」なのだそうです。
「一富士、二鷹、三茄子」がとても有名ですが、これには続きがあって6番目まであるそうですよ!
リンク:【初夢】一富士二鷹三茄子の意味と由来。続きがあるって本当?
リンク:「初夢」はいつ見る夢?「大晦日の夜?」「元日の夜?」
5. 書き初め(1月2日)

1月2日に、その年最初の書や絵を書くことによって、書や絵の上達を願う行事です。
子どもたちの学校の宿題だけではなく、地域で書き初め大会が行われることもありますので、ご家族全員で楽しむのもいいかもしれませんね。
6. 箱根駅伝(1月2日、3日)

正式名称は「東京箱根間往復大学駅伝競走」といい、学生長距離界最長の駅伝競走です。
1日目(往路)は東京都大手町にある読売新聞東京本社ビル前をスタートし、神奈川県箱根町の芦ノ湖駐車場までの107.5㎞を5区間で走ります。
2日目(復路)は逆に神奈川県箱根町の芦ノ湖駐車場をスタートし、東京都大手町にある読売新聞東京本社ビル前までの109.6㎞を5区間で走ります。
1チーム10人がタスキを繋ぎます。
リンク:駅伝の意味と発祥とは?なぜタスキなの?距離は何キロ?
7. 初詣(1月1日、2日、3日)
初詣は一般的にお正月三が日に行く人が多いです。
一年間を過ごせたことに感謝をし、新しい一年の平安と無事を祈るために神社やお寺に初詣に行くのですが、必ずしも三が日に行かなくてはならないものではありません。
初詣で引いたおみくじは、持ち帰っても結んで行っても、どちらでも良いそうですよ!
リンク:初詣の期間はいつからいつまで?その意味とは?神社とお寺どちらがいい?参拝の作法
リンク:意外と知らないおみくじの順位。待ち人の意味は?凶は持ち帰る・結ぶ?
8. おせち料理(1月1日、2日、3日)

おせち料理とは、一年で最も重要でおめでたいとされる正月に作る料理のことです。
昔は家で作っていましたが、現在はお重に詰めた状態で購入することができますね。
中身だけを購入して自分でお重に詰めることもできますから、作るのが苦手なものだけを購入する人もいるようです。
おせち料理の中身は地域や家庭によって異なりますが、ひとつひとつに意味があるようですよ!
リンク:【おせち料理の種類と意味一覧】おせち料理の歴史と由来!どんな願いが込められているの?
9. 人日の節句(1月7日)

人日(じんじつ)の節句というとピンとこないかもしれませんが「七草の節句」というといかがですか?
春の七草を使って作ったお粥をいただいて、年末年始の暴飲暴食で疲れた胃腸を労わったり、一年間の無病息災を願う行事です。
リンク:人日の節句の読み方と意味とは?七草粥はなぜ食べる?春の七草の覚え方
リンク:七草爪とは?1月7日に爪を切ると風邪を引かないと言われるのはなぜ?
10. 十日戎(1月10日)

十日戎(とおかえびす)は、1月10日および、その前後の9日、11日に行われるえびす神社のお祭りのことです。
「福笹(ふくざさ)」や「熊手」を飾って商売繁盛を願います。
リンク:十日戎の由来とは?笹や熊手を飾る意味と飾り方は?処分はどうするの?
11. 松の内(地域によって異なる)

松の内(まつのうち)とはお正月飾りを飾っておく期間のことで、関東では1月7日、関西では1月15日となっています。
江戸時代(1603年~1868年)までは日本全国同じ日で、松の内は1月15日までだったそうですよ。
リンク:松の内の意味とは?いつからいつまで?なぜ関東と関西で違う?
12. 寒中見舞い(松の内が明けて立春まで)
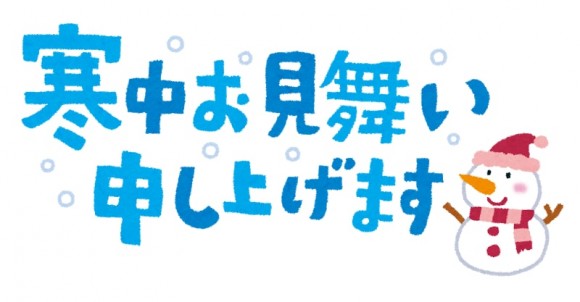 一年で一番寒い時期に相手の健康を気遣って出す便りのことです。
一年で一番寒い時期に相手の健康を気遣って出す便りのことです。
喪中やだし忘れなど、年賀状の返礼として送ることもあります。
お正月飾りを飾っておく期間である松の内が明けてから、立春(2月3日ごろ)までに出しますが、松の内は関東では1月7日、関西では1月15日となっています。
リンク:【2024年】寒中見舞いはいつからいつまで出す?書き方の文例・テンプレート
リンク:「寒中見舞い」気の利いた一言・メッセージ・添え書き例文まとめ
13. 鏡開き(地域によって異なる)

お正月に飾っていた鏡餅をいただく日です。
関東と関西で松の内が異なりますので、鏡開きの日にちも異なるそうです。
松の内が1月7日までの関東では1月11日に、松の内が1月15日までの関西では1月15日または1月20日に鏡開きをすることが多いようです。
リンク:鏡開きの意味と由来とは?2024年はいつ?関東と関西で違う?
14. どんど焼き(地域によって異なる)

締め飾りや門松などのお正月飾り、書き初めなどを燃やして無病息災や五穀豊穣などを祈願する行事です。
松の内が1月7日までの関東では1月11日から1月15日、1月15日までの関西では1月15日から1月中にどんど焼きを行うことが多いようです。
リンク:どんど焼きの意味とは?期間はいつからいつまで?行けなかったらどうする?
15. 初釜(1月初旬)

初釜(はつがま)とは、新年に茶道のお稽古を始める日のことをいい、新しい年を祝う茶道の新年会のようなものです。
初釜の日程に決まりはありませんので、三が日が過ぎたらすぐに行ったり、新年の挨拶が終わったころ(10日ごろ)に行うなど、さまざまです。
リンク:初釜の意味と時期とは?着物と持ち物どうすればいい?初釜の流れ
16. 出初式(1月初旬)

出初式(でぞめしき)とは、消防士、消防団など、消防関係者が行う新年の行事で、「消防出初式(しょうぼうでぞめしき)」とも呼ばれます。
その年の初めての消防演習を行う式を「出初式」といい、地域の住民の前で消防士、消防団の設備や技術を披露して安心してもらう目的や、地域の住民に火災予防に対する意識を持たせる目的があります。
リンク:【2024年】出初式はいつ?はしごに乗るのはなぜ?目的と意味とは?
17. 年明けうどん(1月1日~1月15日)

年明けうどんとは、年明けに縁起を担いで食べるうどんです。
「見たことも聞いたこともない」と思う人が多いかもしれませんが、2000年代になってから始まった習慣のようですよ!
現在は一部地域だけの習慣ですが、いずれ日本中に広まるのかもしれませんね。
18. 成人の日(第2月曜日)

成人式とは、大人になったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い励ます趣旨で1948年(昭和23年)から始まりました。
多くの自治体で成人式が行われ、新成人のお祝いをします。
リンク:成人式の日程、2024年はいつ?流れや内容は?行かないと後悔する?
19. 小正月(1月15日)

小正月は現在は1月15日ですが、旧暦でいう「元日」にあたります。
豊作祈願や悪霊祓い、吉凶占いなどが小正月の主な行事で、小豆粥を食べる習慣もあるそうですよ。
リンク:【2024年】小正月はいつ?語源と由来、行事と食べ物の意味とは?
20. 藪入り(1月16日)

藪入り(やぶいり)とは、江戸時代(1603年~1868年)に都市部の商家に広まった習慣で、旧暦1月16日と7月16日に商家などで住み込みで奉公をしている奉公人(丁稚(でっち))や嫁いだ女性が実家に帰省することをいいます。
旧暦から新暦になったときに日にちがそのまま引き継がれています。
リンク:「薮入り」の意味や由来、語源とは?2024年の日にちはいつ?
21. 二十日正月(1月20日)

二十日正月(はつかしょうがつ)は、正月にお迎えした年神様(毎年お正月に各家にやってくる豊作や幸せをもたらす神様)がお帰りになる日と考えられています。
この日をもって正月の行事は終了しますので、お正月の飾りなどはすべて片付け、正月料理や餅などもすべて食べつくします。
リンク:二十日正月の意味とは?食べ物は何?小豆粥・麦飯・とろろ・ぶり
22. 旧正月(1月下旬~2月中旬ごろ)
旧暦のお正月を「旧正月」といい、中国や韓国、ベトナム、台湾などでは現在も旧正月のお祝いをしています。
日本では横浜、神戸、長崎の中華街など中国の影響が強い地域で盛大にお祝いされています。
リンク:【2024年】旧正月はいつからいつまで?日本ではなぜお祝いしないの?
リンク:「旧正月」とは?2024年はいつ?中国・台湾・韓国・ベトナムのお正月

新しい一年が始まる1月ということで、無病息災や豊作を願ったりする行事が多いような気がしますね。
その年を無事に幸せに過ごせますように・・・という願いは、今も昔も変わらないことなのかもしれませんね。


コメント
コメント一覧 (1件)
もうちょっとだけ行事一覧がほしい。